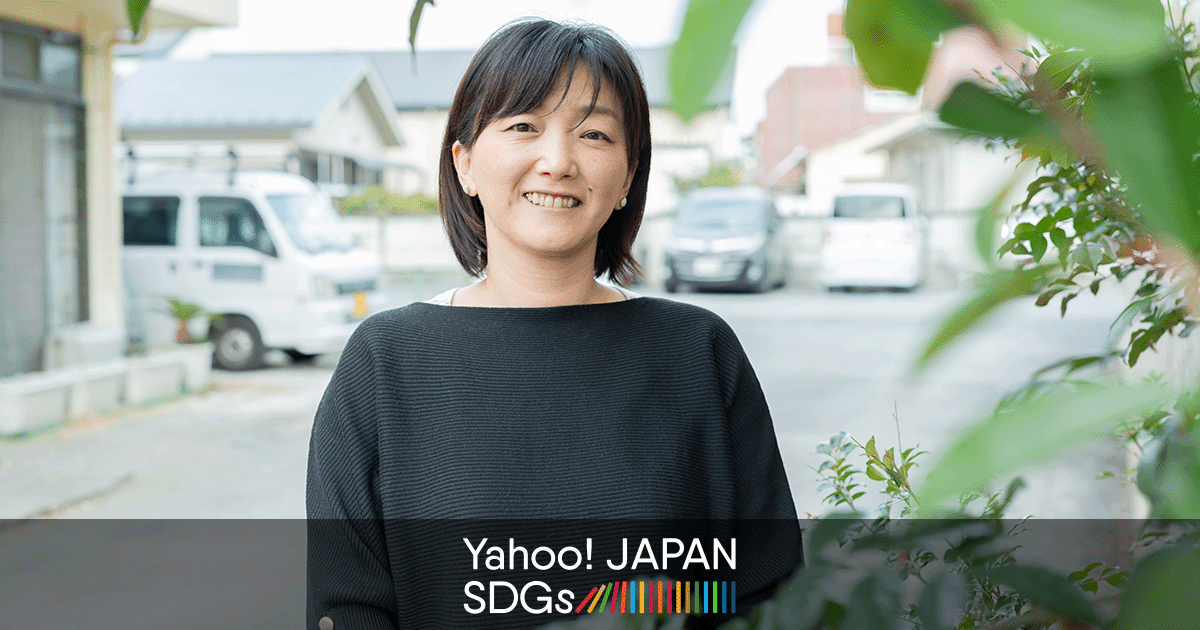あなたが日本語のわからない子だったら? 本当の意味で''多様''な人々が共生する社会のために
現在、日本には海外にルーツを持つ子どもたちがおよそ12万人以上いると言われています。「海外にルーツを持つ」とは、主に両親またはそのどちらか一方が外国出身者である子どものことを指します。
そのため、外国籍の子どもたちはもちろんのこと、中には日本国籍を持ついわゆる「ハーフ」や、難民2世などの理由によって、無国籍状態にある子どもも含まれています。
ここで一度、想像してみてください。家族の事情で来日し、すぐに日本の学校に転入しなければならないという状況を。
日本語がわからず、授業についていくことも、友人をつくることも簡単ではないだろうな......というのは、想像に難くないのではないでしょうか。しかし、自治体や学校によっては、まだまだ日本語教育をはじめとした支援体制が十分に整っておらず、そのまま未就学となってしまう子どもたちもいます。
こうした海外ルーツを持つ子どもたちの問題に、10年以上前から向き合い続けてきた一人の女性がいます。NPO法人青少年自立援助センターが運営する『YSCグローバル・スクール』の事業責任者・田中宝紀(たなか いき)さんです。
田中さんは、16歳のときに単身でフィリピンのハイスクールに留学。 フィリピンの子ども支援NGOを経て、2010年に東京都福生(ふっさ)市で「YSCグローバル・スクール」を立ち上げました。
創設当時を振り返って、「海外ルーツの子どもの支援について知れば知るほど、全国的に何もかも足りていないことがわかった」と話す田中さん。特に福生市をはじめとする、東京都の西側の地域は、在住外国人が多いにもかかわらず、支援が手薄だったと言います。
しかし、なかなか思うように改善されていかなかった状況も、ここ数年の行政の動きやコロナ禍によって少しずつ良い方向に進み始めているのだそう。
この先さらに日本で暮らす外国人が増えていくと予想される中で、本当の意味で多様な人々が共生する社会をつくっていくには、どうしていくべきなのか。海外ルーツを持つ子どもたちを取り巻く現状や、この十年余りで変化してきたこと、そしてこれからのあるべき社会について、お話を伺いました。
「日本語学校」「フリースクール」「塾」の3つを兼ねた学びの場
「YSCグローバル・スクール」は、NPO法人青少年自立援助センターが運営し、海外にルーツを持つ子どもと若者のための専門的教育支援事業として、2010年に始まりました。6才以上の子ども・若者たちの多様なニーズに応える学びの場として、さまざまなカリキュラムが用意され、年間約200名の生徒たちが授業を受けています。
東京都福生市と、足立区竹の塚に教室があり、現在は対面とオンラインのハイブリッド形式で日本語授業を行っています。
── 今授業を受けている生徒の皆さんは、どんなお子さんたちなんですか?
高校受験を終えた中学3年生の子どもたちですね。すでに出身国で中学校を修了していて、日本の高校に進学するまでの予備校代わりに通っている子もいるので、厳密には全員が15歳というわけではありません。
平日の昼間は、不就学や、何かしらの嫌な経験による不登校といった、学校の外側にいる10代が中心です。なかには支援体制がない中学校の代わりに、ここの利用が出席扱いになるケースもあります。日本語学校とフリースクールと、高校進学予備校を兼ねたようなイメージです。放課後の時間帯は、日常会話程度の日本語は問題なくできる子どもたちが、塾代わりに通ってきています。
"いるのが当たり前"。だから支援の必要性が見えづらい
── 日本語が全然わからない子どもたちって、具体的にどんなルーツを持っているのでしょうか。正直、想像しきれていない部分も大きくて......。
さまざまなケースがありますが、典型的なのは、ともに外国籍のご両親から生まれたお子さんですね。
たとえば、お父さんが日本のネパール料理のレストランで働いていて、共に暮らしているケース。先に父親が単身で来日して、途中から母国で暮らすお母さんと子どもを日本へ呼び寄せることが多いです。タイミングはさまざまで、父親の生活環境が安定したり、子どもの教育の区切りがよかったり、ビザがたまたま出たときなどです。
── ネパール料理屋さんの例は、とても身近で想像しやすいですね。
あとは、他にもこんなケースが挙げられます。そして、そういった家族や子どものほとんどが、母国へ帰ることなく、日本で生活の基盤をつくり、暮らし続けます。そもそも、親に引っ越しを告げられたら、子どもはついていくしかないですよね。
── そういう例もあるのか......。福生市には米軍基地があります。都内でも特に在住外国人の方が多い地域だと聞きますが、福生市ならではの特徴はありますか?
このあたりは、米軍基地ができた戦後の1940年代から、駅の反対側に繁華街が広がっていたんです。地域の人からは「赤線(※)」と呼ばれていました。
そこにフィリピンなど、アジア出身の女性が接客する飲食店などが開業し、外国人たちが集まりやすい環境ができた。そこで日本人男性と外国人女性との間に子どもが生まれて......というところから、この福生市に外国ルーツを持つ子どもたちが増えていったんです。
── そんな歴史があったんですね。福生市で暮らす日本の人たちは、街に在住外国人が多いということを、どう捉えているのか気になりました。
街全体の受け止め方としては、「外国の人がいて当たり前」。だから良くも悪くも混ざりすぎていて、支援の必要性が見えづらくなってる部分はあると思います。
── そもそも日本語がわからなかったら、困っていても当事者は声をあげられないし。
そうなんですよね。支援、という視点で体制が整えられはじめたのも、本当にここ数年です。本来は自治体がこの環境をいかして、多文化共生に積極的に取り組むべきだったんだけど、なかなか進んでこなかった。外国出身の方が多い地域の中には、静岡県の浜松市や、愛知県の豊田市(※)のように、積極的に取り組んでいる自治体もあるんですけどね。
ボトルネックになっているのは、深刻な担い手不足
── 外国籍の子どもたちの2万人が不就学という情報を見たのですが、これは本当なんでしょうか。
実は、就学手続きもしていないし、教育も一切受けていないし、行政側が存在を把握していないような、狭い意味での不就学の子は1000人程度です。
残りは、どこで何をしているのかを行政が把握できていない数、という意味なんですよ。ブラジル人学校に通っていたり、帰国しているかもしれない。YSCに通っていたりする場合もあるわけですよね。でも、行政側の情報はアップデートされていない。
── そういうことだったんですね。
"2万人"という数ばかりが一人歩きしていて、良くないなとは思っています。でも一番問題なのは、2万人の子たちについて「外国籍だから把握しなくていい」という状態なんです。
自治体が全く把握していなかった子どもが、家の中で虐待を受けていて命を落とした事件が過去にありました。どんな国籍の子どもでも、その命がどこに存在しているか、安全かどうかを把握できる環境づくりは、絶対的に必要です。
さらに、今は教育を受ける権利を行使したいと意思表明しないと、外国籍の子どもたちは、日本の小中学校に通えません。人道的な観点で子どもの権利をしっかり紐解いて、十分な教育機会を保障するような姿勢に入れたら、日本はもっと変わっていくはずです。
── 福生市は、まだまだ体制の整備が進んでいないというお話もありましたが、日本全体としてはどんな状況なんでしょうか。
めちゃくちゃシンプルに言うと、政府は積極的に動き始めているけれど、外国人住民があまり多くない自治体は、支援の担い手不足などの課題等もあって、そこまで動けていないという状況です。
── 政府がやる気になった経緯というのは?
2018年末の臨時国会で成立した改正入管法で、2019年の4月から「特定技能」という新しい在留資格が創設されたんです。作業着を着て行うような肉体労働を中心とした、いわゆるブルーカラーの労働者の受け入れをする正面のドアが開いたんですよね。
今は国際的に人手不足ですから、それによって人材獲得競争が激化。日本も、海外からの人手を確保する取り組みの一環として、「外国ルーツの子どもたちの日本語教育を、きちんとやっていかなければならない」という気運が高まったんです。
そして2019年には、日本語教育に関する初の法律となる「日本語教育推進法」が制定されて、ようやく自治体関係者も体制づくりに取り組みやすい土壌ができた、という流れができました。
── 2019年って、本当に最近ですね。この問題への関心の低さを表しているように感じます。しかも、担い手がいない......。
日本語教師自体の数も足りていないし、自治体が国の補助金を使ったとしても、日本語教師の方が安定して働けるだけの待遇にならないんですよね。予算が十分じゃなければ、ボランティアを育成してサポートするしか方法がない。
しかも整備が必要なのは、技能実習生などの受け入れが進んでいる地方自治体なんです。ニーズが高まっているのに、地方にはそもそも若い人が少ないから、ボランティアすら見つかりません。取り組む必要性はわかってるけれど、やりようがない状況なんです。
── 悪循環ですね......。国内ではまだまだコロナ禍が続いていますし、それによって、さらに新たな課題も生まれているのでは?
外国人家族のコロナ禍の影響で言うと、どうにか持ち直した家族と、ひたすら経済状況や生活環境が悪くなっている家族とで、大きな格差が生まれています。サポートを受けようにも、日本語の壁がネックになって、生活を立て直すこともできません。いくら多言語化が進みはじめたとはいえ、安心して生活するにはまだまだ十分でない状況が続いています。
一方で、良い側面もありました。自治体によっては、給付金の受け取りのために外国の方たちが社会福祉協議会に殺到して。そこで地域のニーズが一気に可視化されたんですよね。
── 良くも悪くも、コロナ禍でようやく困っていることが認知されたと。
「国籍やバックグラウンドに関わらず、日本国内で困っている人は助けないといけないよね」という気運は、ソーシャルセクター全体で高まりました。
今まで日本人のみを対象にしてた生活困窮者支援団体の方たちが、外国人の申請の伴走にも入ってくださるようになったり、やさしい日本語でチラシをつくったり、英語でアナウンスをしたりといった動きが広がったんです。そういった取り組みのおかげで、定住可能な在留資格を持っている方たちにも、スムーズに支援が届くようになりはじめています。
── 前向きなニュースですね。
さらに、今まで日本語教育や外国人支援に積極的には取り組んでこなかったNPO団体や、国際NGO団体の視点が、一気に日本国内の在留外国人に向き始めたことも、一つの希望ではあります。担い手不足だったところに、足場がしっかりした団体や若い世代が参画し始めているのはすごく良い傾向だし、新しいフェーズに入ってきたなと実感しています。
── YSCグローバル・スクールでも、コロナ禍で何か変わった部分はありますか?
2013年くらいから、対面での授業が難しい地方の子どもたちに対して、オンライン授業の必要性を感じていて、2015年からはZoomを使い始めていたんですね。でも、当時は全然馴染みがなく、理解が得られなかった。
でもコロナ禍になったことで、年間120人くらいだったオンライン受講者が、2020年度にはちょうど2倍の240人になりました。YSCでは一斉休校期間中に、学びの機会を失ってしまった子たちを無料で受け入れていたことから、オンラインでサポートしてくれるという認識が広がり、受講希望者が一気に増えました。
── オンラインによって初めて機会を得られた方たちもきっといますよね。
おっしゃるとおりです。身近に日本語を学ぶ機会が一切なくて、どうしたらいいのかわからなかった方も全国にたくさんいました。授業では、まず日本語学習の基礎の部分である「やさしい日本語」を習得してもらうことを目標にやっています。
── なるほど。その先は、どうなっていく想定なのでしょうか?
ある程度やさしい日本語がわかれば、地域のフリースクールや無料の学習塾、マタニティサポート、子ども食堂などさまざまな社会資源を共有できるようになると思うんです。やさしい日本語を共通語に、地域と繋がっていくイメージですね。
もちろん、地域資源側は外国人の方も利用することを前提として、必要な対応をおこなっていく必要があります。双方向からの流れで結び付けていくことが大切だと思います。
共生社会への第一歩は、今ある日常を見つめ直すこと
── こうした外国ルーツを持つ方たちの現状を知ったときに、外国ルーツを持つわけではない人ができることって、何だと思いますか?
まずは、共生社会に向けて歩んでいく上で、日常生活の延長でできることや、起こすべき変化がたくさんあるのだと知っていただきたいなと。
たとえば、「マイクロアグレッション」と呼ばれる無意識の偏見や無理解、差別心が含まれる言動をしていないか、振り返ってみることですね。外国の人に対して「箸上手いね」とか「全然日本人に見えるから大丈夫だよ」とか。
── 自分自身もやりかねないし、何気ない会話の中でそういう発言に出くわすシーンも結構あるので、きちんと意識して伝えていかなきゃいけないですね。
わたしも面と向かってはなかなか指摘できません。たとえば「外人」と言っていたら、「ああ、外国人の人ね~」と言い直すみたいな、ちっちゃな抵抗をしています。あとは在日の方々をはじめ、見た目では海外ルーツの方々だとわからないこともあるので、日本に暮らしている人は多様なんだという前提を持つことも大事ですね。
── もしかしたら人に話していないだけという可能性も、大いにあるわけですよね。
そうなんです。アイヌルーツの方や琉球ルーツの方も含めて、実はものすごく多様な方たちが日本に暮らしている。なのに、ごく狭い"日本人"の範囲の中でしか、正しさが捉えられてない場面がまだまだたくさんあるんですよね。
一人ひとりがその前提を持って、視点を広げていくことが、共生社会にはものすごく重要だと思います。
── その視点を持っているか否かで、日常生活での言動も変わっていくだろうなと思いました。
もう一つ気軽に始められる具体的なアクションとしては、「やさしい日本語」を身に付けることですね。先日家族でファミレスに行ったら、ホールスタッフの方が日本語が得意ではない方でした。その方に「うどんの長ネギと、大根おろしを別盛りでください」と注文したら通じなかったんですね。それを、「ネギは別のお皿に入れてください。大根おろしも別のお皿でください」と言い換えたら、オーダーが通ったんです。
そういう、噛み砕いた日本語を多くの人が使えれば、スムーズにコミュニケーションが取れるし、日本語が得意ではない彼らも、安心して生活できると思います。
── なるほど! 難しいことではないし、お互いにとってプラスですもんね。
もちろん、寄付だったりボランティアで参加することも重要です。けれど、日常生活が共生社会向けにアップデートされていかないと、いつまでも心の壁はなくならないんですよね。日常で起きてることを見ていけば、「この場面ではこれができるよな」といった発見が、案外たくさん生まれていくと思います。
時代は次のフェーズへ。次世代により良いバトンを渡すためのインフラ化を
── 2010年の立ち上げから10年以上が経ち、YSC自体の知名度も上がって、当事者の方たちがアクセスしやすくなったのではないでしょうか。
そうですね。2010年の立ち上げ当初は、駅前でのチラシ配りやアパートへのポスティングから始めました。そこから少しずつ周辺の自治体や学校関係者と繋がり、広がっていきました。今は8割の方が、どなたかからの紹介でYSCを知ってくださって、学校や自治体さん、国際交流協会さん経由でYSCに辿り着くケースが多いです。
2015年からは情報発信にもすごく力をいれはじめて、Twitterや「Yahoo!ニュース」などで、課題とセットで団体の知名度を広げることができたのは大きかったと思います。
── YSCグローバル・スクールとしては今後、どこに向かっていくのでしょうか。
わたし自身は正直、事業として大きくなることに関心はないんです。YSCグローバル・スクールは凝縮されたエッセンスのようなものだから、そのノウハウを広げて、社会にバトンを渡していくべきだと思っています。先生たちのお給料のために仕事を生んだり、競争に勝ち残ろうとしたりすると、社会貢献としてはおかしくなっちゃうかなと。
── 本来の目的とずれてしまいますもんね。10年以上この問題と向き合い、第一線を引っ張ってきたと思うのですが、振り返ってみてどうですか?
いやあ、年に何回かは「もう辞めてやる~!」って思いながら、ここまで来ましたね(笑)。でもそのたびに、新しい出会いがあって、目の前の子どもたちと彼らに真摯に向き合う職員がいて。さらに年々自分にしか担えない役割や、社会から求められるものを実感する場面も増えてきて。良くも悪くも「これを今、放り出すわけにはいかないな」というプレッシャーが、自分をここまで来させてる部分もあると思います。
── なるほど。ある意味、使命感みたいなところもあるのかなと感じました。
正直なところ、意図していない部分で、自分の下駄がどんどん高くなってしまっている感覚を抱いています。他にいないから、やらざるを得なかった部分もあったんですよね。
やっぱり、新しい時代にふさわしいアイデアや行動力を持った人に、しかるべきタイミングでバトンを渡すべきだなと。次世代がより安心して受け取れるバトンをつくるのが、これからのわたしの仕事だと考えています。要するに、インフラ化を進めていくということですね。
── 世代交代に向けて、現場を整えていくタイミングなんですね。田中さんの中で今、具体的に何か考えていることはありますか?
今後、共生社会の一員として生活するとはどういうことかを身に付けるために、ダイバーシティ教育を取り入れたり、最低限のNG項目をまとめたマニュアルのようなものを作ったりしてもいいんじゃないかなと。
この問題に関心を持ってくれる方たちが増え始めている今だからこそ、みんなで取り組むことで既成事実をたくさん積み重ねていく。そして、一人ひとりにとって快適な環境をつくれるといいですよね。
YSCグローバルスクール
公式サイト:
https://www.kodomo-nihongo.com/index.html
-
取材・執筆むらやまあき
Twitter: @lune_1113
-
取材・編集山口奈々子
Twitter: @nnk_dendoushi
Instagram: nnk0107
-
撮影飯本貴子
Twitter: @tako_i
Instagram: takoimo