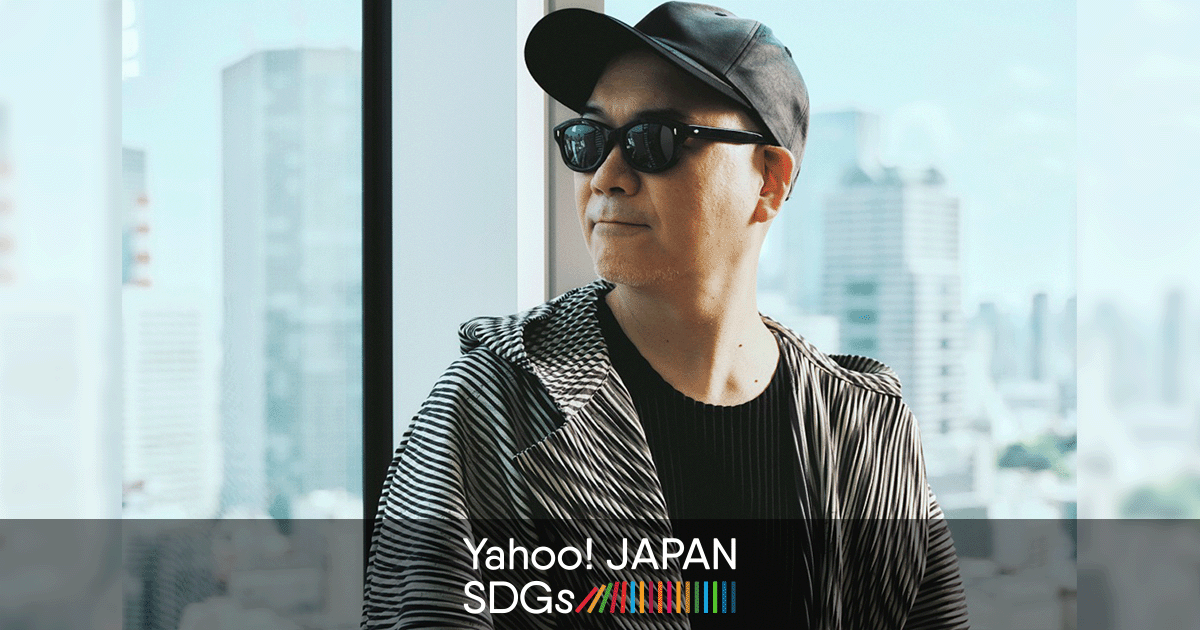「自分も加害者だったんじゃないか」ライムスター・宇多丸に聞く、映画が問い直してくれる問題
私たちにとって映画は、とても身近な芸術でありエンターテインメントです。その映画の本場──ハリウッドやアカデミー賞で知られるアメリカでは近年、人々の多様なあり方や多様な文化を反映していく動きが活発化しています。
たとえば、アカデミー賞を主催する
映画芸術科学アカデミー
は2020年9月に、2024年からの作品賞受賞の新基準に「主要キャストにアジア人やヒスパニック、アフリカ系アメリカ人などを起用すること」や「ストーリーの中心に女性やLGBTQ+といった人たちを置くこと」などを含めた4つの基準を設け、うち2つを満たすことが受賞の条件と発表しました。
人種や民族グループ、女性、LGBTQ+、様々な障がいを抱える人などに向き合い、人権問題を解決していこうと変化していくアメリカ映画界から、私たちが学べることはあるだろうか?
そんな問いを、ヒップホップグループ・RHYMESTER(ライムスター)のメンバーで映画評論家としても活動する宇多丸さんにぶつけてみました。
宇多丸(うたまる)
1969年東京都生まれ。ヒップホップ・グループ「ライムスター」のラッパー、ラジオパーソナリティ。2007年4月に、TBSラジオ『ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル』をスタートさせ、本音で語りつくす映画批評コーナー等が話題を集めて、2009年には第46回ギャラクシー賞「DJパーソナリティ賞」を受賞。2018年4月より、TBSラジオで月曜日から金曜日に生放送されるワイド番組『アフター6ジャンクション』でメーンパーソナリティを務めている。
宇多丸さんは、多くの人権問題が、「なぁなぁにされていること」によって解決に向かっていけないと言います。
宇多丸さんが挙げる、なぁなぁにされていることとはたとえば、貧困を無くそうと訴えながらも誰かに不当な労働条件を押しつけたり、ジェンダーの平等を推進する裏で性的被害を受けた女性が自己責任と責められたり、といったようなこと。
なぁなぁにされている問題が持つ体質は、被害者でも加害者でもない立場の人たちが「自分には関係ないこと」の態度で蓋をしてしまいがちなことであると宇多丸さんは言います。
しかし、本当のところは誰でも無関係ではなく、むしろ誰もが当事者として自分自身を問い直していくことが必要だと、私たちに語りかけるのです。
なぁなぁな問題を#MeTooが炙り出した
── 映画というカルチャーを通じて、人権問題を捉え直すことができるのではないかと思っています。そもそも、近年のアメリカ映画が観客の多様な立場や文化を反映していく動きに変わってきているのは、どういったことが背景にあるのでしょうか?
まず、アメリカの映画界が、一朝一夕にいろんな人権問題に向き合っていこうとなっていったわけではもちろんなくて、長年いろんな人々が要所要所で戦ってきた、その積み重ねの結果でもある、というのは理解しておかなければなりません。
ただ、そういった前提がある上でですが、近年の加速度的な動きにつながったのはやっぱり、2017年末の#MeToo運動の本格化じゃないかと。
── そもそも#MeToo運動は、アメリカの映画界が発端ですよね。
はい。セクシャルハラスメントや性的暴行による被害というのは、業界内に限らず、僕ら一般人も薄々知っていたことではありますよね。必要悪とまでは割り切っていなくても、「まぁ、現実はそういうもんみたいだよね」みたいに見過ごされてきた。つまり、なぁなぁにされてきた問題でした。
それが明るみに出て、調査報道で裏付けもされ、動かぬ証拠となった。それが#MeTooです。僕は、#MeToo以降の世の中の違いは、いろんなことをなぁなぁにしない風潮に変わってきたことだと思うんですよ。
── なぁなぁにしない風潮、とは?
今までは、「まぁ、正しいのはこっちだけど、世の中はそういうもので」みたいに片付けられてきたことを、これからはもう、安易によしとしないようにしようよ、っていうような流れのことです。「なんでなぁなぁにしてたんだよ? 目の前に被害者がいるのに?」という意識の変革が広く行われたのが、#MeToo以降の一番の変化であるような気がします。
つまり、#MeTooをきっかけに、他の人権問題も放置されたままでいいのか?という大きな問いにつながっていったんじゃないか、というふうに僕自身は感じています。
── #MeTooが「なぁなぁにしない」推進力となった、他の人権問題はどういったものがあるのですか?
女性に対する差別のみならず、たとえば同性愛やトランスジェンダーの方々など、とかく権利や尊厳を踏みにじられやすい、あらゆる弱者やマイノリティに対する認識を改めなければ、というような流れは、相対的にであれ確実に強まりましたよね。
あとはたとえば、言うまでもなくアフリカ系アメリカ人の人権問題は長年ずっと訴え続けられてきたことなわけですが、やはり#MeToo以降の「なんであれ、不正をなぁなぁにしない」ムードの強まりが、特にこのタイミングではいわゆるBlack Lives Matter運動の強い後押しにもなったんじゃないか、という感じが僕にはします。
とにかく2017年の以前と以後では、表現する側だけでなく、それを受ける側のテンションもけっこう、違う気がするんですよね。
── 日々、ラジオを通じてリスナーと対話する宇多丸さんとしては、作品を見る人の目も変えられたように感じる、と。
たとえば、昔からフェミニズム的な文脈では性差別だと批判されていたような映画が、今や一般の観客から見ても自然に、「これはさすがに昔の価値観だよね」と感じられるようになっていたりとか。自分自身もそう感じることが増えましたし、受け手側のモードの変化もすごく大きかった気がするんですよね。
僕自身のことで言えば、自分にはそこまで差別的な意識はないつもりでいたけれど、かつての発言とか、それこそ歌詞とかもですけど、見返してみるとギョッとする、みたいなこともよくあります。なので、「いやいや、自分はわかっているみたいな、その意識、その発言が一番危ないんだって」と自分を戒めたりしてますね。
誰でも人権問題の当事者
── #MeToo以降の作品で、人権問題を考えるのに適した作品があれば教えてください。
ここまでの話の文脈から紹介したいのは、『プロミシング・ヤング・ウーマン』。それこそ今まで社会の中でなぁなぁにされてきて、なんならありでしょ、くらいの認識でまかり通っていた言動を、「いやいや、これは紛れもない性暴力で、はっきり被害者がいるんだ」と、性別問わずに問いかけてくる作品です。
僕自身もこの作品を観て、自分もまた無意識に加害者側の論理に寄っていたことがあるんじゃないか、と考えさせられました。たとえば僕はクラブで遊んできたから、この映画の中で描かれているような、前後不覚でそのまま男性に連れられて一緒に消えていく女性の姿というのは、ある種よく見る光景だったわけです。でもそのときは、それが望まぬ性的行為、すなわち性暴力につながる可能性についてしっかり考えていなかったし、それを黙認することは加担してるも同然、ということにも、気づいていなかった。
プロミシング・ヤング・ウーマン - Yahoo!映画
明るい未来が約束されていると思われていたものの、理解しがたい事件によってその道を絶たれてしまったキャシー(キャリー・マリガン)。以来、平凡な生活を送っているように思えた彼女だったが......

── 同じ女性である私も、被害者が自分の身内や友達じゃなかったら、可哀想だと思う反面、自分には関係ないことと他人事の態度を決め込んでしまうかもしれません。
まさにそこも射程圏内に入れている作品です。女性であっても、「自業自得」「彼女にも隙があった」などと切り捨ててしまうことは、ぜんぜん考えられますよね。また、男性中心的な社会では、そうした性的な乱暴さが「若気の至り、やんちゃ」で片付けられるような現実がある。
ポイントだと思うのは、この作品、性暴力被害に直接あった本人ではない、当事者じゃない人が復讐していくストーリーだということ。それはつまり、「わかっていてなにもしなかったら、同罪ではないのか?」というメッセージになっていると僕は思いました。
劇中、男性から女性へのきつい暴力シーンがあるのでやや観覧注意ではありますが、オススメの一作です。
── なぁなぁにされている問題に対して、「自分は被害者でも加害者でもない」とある種、傍観者でいる人たちにも自分ごとに思える作品なんですね。
当人に悪気はまったくなかったとしても、「そんなつもりはなかったのに」抑圧的になったり、暴力的になったり、差別的になったりしてしまう可能性が、人には誰でもある。だからこそ、「それはどうしてか?」「ではどうしてゆけばいいのか?」と問い続けてゆくことが大切なんじゃないかと。
大きな話で言えば、なぁなぁにされている問題に他人事の姿勢を決め込むことは、今のロシアのプーチン政権の有り様、みたいなことまでつながると思うんです。不正な行いをして悪びれもしないとか、弱い立場の人たちを踏みつけにするとか、そういうことが長年いくつも重なって、今のプーチン政権があるわけじゃないですか。
なので、「プーチン政権はひどい」で終わらせるのではなく、では自分たちの国やコミュニティーにはああいった体質がないと言えるのか、と問い直してみることが大事だと思います。
問い直されず、消費されがちなエンタメ
── 映画は、一見すると自分には関係なさそうに思える問題も、自分ごととして捉えたり、自分自身を問い直していける最適なツールでしょうか?
まず僕たちは、自分の知らないところで起きている社会の事象を、ニュースや本などを通じて知ることができるわけです。でも、無味乾燥な「情報」だけだと、「わかった気」になって終わってしまうことが、多々あるんですよね。
たとえばニュースで、「世界の難民は1億人を超えていて、キャンプ生活を余儀なくされている人たちがたくさんいる」という情報を目にしたとしても、それだけでは正直、さしあたって他人事(ひとごと)としてしか捉えられないというのも、ある種無理からぬことかなとも思うんです。
── 情報を追うだけでは当事者意識は芽生えにくい、と。
でも、それが映画などの「作品」になると、それがフィクションであれドキュメンタリーであれ、言わば「物語化」のプロセスを経ることで、途端に自分ごとに思えてきたりする。それは、物語というものの巨大な効果ですよね。
なんなら、正しい人だけでなく、正しくない人の立場にさえ、ある種の感情移入ができてしまう。現実の社会にいれば排除したい思いに駆られるような立場の人にさえ、寄り添えてしまう。そういう効果があるということですよね。
だから、多くの物語に触れている人は、それだけ多様な、豊かな視点を持てているはずなんです、原理的には。
ただ同時に、我々はとかく物語を、その場限りのエンタメ、快楽として消費してしまいがちでもあって......。
── 映画がエンタメとして消費されている、とは?
よく出す話題ですけど、「『ファインディング・ニモ』を観た人が、カクレクマノミを飼おうとするって、どういうことなんだよ!」って(笑)。映画を観た人たちがカクレクマノミを欲しがって、ペットとして人気になり、乱獲につながった、という現実があるわけですよ。
── 海の生物を人間(ダイバー)の都合で、家族を引き裂いてペットにするお話なのに、その結果が乱獲というのは残念ですね。
いかに我々が「物語」をその場限りの楽しみとして消費してしまいがちか、端的に示すエピソードだと思います。
ファインディング・ニモ - Yahoo!映画
オーストラリア、グレートバリアリーフ。広大な海の中でカクレクマノミの400個の卵が孵化しようとしていた。しかし、無事に生まれたのは母親の命と引き換えに助かったたった1つだけ......

── 宇多丸さんの言う「エンタメとして消費される」とは、自分ごととして問い直しがされていない状況のことなんですね。
たとえば、アメリカ映画におけるアフリカ系アメリカ人の描かれ方も、何十年も問い直しがされてきて、今の形があるわけです。
たとえば、1960年代に公開された『夜の大捜査線』という映画は、非常に差別意識が強い地域に優秀なアフリカ系アメリカ人の刑事がやってきて、白人の刑事とバディになっていく、という当時としては間違いなく進歩的な作品ですけど、その後の観点で見ると、シドニー・ポワチエ演じるそのアフリカ系アメリカ人の刑事が、あまりにも優等生的に設定されているのが、逆に気になってくる。「ここまでできた人じゃないと認められないのか」と思うと、これもまた偏っているような感じもしてくるわけです。
時代は飛んで、たとえば『ドゥ・ザ・ライト・シング』。登場するアフリカ系アメリカ人たちは、決して正しいことだけ言ったりやったりしているわけじゃない。それでもなんとか彼らなりの「ライト・シング」を成そうとする、より生き生きした人物像がそこにはあるわけです。
そういうふうに、「アフリカ系アメリカ人をこういう描き方だけで済ませていいのだろうか」という問い直しが長年にわたってされてきている。そういう積み重ねが、それこそ『ブラックパンサー』のような、超大作エンターテイメントにして硬派な社会派メッセージも多分に含む作品が生まれる現状に、つながってくるんですよね。
夜の大捜査線 - Yahoo!映画
南部で発生した殺人事件の容疑者として、駅で列車を待っていた黒人青年ヴァージルの身柄が拘束された。しかし警察の取り調べによって、ヴァージルは殺人課の刑事であることが判明する......

ドゥ・ザ・ライト・シング - Yahoo!映画
スパイク・リー脚本・監督・主演の第4作。ブルックリンの黒人街ベッドフォード・スタイヴェサント。街の小さなラジオ局"ウィ・ラブ・ラジオ"をひとりで切り盛りするミスター・セニョール・ラブ・ダンディのDJが......
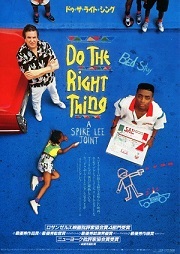
── 最近の映画界の話で言えば、宇多丸さんもラジオ番組『アフター6ジャンクション』の中でも触れていましたが、ウィル・スミスがアカデミー賞授賞式でクリス・ロックを平手打ちした件が日本でも話題になりました。
すごくショックな出来事でした。日本国内では、ウィル・スミスの行為や「家族を守る」というマッチョなスタンスを安易に支持するような論調も当初は多くて、それにもまた落ち込んでしまいました。
すでにウィル・スミス自身がはっきり謝罪、反省していることですが、なんであれ言論に対して直接暴力に訴えることなど言語道断であるというのは、本来議論するまでもない文明社会の大前提です。アカデミー賞授賞式という多くの人々がかかわる晴れの場であったこと、加えて戦争という究極の暴力が進行中という痛ましい現状などを考えあわせれば、絶対にするべきでない振る舞いだったのは言うまでもないことだと思います。
「近頃、せせこましくてつまらない」は嘘
── とは言え、#MeTooをはじめ急速にいろんなことが問い直されている世の中で、たとえばテレビバラエティしかりですが、「気をつけないといけないことが多くて、窮屈だ、退屈だ」みたいな声が少なくないように思います。よりよく変化していくために、私たちは変化とどのように向き合えばいいでしょうか。
たしかに近年はあまりにも価値観の変化が急激で、どう向き合えばいいのか悩んでしまうのもわかります。僕自身も、自分のわかってなさみたいなものに向き合うのは辛いし、やっぱりあまり気持ちいいものじゃない。
だけど、それを「窮屈」としか受け止めないのだとしたら、それはやっぱりつまるところ、自分の目先の都合や保身のことしか考えない、思考停止的なスタンスと言わざるをえないと思うんですよね。だって、現にこれまでのやり方で苦しんでいる人たちがいるんですよ、って話なのに。人を踏みつけにしてまでして守んなきゃいけないようなものなんですかそれは?と問いたいですよ。
それに、社会のなかで不当に苦しんでいる人たちを放置していると、結局それは、いずれ他の多くの人たちの不利益にも跳ね返ってくるだろう、と僕は考えていますけど。
── というと?
身近な話からすれば、たとえばいま、物流危機と言われていますよね。どうして物流危機かというと、運転手のなり手がいない、と。じゃあそもそもなぜ、運転手のなり手がいないのか? それは、ずっと賃金が安く、労働条件も悪いままにされているから。つまり、これまで末端の労働者に、一方的に負のしわ寄せを押しつけてきたツケが、ここに来て社会全体に跳ね返ってきてる、ということでしょう。
そんなふうに、弱者から搾取してようやく回るような仕組みの社会は、必然すぐ行き詰まって、せいぜい「弱者」の層を拡げることで延命をはかるのが精いっぱい、みたいなことになるしかない。そんな国は絶対に衰えてくしかないですよね。まったく「持続可能」じゃない!
なのにそのなかで、なんで自分らだけは大丈夫、と思っていられるのか。僕にはそっちのほうがよっぽど不思議です。
── なるほど。もしかしたら人権問題だけでなく、あらゆる社会問題も問い直さず、なぁなぁなままにしてきたことが要因としてあるかもしれませんね。
逆に、しっかりと思考を先に進めていったほうが、たとえば映画でもそうですが、窮屈どころか、「いやいや、むしろそれでおもしろくなっているから!」と言いたいですね。
── 人権問題をはじめ、いろんなことが問い直されてきた映画がおもしろくなっている?
たとえば『ブックスマート』。学園モノの映画なんですけど、ひと昔の同ジャンルのように、体型やセクシャリティに関することでいじめてくるような登場人物は、ひとりもいないんです。女性の主人公がふたりいて、ひとりはレズビアン、ひとりはふくよかな体型ですが、そのことを「イジってくる」ようなヤツは出てこない。そんなレベルの低いバカは、すでにいないことになっている世界なんです。
もちろん学園内ヒエラルキーみたいなものもあるけど、それはあくまで社交性の高い低いなどに基づくものであって、ただ意地悪なだけの「悪役」を一方的に設定することもしていない。そして、そうした多様性に対する豊かなスタンスが、未だかつてない風通しのよさ、後味のよさにつながっている。それでいてやっていることはひたすら、エゲツなさもアップデートされたしょーもない下ネタだったりするんですよ(笑)。とにかく最新にして、最高の青春映画です!
ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー - Yahoo!映画
親友同士で成績優秀な女子高生エイミー(ケイトリン・デヴァー)とモリー(ビーニー・フェルドスタイン)は、卒業式前日、遊び放題だったクラスメートがレベルの高い進路を決めていることを知って衝撃を受ける......

── #MeToo以降の機運を反映した作品が無類におもしろいというのは、問い直していくこと自体を肯定していますね。
なので、「いろいろ今はうるさくて、せせこましくてかなわない」と思っている人たちには、そうじゃないんだと。新しい視点を得れば、そのぶんよりおもしろいエンタメが生まれうるし、現に生まれまくっているんだよ、ということを伝えたいですね。
── 映画は、物語化されているだけでなく、おなじ時間を使って一緒に見ることもできるからこそ、その問い直しの入り口として有効に感じます。
そうですね。問い直す行為は何もひとりでやらなくてもいい。家族やパートナーと話し合うのでもいいし、むしろそれが重要なんじゃないかと思います。一緒になんか見て議論でもなんでもすればいいし、それで最初はケンカになっちゃうかもしれないけれど、それも言わば"成長痛"ですよ。
「耳が痛いな」とか「ちょっと3日考えさせてください」みたいなことになったとしても、お互い内心納得してないのにただ我慢して一緒にいるだけ、とかよりはずっといいじゃないですか。それが結局は、他者同士である我々が互いに楽しく生きてゆくための、唯一の方法なんだと思います。
(取材日:2022年5月25日)
-
取材・文小山内彩希
Twitter: @mk__1008
取材・編集くいしん
Facebook: takuya.ohkawa.9 Web: https://quishin.com/
Twitter: @Quishin
編集吉田恵理
note: eririri Instagram: eririri.y
Twitter: @eri_riri
撮影藤原慶
Instagram: fujiwara_kei Web: https://www.fujiwarakei.com/
Twitter: @ph_fujiwarakei