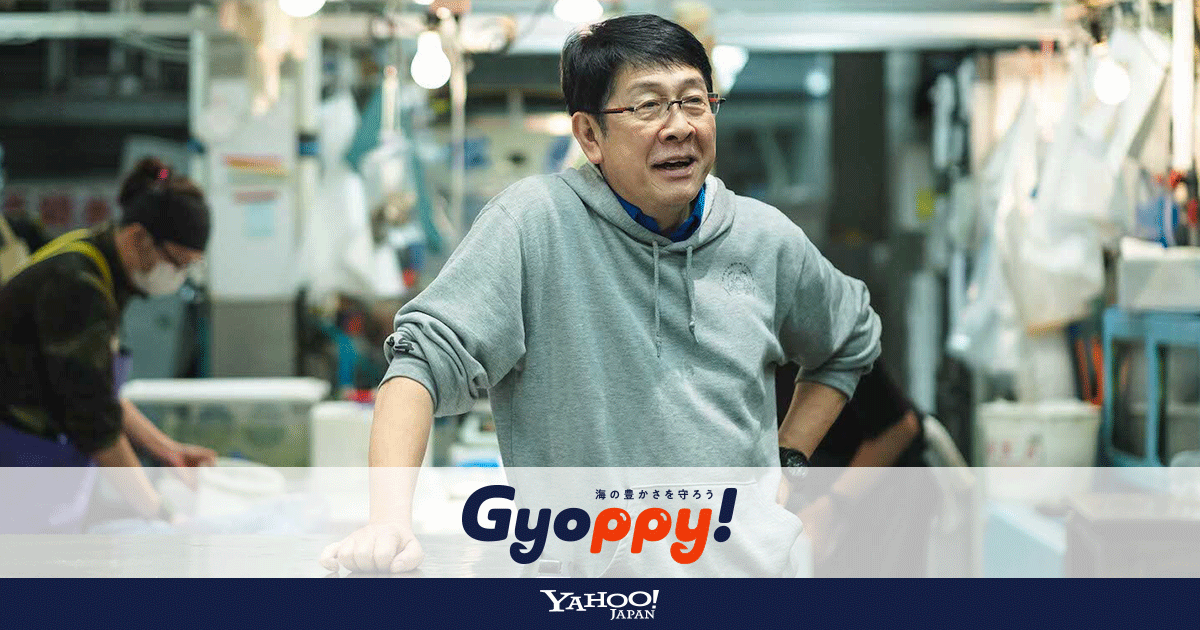「世の中は政治が動かしてる」マグロの絶滅を防ぐため、消費者にできることはない!?
回転ずしって、安くておいしいですよね。マグロの赤身もトロも炙りも100円~200円くらいで食べられるなんて、まさに庶民の味方。
でも、ちょっと待ってください。
Gyoppy!でも何度か取り上げていますが、いま本マグロ(クロマグロ)は個体数の減少が心配されています。2014年に絶滅危惧種に指定され、国際的に漁獲量の規制が進んでいるんです。
なのに100円で食べられる......? ありがたい反面、よく考えるとナゾですね。
そこでお話を聞きに行ったのが、豊洲市場のマグロ仲買人・生田よしかつさん。
生田さんの活動は多岐にわたり、フォロワー9万人のTwitterや登録者数3万人のYouTubeチャンネルでは、政治や魚について発信活動を行っています。
そんな「マグロのプロ」に回転ずしのマグロのナゾをぶつけてみたところ、
「なんで100円で食べられるんだろうね、俺もわかんないよ(笑)。まあ、すし屋や流通業の努力ってことだよね」
なるほど、営業努力......確かにそれに尽きるのかもしれません。ではせめて、マグロをおいしく食べ続けられる未来のために消費者に何ができるのか聞いておかねば。
ということで取材を続けていくと、驚きの答えが返ってきました。
「消費者にできることって、何もないんだよね」
できることは何もない。もはや「海の豊かさを守るために発信する」というGyoppy!のコンセプトにも関わる話になってきました。
しかし、「できることはない」と言いつつ、約20年欠かさず一般消費者への発信も続けておられる生田さん。
やがて取材は魚の話を飛び越え、「漁業を変えるには政治が大切」というテーマにまで行き着きます。テーマとして一見結びつきづらい、「海」と「政治」。
現場を熟知し、社会への影響力も持っている生田さんが辿り着いた現実とは......?
「魚が減っているので値上げします」とはいかない現実
── 僕たちはふだん、「マグロって絶滅危惧種のはずだよな......」と思いながら、回転ずしで100円のマグロを食べています。まず、これについてはどう思われますか?
なんか日本人はそういうところが変だよね。だってウナギにしても、「ウナギがなくなりそう」って言われると「早く食べなきゃ」ってなる。ふつうに考えれば、なくなりそうなんだから、ちょっとやめといたほうがいいじゃない?
── やっぱり消費者の意識の問題が大きいと?
そもそも「食べ物が当たり前にあるんだ」という前提があるから仕方ないんだけど......。でも日本は食料自給率の低い輸入大国だからさ、魚だけに限らず、すべての港と空港が止まったら生きていけなくなる。だから本来、もっと持続可能性のことを考えるべきだよね。
── 確かに......。今は夜中だってコンビニに行けばいくらでも食べ物がありますし、どうしても食べ物は「あって当然」という意識ですね。
特にこういう魚の商売してると、食べ物のありがたみを親とか祖父母からずっと教育される。だって「魚を食べる」ってさ、よく考えるとすごいんだよ。
── 魚がすごい?
勝手に生まれて勝手にエサを探して勝手に大きくなって、それでおいしくなって、獲られて我々の前にやってくる。獲る以外なんの手間もかかってない。これってすごくない!? 他の食べ物で、人間が何もしないで食べられるものってほとんどないんだよ。
── 言われてみれば! コントロールされていない野生のものを食べられる食材って、他になかなか思いつかないですね。
うん。ましてや日本なんて天然のいけすのような豊かな海を持ってるから、ほっとけば魚は増えるわけだよ。これをうまいことコントロールして海外に売れば、ぼろ儲けできる。でも今はできてないんだよね。
── 今はコントロールできていない?
海は豊かなはずなんだけど、人間の手によって獲りつくしてる状態に近づいてるわけ。魚は昔から何も変わってないのに、人間だけが勝手に進化していくからね。宇宙から捕捉して居場所がバレちゃったら魚はたまったもんじゃないよね(笑)。
── なるほど、テクノロジーだけが発展している。それなら、かなり規制をかけていかないと魚が減ってしまうのは当然ですよね......。
これって人間の傲慢、うぬぼれでさ。我々のいる豊洲市場だって大自然から恵んでもらってこれだけの商売ができてるのに。回転ずしの会社だって魚で利益を出して、上場までしてるんだからすごいじゃない。だけど消費者が、便利さや豊かさに飼い慣らされちゃってるのが問題だよね。
── 結局、昔よりも生活が豊かになってしまっているから、豊かな食生活にも慣れている、ということですよね。でも、回転ずしに行って楽しんでいるときも、「安くすることが乱獲につながるのなら、少し値上げしても食べるのになあ」とか思うことはあります。
とは言うけど、みんながみんな、意識の高い人じゃないからね。そこは競争だから。100円のものを110円に上げれば極端に売上は落ちるよ。ビジネスってそういうもの。
── なるほど......。じゃあ世の中全体の物価が上がらない限りは、安くなる一方ですね。
難しいよね。商売してる人にも生活があって、利益を出さなきゃいけない。じゃあその人たちとお客さんに対して、「あなたがた意識高くなってください」「天然資源が減ってるので値段高くなっても我慢してください」と言っても、なかなかそうはいかないんだよ。わかってくれる人が2割いればいいほうだと思う。
── 魚以外の食べ物もあふれてるから、「魚が高くなるんなら他のもの食べるからいいよ」ってなりますよね。
「将来のことも考えたいけれども、いま目の前のことに流されてるのが現実です」っていう人のほうが世の中には多いからね。発信とか啓蒙の難しさって、そこにあると思う。
消費者にとって大事なのは、資源管理よりも「おいしいかどうか」「安いかどうか」
── お話をうかがっていると、じつは資源管理ってマグロや魚だけの問題ではないんだな、と思えてきました。
そうなんだよね。自分でも結論が出てないんだけど、豊かになりすぎちゃった結果だと思うんだよ。戦後、ほんとうに食えない時代を生きたうちの親の世代は、腹いっぱい食べる幸せを手に入れたいと思って必死に生きてきたわけ。それが今は豊かになって、大事なことを忘れちゃった。日本で今起きてる問題はそういうことに根ざしてると思う。
── 僕も朝ドラや昭和を描いたドラマを見て、いろいろなありがたみを忘れちゃいけないなと思うことがあります。
ありがたみは大事だよね。たとえば夕食のときに目の前にある一匹の魚だって、遠くの海で生まれてエサを食べて育って、漁師が沖まで行って網で獲ってきたもの。それを刺身で安く食べられるってすごいことなんだよね。今はいろんなものを新鮮なまま食べられるし。
── 安いのはありがたいんですが、「安すぎでは?」と思ってしまうときは正直ありますね。でも、マグロがセリで数億円になったみたいなニュースとか見てると、安く買ってるようには見えないんですが......。
あれは別格で、話題づくりだよね(笑)。「史上最高値をとりました!」と言えばニュースで流れる。そういうビジネスのやりかただよね。これに限らず、まあビジネスだから仕方ない部分もあるんだけど、本当はちゃんと「食」と「経営」って部分を分けて考えないといけない。
── それが一体になっちゃってるからおかしいと?
たとえば、「年間を通しておいしいサバを提供します」とかね。本来そんなことできないんだよ。すし屋は季節に応じていろんなもの出すのが正しい形なの。
── なるほど。今やコンビニなんかでも一年中同じ食品があるので、それがふつうだと思ってしまいがちですね。
俺も商売人だけど、商売人はもうけるためならウソつくからね(笑)。商売は性善説じゃなくて性悪説だから。昔言われたことあるんだけど、商売と詐欺の違いって、ホントに紙一重で、突き詰めてしまうと「相手が喜んだか怒ったか」だけなんだよね。たとえばただの紙でも、好きな芸能人のサインが書いてあれば1万円でも買う人は買うでしょう? ズルく見えるけど、相手が喜んでればこれは詐欺じゃなくてれっきとした商売になる。
── では資源管理の話も、今はすべてが売る側の都合で回ってしまっている、ということでしょうか。
売る側もだし、消費者もそう。だって消費者にとって大事なのは、「おいしいかまずいか」「高いか安いか」、それしかないわけだよ。おいしさと価格が見合っているかどうか。そこから、「でも本マグロって絶滅危惧種なんでしょ」なんて想像する人は世の中にあんまりいない。
── 確かに......。いちいち考えないですね。
前にスーパーマーケットの経営者たちに向けて講演したとき、「持続可能なスタイルの漁業で獲れてます」ってことを表す「MSC認証マーク」のことを誰も知らなかったもんね。そんなものなんだよ。経営者とか現場の人間が知らないんだから、その先の消費者が知るわけない。
── 経営者も商売のプロであって、資源問題のプロじゃないですもんね。
商売人って、自分たちの利益を安定させてガッポガッポお金が入ってくる、それが目標でしょ。やがてそれにも飽きると「じゃあちょっとマグロの資源の心配でもしようか」ってなるわけ(笑)。これって極論に見えるかもしれないけど、でも正直な本音じゃない? かっこいいこと言っても、メシ食えなかったら終わりだからね。
きれいごとは20年言ってきた、でも何も変わらない。魚の資源管理は、発信よりも政治の問題
── うーん。考えれば考えるほど、資源のこと、未来のことを訴える発信活動の難しさを痛感します。
俺もはじめは一生懸命やってたよ、「みなさん意識高くなりましょう」「これ絶滅危惧種だから食べちゃダメですよ」と。でも、だーれもやんない。
── そういった活動は何年くらい前からやられてたんですか?
こんなにSDGsとか言われるようになる前から、もう20年近くやってるね。18歳で河岸に来て、毎日すげえ量の魚が揚がるから「これなくなんねえのかな」と思ってたし、イワシなんか値段がつかなくて捨てたこともあるからね。そして27、28歳のとき、当時扱ってたオーストラリアのマグロに、来年から漁獲量に枠がつくられるんだと知って、そこから興味を持った。
── その後はどういった活動を?
青臭く、いろんな人にこのことを知らせようと、NPOも一般社団法人もつくったし、講演もやったり......。でも、確かに危機感を持つ人たちは増えてきたけど、こんだけやったって状況は変わってねえもん。同業の連中も、資源管理に興味ある人いないぜ?「確かに10年後20年後のことは大切かもしれないけど、でも俺のところ今年廃業になっちゃうかもしれないもん」って話だから。しょうがない。
── なるほど......。すると、どうしたらいいんでしょう。
俺はね、政治だと思う。これは消費者にデータを知らしめてどうのこうのするより、政治マターだよ。ここ数年はそう思ってやってる。
── 政治、ですか? 確かに生田さんは、SNSやYouTubeでも政治的な発信をされていますが......正直、漁業と関わるイメージが薄いです。
二宮金次郎が読んでる中国の古典『大学』のなかに「政治の上中下」の話があって、それによると、一番いい政治は「問題が起きる前に、一般庶民が何も気づかないうちに問題が解決してる」っていう政治なんだよね。魚の資源管理はすでに問題が起きちゃってどんどん悪いほうに行ってるんだけど、今から対策をすればまだ「中くらいの政治」にはなれる。
── 発信活動だけではなく、今度は政治の側に働きかけていくと?
あんまり見えづらいけど、やっぱり世の中って政治が動かしてるんだよね。
── 魚に限らず、日本人は「政治が生活に直結してる」という意識は薄いですよね。政治のことをあんまり考えない人が多い印象です。
しかも「政治家っていうのは悪者で、いつもてめえの私腹をこやすことしか考えてない」って虚像がメディアによってつくられてる(笑)。でも実際に永田町で政治家に会うと、けっこう地道に一生懸命やってる人も多いんだよ。それは政治家と交流するようになって学んだこと。
で、そう考えると、やっぱり俺たちは「資源管理が大事です」みたいなきれいごと言うのが目的じゃなくて、世の中変えて魚を守るのが目的なわけじゃん。それを達成するために、政治の側からの規制改革ってのがものすごい大事なわけ。
── 規制改革。漁獲量の制限とか、ですか?
そうそう。規制と言うとみんな「規制緩和」って思いがちだけど、水産の場合は「規制強化」が大事なんだ。だから最近は緩和じゃなくてちゃんと「改革」って言い方になってきた。それだけでもだいぶ進歩してるんだよ。
── 規制を強めなきゃいけないのを、政治の側があんまり分かってなかったと。
大衆に発信してわかってもらう労力を考えれば、政治にコミットしたほうが早いからね。
── なるほど、生田さんのYouTubeチャンネルが魚も政治もごちゃまぜな理由がわかった気がします。
あれは「ただの魚屋のおっちゃん」が政治を語ってるところに価値があるんだよね(笑)。すると政治を身近に思って興味を持ってくれる人が出てくるから。それで水産資源の問題にまで辿り着いてくれたらラッキーなんだけど......まあ、大衆は変わらないよ。大衆が変わったら逆にこわいよ。
── こわい、ですか?
ポピュリズムで大衆が扇動されちゃったら、こわいからね。みんながみんな「水産資源を守ろう」とか言い出したら、絶対どこかに過激派が出てくる。魚食うやつは殺してやる、みたいな。
── ああ、なるほど。発信が行きすぎるとそういう事態もありえますね......。
だからそもそも政治家がちゃんとやってれば、こんな発信の運動とかしなくていいんです、すべて解決。俺は政治家にはならないで一生魚屋でいるけどね、うまいもん食えるから(笑)。
人は、変われない。人の欲をコントロールできるのは政治だけ
── では最後に、マグロを食べ続ける未来のために一般消費者にできることを教えてください。
もちろん水産資源のことを勉強するのは大事だし、だから発信活動もしてるんだけど......実際のところ、消費者にできることってないんだよね(笑)。
── ない......んですか!?
だって現実的に、単にマグロを食べるのをやめればいいかって言ったらそれも違うよね。お店にいっぱい売ってるんだから。急にみんながやめたら、それこそ膨大な無駄をつくるだけ。それこそ大問題だよ。それに自然や生命への冒涜だと思う。
まあ、強いて消費者にできることを言うとすれば、今、ここにあるものを「感謝して」いただくって気持ちを持ってほしいね。
それよりも、要するに消費者も「海ってなんだろう? 魚ってなんだろう? 僕らの食って一体なんなんだろう?」と、哲学みたいだけど、そこを突き詰めて考えないといけない。
「お金儲けをやめましょう」とも言えないしね。単にお金儲けが間違ってるわけじゃないんだよ。だって絶滅危惧種のマグロが100円で売ってたとしても、それで喜ぶ消費者がいれば、それは全否定はできないわけだよね。
── 難しいですね......。
きれいな結論を出せない問題なんだよね。人って、変えられないんだよ。俺は豊洲市場への移転問題とかを経てよーくわかった、一番恐れるのは変化なんだ。「豊洲に移転したくない」って言ってた人も、突き詰めれば「だって築地で今できてるじゃん、なんで変える必要あるの」と。変化するのがなんとなく嫌なんだよね。ルーティンをこなすのって人間ラクなんだ。
── 確かに、「変わりたくない」という無意識を持つ人々に「変わろうぜ」と言っても......。
基本的に、絶対無理だよね。
── となると、変な言い方ですが、「できることのなさを認識する」ことが僕らにできる最低限の「できること」なのかなと思いました。「人は変われない」という現実をちゃんと認識することから始める、というか。
そうだよね。みんな生活は変えたくないし、みんな欲がある。だけどその欲をコントロールできる唯一の方法がある......それが政治だよ。人の欲をコントロールできるのは規制だけで、規制をかけられるのは政治だけ。
── なるほど、そういう思いがあって政治的なアプローチをされているんですね。ではそこも含めて、今後は何をしていかれますか?
まあ、なんだかんだ言っても、一般に対しての啓蒙は諦めちゃいけないからね。政治って、世間からの後押しがないと進まないのも事実だから。いまは政治家の独裁的なことって一番嫌われるし。そういう声をつくっていく手伝いくらいはしたいなと思ってる。YouTubeでも政治のことをやりつつ、ときどき水産の話もちゃんと入れる。水産だけだと再生数上がらないから(笑)。
── そうなんですか?
単に魚食って「うまいねー」って話ならみんな観るんだけど、「日本の海から魚が減っています」って言うと全然再生数は増えない。だってみんな楽しい話が聞きたくてYouTube来るわけだからね。暗い話なんか聞きたくない。楽しい話の中に混ぜて、簡単に、さりげなく教えるのが大事。
── 戦略がすごい......!
水産資源のこと言っても、豊洲でも誰もついてこないからね(苦笑)。「飯のタネがなくなろうとしてるんだぞ」と言っても、「そうかもしれないけど仕事だけで精一杯」ってなる。そしてそれを非難はできないからね。きれいごとじゃない、これがリアルな現実。
だからそういう現場の声も踏まえながら、これからも政治のほうに働きかけていきたい。政治的な活動は人に批判されることも多いけど、状況を本気で変えるためにもっとやっていきたいね。
おわりに
20年以上にわたり、水産資源の問題を発信してきながらも、現在は政治家への働きかけなどの活動にも軸足を置かれている生田さん。
その背景として、「地道に発信してきたけど状況が変わらなかった」という厳しい実感を持たれているのを感じました。
僕たち日本人は、「政治」と聞くと少し身構えてしまう感覚がある人も多いと思います。
でも本当は、Gyoppy!がふだん伝えているような海や漁業の話だって、政治の問題と密接に関わっている。
豊かな海。いい政治。それを自分たちでつくるんだ、という意識。「きれいごと」だけでは何も変わらなくても、「きれいごと」を言わないと何も始まらないこともまた事実です。
自分のために、そして社会のために各々がどう生きていくのか、「海」を通してこれからも考えていきたいと思います。
-
文大島一貴
Twitter: @aike888g
Facebook: bigislankzk
-
撮影安東佳介
Twitter: @keisuke_andoh
Instagram: @keisuke_andoh
Facebook: kesuke.andoh.5
-
編集くいしん
Twitter: @Quishin
Facebook: takuya.ohkawa.9
Web: https://quishin.com/