収入源のナマコ漁を禁じたら、貝も森も減った。資源管理の難しさをフィジーで知る

暮らしを支える豊饒の海
フィジーの海にはふたつの顔があります。
ひとつは、青い海です。フィジー本島の西側海域にはサンゴ礁が広がっており、海外からの観光客がリゾート目的に訪れます。
フィジー、その美しき海 ~ソソ村の青い海~
もうひとつは、茶色の海です。東側海域にはサンゴ礁だけではなく、マングローブ、干潟、藻場など多様なエコシステムが広がっています。数多くの水生生物が生息しており、漁業が盛んに行われています。
Welcome to KUMI Village!

今回皆さんをご案内するのは、フィジー本島の東側にあるクミ村。首都スバから車で90分ほどの距離にある人口280名ほどの村です。
クミ村を訪問するのは今回で4回目ですので、知った顔も数多くあります。いつものように部外者を受け入れる儀式であるセブセブをしてから入村します。
人々の暮らし

クミ村の人々は、農作物や漁獲物を販売することで現金収入を得ています。沿岸でのナマコや貝類の漁獲は女性が担っています。
干潮時、女性はバケツなどをもってドロドロの茶色い干潟へ行き、徒手にて漁獲していきます。
私も漁に同行しました。ホームステイ先の子供たちが後をついてきます。いつの間にか私の前を歩き「タカ~~シ、こっちに貝がある。ここに小魚がいる」と教えてくれます。
しかし、どこに貝があるのかわかりません。子供たちは砂に埋もれた貝を素早く集めるのですが、私は貝を発見するに至りません。おまけに干潟の茶色いドロドロに足をとられてコケそうになる、ダメだこりゃ。

女性の多くは毎週末、市場において漁獲物を販売します。得たお金で生活に必要な物資を購入して村に戻ります。
最近は、電気、携帯電話、教育などにお金がかかるようになり、現金収入を得られる水産物の重要性は高まっています。
なかでもナマコは高値で売れることから、クミ村の人々にとって重要な資源のひとつでした。ナマコを求める中国人バイヤーも頻繁にクミ村を訪れ、その場で買い付けていました。
ナマコが漁獲禁止に

2017年9月、ナマコ資源の保全を目的に、ナマコの漁獲や販売を一切禁止する措置がフィジー政府によって導入されました。ナマコ漁業への規制強化といった世界的な流れがフィジーにも押し寄せたのです。
クミ村の人々にとって重要な収入源であったナマコ。その漁獲を禁じられた住民は収入減少にどう対応したのでしょうか。
まず、貝類やタコなど、ナマコ以外の水産物をより多く漁獲することにより、収入を補おうとする人々が増えました。2009年の調査では、貝類を漁獲する女性は全体の60%ほどでしたが、2018年は100%に達しました。
貝類をそのまま販売するのではなく、調理して高値で販売する女性も見られるようになりました。

農作物をより多く販売するものも見られるようになりました。村管理の森林を焼き払って農地を造成し、キャッサバやタロイモなどをたくさん栽培し、それを市場で販売するようになったのです。農地を従来の2倍、3倍へ拡大するものも見られました。

村人の一部は、ナマコ漁業を継続しました。規制が導入された当初、市場においてナマコを販売しても、咎められることはなかったようです。
しかし、政府による取り締まりが厳しくなり、2019年の調査では、ナマコを販売するものは確認できませんでした。
ナマコ資源の管理強化がもたらしたもの

村人の工夫によって、各世帯への経済的ダメージは最低限に抑えることができました。しかし、良いことばかりではなく、新たな課題も生み出されてしまいました。
ひとつは、貝類資源への漁獲圧力が高まったことです。ナマコの代わりに貝類が多く漁獲されるようになり、村の前浜では貝の生息密度が大幅に減少しました。このままでは、ナマコに続いて貝類まで減少してしまい、人々の現金収入源がさらに狭まってしまう可能性があります。
ふたつは、森林伐採の拡大です。ナマコ漁業が禁止されて以降、森林を伐採して耕作地を拡大する動きが広まりました。衛星写真でも森林喪失は一目瞭然ですし、クミ村の周辺を歩いてみましたが、森林が焼き払われている場所を数多く確認できました。
フィジーは赤土流出が課題となっています。森林伐採と農地拡大は土壌流出とそれによる海洋環境の悪化を招き、人々の生活を困窮化させるのではないかと心配になります。
フィジーからの留学生に期待

こうした調査は、フィジーから日本に来た留学生とともに行っています。留学生は大学院修了後、フィジー水産庁や南太平洋大学において働きます。
今回の調査で得た経験を、フィジーの水産政策に活かしてほしいと思いながら、2019年3月、留学生の門出をフィジー調査隊全員で祝いました。
-
文・写真鳥居 享司
\ さっそくアクションしよう /
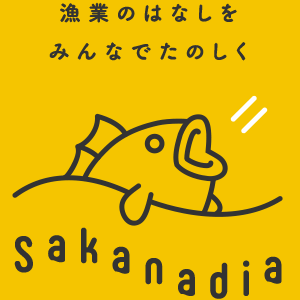
多くの人が漁業を身近に感じ漁業への関心を深めることで、持続可能なニッポンの漁業が未来へつながっていきます。




