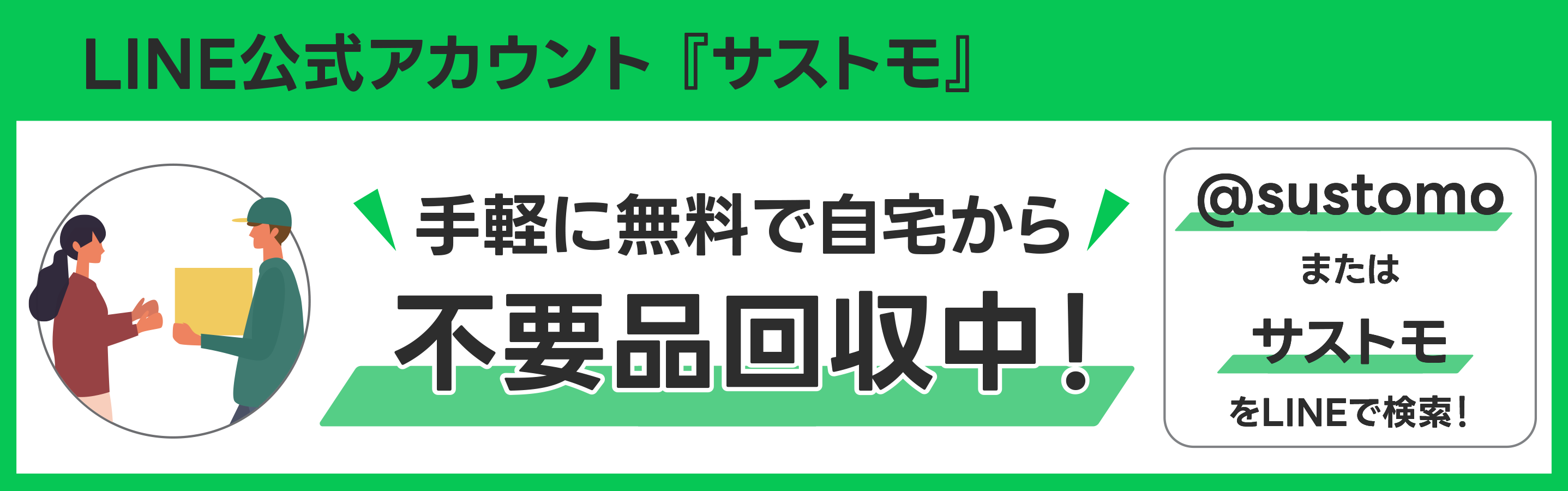東京の森を未来につなぐ――檜原村で生まれた「東京美林倶楽部」と30年の物語

東京都心から車で約2時間。東京都の西端に位置する檜原村(ひのはらむら)は、周囲を山々に囲まれ、村の70%が国立公園にも指定されている自然豊かな地域です。かつて炭作りで栄えたこの村は今、憩いやレジャーの場として親しまれる一方で、新たな形の林業が生まれるエリアにもなっています。
そんな活動の中心を担っているのが、檜原村を拠点に活動する林業会社「東京チェンソーズ」。
森の形を大きく変えず、持続可能な形で資源を活かし、規格外とされてきた木材にも新たな価値を見出し、都市と森をつなぐ取り組みを進めています。

しかし、個人が森に関わる機会は限られているのもまた事実。そこで東京チェンソーズは、30年かけて東京に手入れの行き届いた森林を育てるプロジェクトとして、2015年に「東京美林(びりん)倶楽部」をスタートさせました。市民や企業の会員とともに苗木を植え、下草刈りや枝打ち、間伐など作業を続け、次世代に続く森をつくる取り組みです。
檜原村の木材は建築材料や家具、おもちゃなど、さまざまな形で活用されており、2016年には東急電鉄の池上線「戸越銀座駅」の駅舎リニューアルにも採用され、都市に暮らす人々と森がつながるきっかけとなりました。
普段の生活では意識することのない「東京の森」のリアルな姿と、その森を未来へつなぐ取り組みについて、檜原村で話を伺いました。

炭作りで栄えた東京の山村で、林業の新たな形を模索する
檜原村の森を案内してくれたのは、東京チェンソーズの木田正人(きだ・まさと)さん。森林の中を歩きながら、会社の取り組みと檜原村の歴史について話を伺いました。

── 東京チェンソーズの活動について教えてください。
木田さん
日本の林業従事者は1960年頃、40万人を超えていましたが、現在はその1割ほどの約4万人にまで減少しています。木材価格の低下や補助金への依存など課題が多く、持続可能な産業としての形を模索する必要があります。
東京チェンソーズは2006年に檜原村で創業した林業会社です。当初は森林組合の下請けとして森林整備を行っていましたが、2014年に檜原村で約10haの山林を購入し、伐採と搬出、加工や製品販売、最近では森の空間活用まで事業の幅を広げてきました。この間、林業の仕事に魅力を感じて加わる仲間も増え、活動を進める原動力となっています。

── 檜原村の森にはどんな特徴があるのでしょうか?
木田さん
檜原村は、かつて炭作りで栄えた村です。コナラやクヌギといった広葉樹を伐採し、炭に加工したものを隣の旧五日市町(現あきる野市)の炭問屋を通じて各地へ出荷していました。
しかし、戦後になると復興のために建築資材が大量に必要となり、国の政策として広葉樹からスギ・ヒノキへの植え替えが進みました。現在見られる森の大半は、その時に植えられた人工林です。この流れは檜原村だけでなく、日本全国に共通する特徴だと思います。

── 私たちがよく目にする山の多くは、いわゆる原生林ではなく人工林なのですね。
木田さん
そうですね。今の檜原村の森林は、1950〜60年代に植えられたスギやヒノキが多く、建材として十分利用できるサイズになっています。しかし外国産材に押され、うまく活用されていないのが現状です。
また、植えた後の手入れ作業が不十分だったため、しっかり育たなかったり、林道や作業道の整備が追いつかず伐採できないという問題もあります。本来なら資源として活用できる木が、管理されないまま放置されているケースも多いんです。
── せっかく育てられた木が、伐採できなくなっている......?
道をつくれば、人が木々と触れ合える

これだけ豊かな森が広がっているのに、なぜ木材として活用できないのだろう? そんな疑問を抱えながら、木田さんに導かれて山の奥へと進んでいきます。
その途中、私たちが歩くこの作業道も、東京チェンソーズが設(しつら)えたものだと聞かされました。道はあって当然のものではなく、自分たちで作らなければいけないもの――そう認識を改めていると、作業中の東京チェンソーズメンバー・伏見直之さんと出会いました。

── こんにちは! 今はどんな作業をしているのですか?
伏見さん
斜面を掘って、土を落としながら丸太で固定し、小型の重機が通れるくらいの道を作っています。山の環境を壊さないよう、必要な部分だけを整えながら進めるのがポイントですね。この道は6年ほどかけて設えているのですが、あと100mで一般道と通じる林道までつながる予定です。
── 作業道を作るのは時間もかかるし、かなり地道な作業のように思えます。
伏見さん
そうですね。でも、道がないと木の伐採も搬出もできないし、人が森に入ることもできません。道を作ることで森の環境も良くなるし、林業を続けるうえで欠かせない仕事なんです。

── こうして道を開くことで、多くの人が森を訪れやすくなるのですね。
伏見さん
そうですね。私たちのような林業従事者以外も森に入りやすくなるので、よく森を案内するツアーを行うのですが、そこでの反応が面白いんです。
たとえば、デザイナーや木工職人と一緒に森を歩くと「この形の木が面白い!」とか「熊が縄張りを主張するために皮を剥いだ痕を活かしたい」といったアイデアが生まれる。これまでは道の補強に使うくらいだった根っこも、今ではユニークな家具やオブジェの部材として活用されるようになりました。

伏見さん
一般的な木材市場では、建築材料として使える真っ直ぐな幹の部分だけが丸太として流通し、木全体の約50%しか活用されていません。枝や根、曲がった部分は規格外とされ、ほとんどが山に残される運命だったんです。
東京チェンソーズではそうした部分にも価値を見出す「1本まるごと販売」という取り組みを行っているのですが、森の中で交わされる何気ない会話が、新しいプロダクトのヒントになることも多いですね。

── 森を整備することで、多くの人が山に関わり、新しい価値を見つけられるようになる。森の道を作ることは、林業従事者のためだけではないのですね。
木田さん
そう思います。今でも建材の主流は節のない真っ直ぐな木材ですが、最近は節の模様や曲がった枝を活かしたデザインが受け入れられることも増えてきました。木材に対する価値観が変わったおかげで、テーブルやベンチ、照明のパーツなど、これまで規格外とされていた部分にも新たな用途が生まれています。
きっと昔、檜原村で木を植えた人たちも「ただ伐るだけでなく、木を無駄なく使ってほしい」と思っているはずです。丸太の販売だけで利益を出すのは難しい時代ですが、こうした付加価値を生み出すことで、持続可能な形にしていければと考えています。

30年かけて森に関わり続ける「東京美林倶楽部」

東京チェンソーズでは森林の手入れやプロダクトの製造販売以外にも、森の中で行う各種ツアーや、子どもと一緒に学習机を作るワークショップを企画するなど、森や木材に触れる機会を多くの人に提供しています。
しかし、木は育つまでに長い年月を要するもの。一度の関わりではなく、 継続的に育てる関係が生まれれば、森への愛着も深まっていくはず。そんな思いから2015年にスタートしたのが、植樹から活用まで30年をかけて森と関わるための「東京美林倶楽部」です。

東京美林倶楽部では、会員が1口につき3本の苗木を植え、毎年の下草刈りや枝打ちを通じて、木の成長を見守ります。25年目以降には順次2本を間伐し、家具やおもちゃなどの材料に使うこともできます。最後の1本は森に残し、次の世代へと受け継いでいきます。
東京チェンソーズが管理する社有林では、これまでに 700本以上の木が植えられました。森が適切に育つよう、スタッフが定期的にメンテナンスを行いながら、今も30年の時間と向き合っている最中です。

── 東京美林倶楽部で植えられた木々が育っていますね。なぜ、このような取り組みを始めたのでしょうか?
木田さん
日本の林業では、伐採した後に再び植林されるケースが少ないのが実情です。なぜなら木を植えても、木材として活用できるまでには数十年の時間が必要で、その間に収益を生まないから。全国的に見ても、伐採後に再植林されるのはわずか3〜4割程度といわれています。
この問題を解決するため、管理資金として会費を先に集め、30年間責任を持って木を育てる仕組みとして考案したのが東京美林倶楽部です。2014年に東京チェンソーズがこの山のエリアを購入し、大きな木を伐採した後の土地を活用して、翌年からプロジェクトが始まりました。現在はスペースの関係で一時的に新規会員の募集を停止していますが、適した場所が見つかれば、新たな植樹を進めていきたいと考えています。
── なるほど、林業が構造的に抱えてしまう負担を、前もって分け合う仕組みなのですね。会員は具体的にはどう関わるのでしょうか?
木田さん
7年目までは毎年夏に下草刈りを行い、それ以降は余分な枝を剪定する枝打ちをします。ツルを取り除く作業も必要ですね。以前は「感謝祭」と言って、会員と交流する会も開催していました。
感謝祭はコロナ禍で一時中断していましたが、再開を予定しています。近くには 「日本の滝100選」に選ばれた払沢(ほっさわ)の滝もありますから、檜原村の夏祭りと合わせて、村全体を楽しんでもらえたらと思っています。

── 会員にはどんな方が参加されていますか?
木田さん
お子さんの入園や入学の記念として植樹するご家族、定年退職後に新たな挑戦として参加する方など、さまざまな方が関わっています。環境問題に関心を持ち「何か自分でも森に関われることはないか」と考えて参加される方も多いですね。
東京美林倶楽部の第一期に幼稚園児だった子どもが、今では中学生になり、イベントで再会して「こんなに大きくなったんだ」と成長を実感する場面もありました。30年間、同じ場所に通う理由ができたことで、檜原村を訪れることが季節の行事のような感覚になっているのかもしれません。
鉄道も森林も、未来に責任を持つインフラになる
こうした檜原村の木材は、東京23区内でも活用されています。2016年、東急電鉄池上線の戸越銀座駅で実施された「木になるリニューアル」もその一つ。

駅舎の柱やベンチ、壁面に檜原村で育ったスギやヒノキが使われ、都会のなかで木のぬくもりを感じられる空間へと生まれ変わりました。
東急電鉄はこの駅舎リニューアルをきっかけに東京美林倶楽部に参加し、法人会員として森づくりに関わり続けています。鉄道会社という立場で森と関わることについて、東急電鉄の小代雄大(おじろ・ゆうだい)さんに伺いました。

── 東急電鉄が東京美林倶楽部に関わるようになった経緯を教えてください。
小代さん
戸越銀座駅のリニューアルで、あきる野市と檜原村の木材を使うことになったことがきっかけです。その過程で沿線の方とのつながりを深めるため、「木材の生まれる現場を知ろう」と製材所を訪ねました。
最初は単発の取り組みとして考えていたのですが、森と関わることの意義を実感し、東京美林倶楽部の法人会員として参加することになりました。駅長や住民の方々と一緒に檜原村で苗木を植えてから、もう10年近くが経とうとしています。
東京の真ん中に生まれた「木の駅舎」が地域をつなぐ。リニューアルされた戸越銀座駅が守り残したもの
サストモの森

小代さん
実際に森を訪れ、木がどのように育ち、どのように加工され、駅の一部になっていくのかを知ると、すごく愛着が湧くんですよね。見学会に参加された方々も、とても楽しそうでした。
製材所を訪れる機会なんてなかなかありませんし、「この木が駅の一部になっているのか」と実感して喜んでくれました。私たちの手で植えた苗木も想像以上に大きくなっていて、今日はその成長を実感できたのが嬉しかったですね。
木田さん
普段の生活では「東京に森なんてあるの? 行けるの?」と思う人がほとんどですよね。東京美林倶楽部の活動を通じて「東京にも森があり、自分たちが関われる場所なんだ」と思ってもらえたのなら嬉しいです。

── 年月をかけて成長する木だからこそ、時間をかけた関わり方ができるのですね。
小代さん
もしかしたら、交通インフラという長い時間軸で取り組む事業に私たちが取り組んでいるからこそ、林業と通じ合う部分があったのかもしれません。たとえば、戸越銀座駅のリニューアルは約90年ぶりのものでしたし、駅舎も鉄道も「つくって終わり」ではなく、長い時間をかけて維持し続ける必要があります。だからこそ、愛着を持って長く関わり続けることを強く意識しているんです。
木田さん
数十年というスパンで取り組める事業は、そう多くはありません。森も駅も「自分たちがいなくなった後も続いていくもの」だからこそ、責任を持って未来を考えなければいけない。
そして、誰かが単独で頑張り続けるのではなく、仲間を集めることで持続可能な活動になっていく。東京美林倶楽部も、多くの方と30年かけて森を育てるうちに、新たな形に派生していくかもしれません。
森に人が入れば、新たな未来が動き出す

30年、50年、100年と人々の世代が変わっても続いていく森。その森が「良い姿」であり続けるためには、林業に関わる人だけでなく、多くの人が森に足を運び、関わり続ける仕組みが必要です。東京チェンソーズの事業や東京美林倶楽部の活動は、人と森をつなぎ、そこで生まれる循環を育んでいました。
人が入ることで森は整備され、新たな価値が生まれていくもの。誰も踏み入れなくなる前に、心地よい未来へとつなぐための30年。その歩みは、まだ始まったばかりです。

-
取材・執筆淺野義弘
X(旧Twitter): @asanoQm
Facebook: yoshihiro.asano.3954
撮影本永 創太
Instagram:souta.motonaga
編集友光だんご(Huuuu)
X(旧Twitter):inutekina
Facebook:tomomitsudango