古い企業の現実は変わらない――「昭和」「理不尽」批判された秘書検定、それでも貫く「今の考え」

6月1日、2022年春に卒業する大学生らの採用面接が正式に解禁された。就職活動を見据えた学生の多くが資格・検定を取得するが、そのなかでも知名度の高い「秘書検定」の問題がSNS上で波紋を呼んだ。出される問題が「理不尽」「現実に即していない」というのだ。半世紀の歴史を持つ秘書検定は当初、「女性が男性をサポートする」働き方を前提として作られた。時代が変わった今、秘書検定の存在意義とは。検定を運営する協会や現役の秘書に聞いた。(取材・文/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
秘書検定は「昭和」「理不尽」?
「上司からミスを指摘されたときは、仮にそれが自分のミスでなくても、言い訳などしないですぐにわびる」「上座には上位の人が座る」「報告は自分の感情や憶測を除いて、事実だけを正確に提供する」(実務技能検定協会編『秘書検定集中講義2級 改訂版』)
秘書検定には、こうした「社会常識」が詰まっている。出題されるのは、社会人としての資質やマナーといった振る舞いに関する問題から、書類の扱いや会議の準備など実務的なものまでと幅広い。そのうちの一つ、秘書として「必要とされる資質」に関する問題が、「看護師には解けない」として今年の2月にSNS上で拡散された。
"秘書A子は上司に、「K社から新製品発表会の案内状がまだ届いていないと連絡があった。漏れがないようにしてもらわないと困る」と注意された。しかし、案内状のリストにK社は入っていない。このような場合、A子はどのように対処すればよいか。"
正答は「上司にすぐに送ると言って、送り状にわびの言葉を書いて送り、リストに追加しておく」だ。ネット上では「K社はリストにないが送ってよいかと上司に確認する」「リストになぜK社がなかったのかを上司に尋ねる」といった選択肢を支持する人が多かった。しかし、解説には「自分には責任がないという言い訳になるので不適当」とある。
これを発端に「昭和」「理不尽」という批判があがった。倫理観が合致しないので「情報セキュリティー系の仕事に就かせてはだめ」といった投稿もあった。
検定を運営する実務技能検定協会の保坂恭世理事長は「秘書検定の知識はあくまでも基本原則です。自分の職場に置き換えて問題を解いていったら、検定試験は通用しなくなる」と説明する。
「一つの仕事を任されて専門的に何かをしていくというのは秘書職ではなくなると思うんですね。秘書は上司をサポートするというのが大前提にあり、職場によって仕事内容は変わってきます。賛否両論あるとは思うのですが、どんな職に就いても、どんな会社に行っても通用するような考え方の基本原則というふうに考えていただけるといいと思います」
一方で、「伝統的な日本企業の考え方が色濃く反映されている」とも話す。
秘書検定が「古い企業やおじさんの考えを可視化」
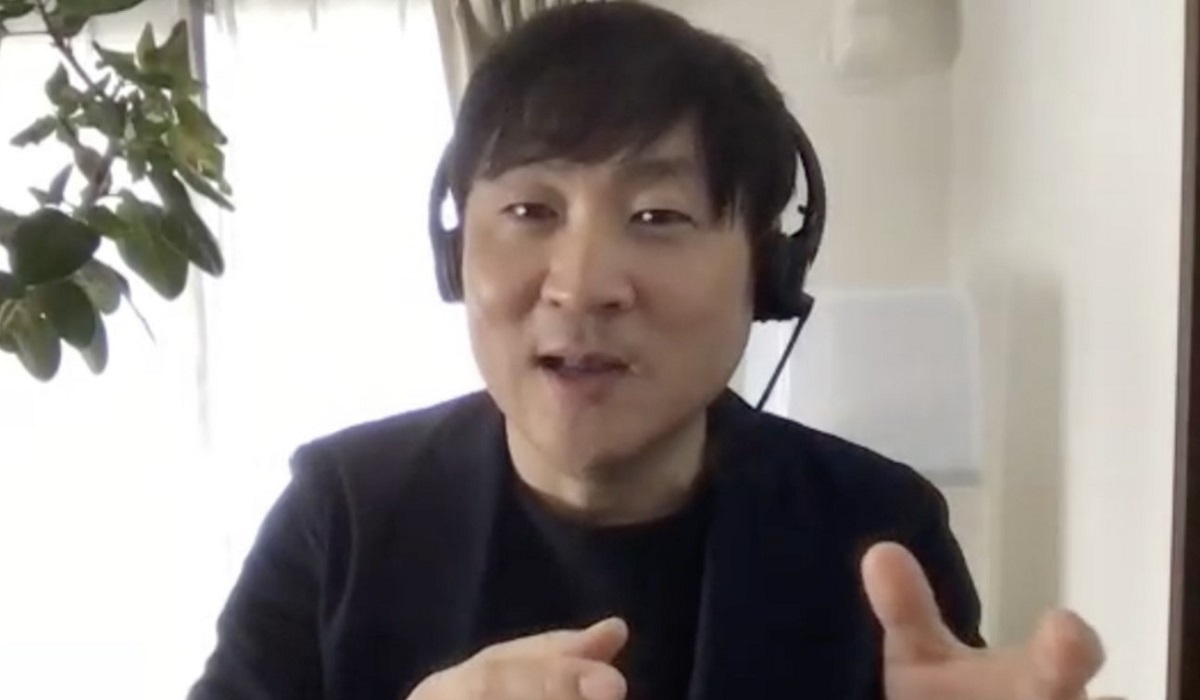
人事の専門家で、リクルートなどでこれまでに数十人の秘書を採用してきた曽和利光さんは、自身の秘書にも秘書検定を受けさせた。
「日本は100年以上続く企業が世界一多く、不文律も多くあります。秘書検定は、日本の古い企業の習慣を体系化・可視化している。価値観の是非は別として、『古い企業、あるいはおじさんはこう思っているよね』というのを知っておいて損はないと思います」
ネット上で批判があることに対しては、秘書検定の特異性が影響していると指摘する。簿記検定や英検など、多くの検定は専門能力を証明するものだが、秘書検定は価値観を扱う。試験問題として価値観に正否をつけるので、批判が伴うのは自然なことだという。
「ネット民の方から見たら、秘書検定の内容は非常に古い考えに映るかもしれません。ただ、それが日本の多くの企業の現状です。秘書検定に反発している人は、古い企業の体質に反発しているのではないでしょうか。たとえ秘書検定がなくなったとしても、そこにある現実は変わりません」
コロナ禍だからこそ「検定が生きる」可能性
秘書検定の始まりは1972年。当時、多くの企業では女性が補助的な役割を担っており、女性が男性をサポートする業務に就くことを想定して検定問題は作られた。
「一昔前までは、秘書といえば若い女性。話すときにはゆっくりとおしとやかに、声を3トーンくらい上げるのが美徳とされていました」
1993年に建設会社に入社、その後12年間秘書を務めた白川ミユキさんの最初の職場は、ステレオタイプの秘書像に近いのではないだろうか。朝は誰よりも早く出社し、上司のデスクを整える。新聞を用意し、それぞれの好みに合わせたお茶を入れる。上司のスケジュール管理、会議や来客、外出の準備をするほか、取引先のデータもまとめる。
「寿退社が当たり前の時代で『いつ辞めるの?』と言われたこともあります。女性は2、3年で辞めてくれたほうがありがたいとか、ニコニコしてムードを作ってくれればいいという話も耳にしました。男性中心の歴史ある企業でしたから、女性は企業の一員として扱われていないのではと感じることもありました」」
白川さんは、結婚しても仕事を続けた。その後、外資系ベンチャー企業に転職し役員秘書に就くと、これまでの企業との体質の違いに驚いた。初めての役員会議で張り切ってお茶を用意すると、社長に怒られた。お茶を出す役割は望まれていなかったのだ。その代わり、当時目新しかった社内ネットワーク導入のプロジェクトメンバーに加わり、数社との折衝から決定までを任されるなど、補佐的な業務以外の働きも求められた。
「時代の変化を肌で感じた」と白川さん。一口に秘書の仕事といっても、会社や上司、時代によって、求められるものは大きく異なる。
「秘書というと単なるサポートと考えられる方も多いかもしれません。利益を出すような仕事ではありませんが、『この人がいなければまわらない』というプロフェッショナルにならなければと思いました。でなければ結局、『秘書って要る?』となってしまう」

都内のIT企業で役員秘書を務める田名網美代子さんは、「この1年、支障なくリモートで仕事ができている」と話す。IT化により、スケジュール管理はツールを使用して効率的に進められるようになった。その代わり、コロナ禍で増えていくツールは、上司の疑問や要望に答えられるよう必要に応じて先回りして習得する。
秘書に求められるスキルは、変化を続けている。検定の内容も、時代とともに変わってきているのか。検定協会の保坂理事長はこう話す。
「業務やマナーは多少変化があるので、試験問題は毎年アップデートしています。ただ、検定の根底にある人としての考え方や、人に与える印象の良しあしは根本的にはそう変わりはないですから、今の考え方は貫いていきます」
目指しているのは、「人柄育成」だ。
「ビジネス社会において、どういった表現や行動を相手に印象づければ仕事がやりやすくなるのか。多くの人は明るい人を好み、素直に受け答えができる人を好みます。明るいと思ってもらうには、表情だったり、声の出し方や話し方だったり。素直だと思ってもらうには、言葉遣いや所作、態度、振る舞いですね。それがきちんとできて、初めて感じのいい人柄だと万人に思ってもらえる。私どもの検定を受けることで、これから出ようとする社会でどういった対応が求められるのか、社会を垣間見ることができるので、いい勉強になるのではないでしょうか」
就職活動前に取得する定番の検定として知られる秘書検定。これまで受験した770万人超のうち、7割以上が学生だ。今年の3月から、2級と3級はテストセンターでオンライン受験もできるようになった。前出の曽和さんは、コロナ禍だからこそ、就職活動に秘書検定が生きる可能性を指摘する。
「秘書検定においては、資格の有無よりも身になっているかが重要だと思っています。それは必ず所作に表れる。ですが、コロナ禍のオンライン面接では、対面のときより得られる情報が少なくなっています。そういう意味では、採用する上で秘書検定がオンラインでは見抜けない部分を担保する安心材料になるかもしれません」
元記事は こちら





