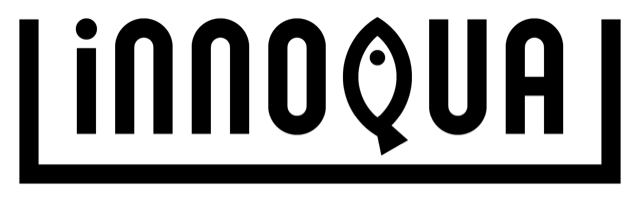ライバルと利用時間をずらして、ナワバリを譲り合うバンドウイルカ

本日はイルカの交友関係の研究について紹介します。
参考:Picky dolphins are choosy about their friends
内容は、「同じ生息域を持つライバル同士のイルカのグループは、出現する時間を調節して、上手く生息域をシェアしている」というものです。
"仲良し同士"で形成されるイルカのグループ
水族館のショーなどで馴染み深く、高い知性を持った哺乳類として有名なイルカは野生において群れで暮らしています。有名な"バンドウイルカ"の群れにおいてはこの群れのメンバーがしばしば変化しているのをご存知でしょうか?
このメンバーの入れ替わりはランダムで起こっている訳でなく、個々のイルカが他のメンバーと一緒にこれからずっと暮らせるかを判断して行われているのです。学校や会社などでの人間のグループ形成ととても似ています。
また、他のグループとは距離を置いて生息域を形成するのが通常です。
群れで狩りをするため、メンバーの引き抜きや餌の量が減ってしまうというデメリットを考えると当然の行動ですね。
トリエステ湾のバンドウイルカ
今回紹介する研究は、前述の「他のグループとは距離を置く」というイルカのグループ行動の通説とは異なった行動をするイルカ達の話で、イタリア付近のトリエステ湾におけるバンドウイルカの生態を16年以上もかけて調査した研究者達によって発見されたものです。
まず研究者達は、トリエステ湾に生息するバンドウイルカのうち、2つの大きなグループの関係について調査しました。
それぞれのグループは、内部は深く安定した友好関係が築けていますが、互いにライバル関係にあります。そのため、近づきたくないのですが、離れた所に住むのではなく、同じ生息域を違う時間に利用することにしたのです。
具体的には、朝と昼に片方のグループが、昼と夜にもう片方のグループが現れるといった具合です。このような1日のうちの時間帯におけるナワバリの移り変わりは哺乳類の中では今回初めて観測されたそうです。
イルカの社会性
イルカのグループ形成の仕方や、グループ同士で近づかないようにする行動、グループ同士で違う時間に縄張りを利用するという行動は、とても人間に近しいものを感じます。
そして、このような人間に近しい社会性を持った生き物の研究というのは、我々人間の社会性がどこまで遺伝子レベルで制御されている本能なのか、何がヒトを"人間"たらしめているのかということを知るヒントになるかもしれません。
このような進化生物学的な研究も、注目分野として今後紹介していきたいと考えております。