「フラワーロス」から考える、花と人にやさしいサステナブルな仕組み

5月は母の日に際して、定番のカーネーションをはじめとする花を贈った人も多かったのではないでしょうか。こういった記念日やイベントごとでなくても、暮らしの一部に花を取り入れることは、私たちの心を癒し、日常に彩りをもたらしてくれます。
しかし、その裏側では市場に出回った花のおよそ30〜40%が消費者の手元に届く前に廃棄されているとも言われており、その経済損失は年間1500億円にまで上ると推計されています(参照元:朝日新聞)。このように、まだ綺麗な状態の花が生産や流通の過程で廃棄されてしまう「フラワーロス」の問題が近年注目され始めています。本記事では、フラワーロスの複雑な背景を紐解きながら、花と人間のサステナブルな未来に向けた取り組みを紹介します。
さまざまな問題が絡み合うフラワーロスの背景

フラワーロスの問題は、単に「花が捨てられてもったいない」という話にとどまりません。花の見た目や鮮度の良さを維持するために、花の生産・流通過程で、大量の水や電力、輸送に伴うガソリンなど、さまざまな資源やエネルギーが投入されています。また、このようなエネルギー消費によって温室効果ガスの排出といった環境負荷もかかっています。つまり、花だけでなく、その背後にある膨大な資源も捨てられていると言えます。それに加え、生産者によって手間暇かけて育てられた花が、誰にも届かずに捨てられるのは倫理的にも望ましくありません。
では、なぜフラワーロスの問題が生じているのでしょうか? その原因は生産・流通・消費と、花がたどるすべてのプロセスに潜んでいます。
規格に合わない花は、そもそも市場に出せない
栽培した花を出荷するためには、茎の長さや花びらの数などを細かくチェックして、卸売市場で販売するための規格に合わせて花を選別しなければなりません。少しでも規格から外れているものは、消費者が目にする前の段階で廃棄されてしまいます。
プロダクトアウト型の生産
花き業界の生産上の問題として取り上げられるのは、消費者のニーズよりも生産者が望む供給量に基づいて出荷される「プロダクトアウト型」の生産システムです。生産者がつくりたい花をつくり市場に持ち込むという流れが通例のため、過剰に生産されたものの、需要に合わず売れ残ってしまいます。
流通に時間がかかりすぎる
鮮度は切り花の命。収穫後から数日〜1週間が良い鮮度を保てるピークであり、輸送に1日余計にかかるごとに、花の価値は15%ずつ下がるとも言われています(参照元:BBC)。しかし、多くの花が卸売市場を経由して流通しており、出荷元から消費者までの距離の長さが鮮度の低下につながっています。
イベントでの大量使用と一括廃棄
結婚式や展示会などでは、一度きりの用途のために大量の花が使われますが、それらは短期間で役目を終えた後、再活用されることなく一気に廃棄されてしまうケースが多いです。
購入者側の選好
一般的に、花は見た目や形の美しさで価値を判断されるため、多少の曲がりがあったり、不揃いな色味の花への理解は限定的です。また、花はギフトとしての用途も多いため、なおさら見た目が重視される傾向があります。
廃棄削減に向けたソリューション
さまざまなプロセスに原因が潜むフラワーロスですが、どんなソリューションがあるのでしょうか?
再活用・寄付の取り組み
再活用や寄付の取り組みは、本来廃棄されるはずの花を活かして、資源の無駄を防ぐとともに、人々に精神的な癒しや喜びを届ける効果もあります。インドの「HelpUsGreen」は、寺院などで廃棄された花を収集し、それらをアップサイクルしてお香をつくる取り組みをしています。また、アメリカの「Repeat Roses」では、イベントで使用された花を回収後に花束として再アレンジし、それらを病院やシェルターなどに寄付しています。さらに、ここで再利用された花を再度回収して堆肥化することで、フラワーロス削減に貢献しています。
生産・流通の仕組みの見直し
生産者と販売者の距離を近づけ、需要に応じた生産・流通体制を整えることで、余剰生産や在庫を根本から減らし、環境負荷や経済的損失の削減につなげることができます。フラワーショップのなかには、オークションや卸売を経由せず、生産者から直接買い付けた花を販売することによって、より鮮度の高い花を消費者に提供しているところもあります。その他にも、オランダを本拠に置く世界最大の花き市場である「Royal FloraHolland」では、デジタルプラットフォームを提供することで、生産者とバイヤー間の商取引と物流のプロセスを一元的に管理することを可能にし、取引の効率性と透明性を向上させています。
認証制度によるサステナビリティの推進
花の生産における環境・社会への配慮を可視化するものとして、生産された花や企業に与えられる認証への注目が世界的に高まっています。購入者がこれらの認証ラベルの意味を理解し、意識的に選ぶことで、よりサステナブルな花の生産・流通を後押しできます。ここでは世界各国のサステナブルな花の生産に関する認証制度を取り上げます。
1.Green Florist(オランダ)
花大国として世界最大の花の輸出量を誇るオランダで、サステナブルな方法で購入者に花を届けている花屋に与えられるのが「Green Florist」という認証です。この認証活動はオランダを拠点とするオンラインギフトショップである「Topgeschenken Nederland B.V.」の花部門が主導しており、ブーケの販売までのサステナブルなプロセスを追跡可能にすることを目的にしています。取り扱う商品の環境への配慮やエネルギー消費の削減などを含めた細かい観点で「FSI(Floriculture Sustainability Initiative)」が承認している基準をクリアした花屋が「Green Florist」として認定されます。これにより、購入者はサステナビリティに積極的に取り組んでいる花屋のもとで、環境や社会に配慮した選択をしやすくなります。
2.Plante Bleue(フランス)
「Plante Bleue」は、フランスの園芸・苗木業者向けの国家承認の認証です。この認証は、水やエネルギー、廃棄物の管理、作物保護などを含む環境配慮に関する基準を満たした生産者に与えられます。この認証によって消費者がラベルを目印に安心して環境にやさしい花や植物を選べるだけでなく、その環境配慮によって生産者・販売者の市場価値や社会的地位も高まります。それに加え、フランスの地方自治体にとっても、公共緑化で環境基準を満たす植物を選ぶ指標となり、持続可能なまちづくりに役立ちます。
3.Florverde®Sustainable Flowers(FSF)(コロンビア)
南米のコロンビアも世界有数の花の生産国として知られています。「FSF」はコロンビアを中心とした花き生産における認証で、花が消費者のもとへ届くまでのプロセスでの環境・社会・品質に関する基準を満たした生産者に与えられます。この認証ラベルの所有者は、顧客に対してラベルの付いた植物を購入することの価値を明確に伝えることが求められています。

最後に
フラワーロスは、私たちの社会システムや価値観を映し出す課題ではないでしょうか。花き業界における生産・流通の仕組みや消費者が花を選ぶ基準など、私たちが花を購入するまでの各段階に廃棄を生み出す要因が潜んでいます。今後も花を楽しむためにも、フラワーロスの削減に向けて、現状の生産から消費までのプロセス全体を見直す必要があるのではないでしょうか。
元記事はこちら
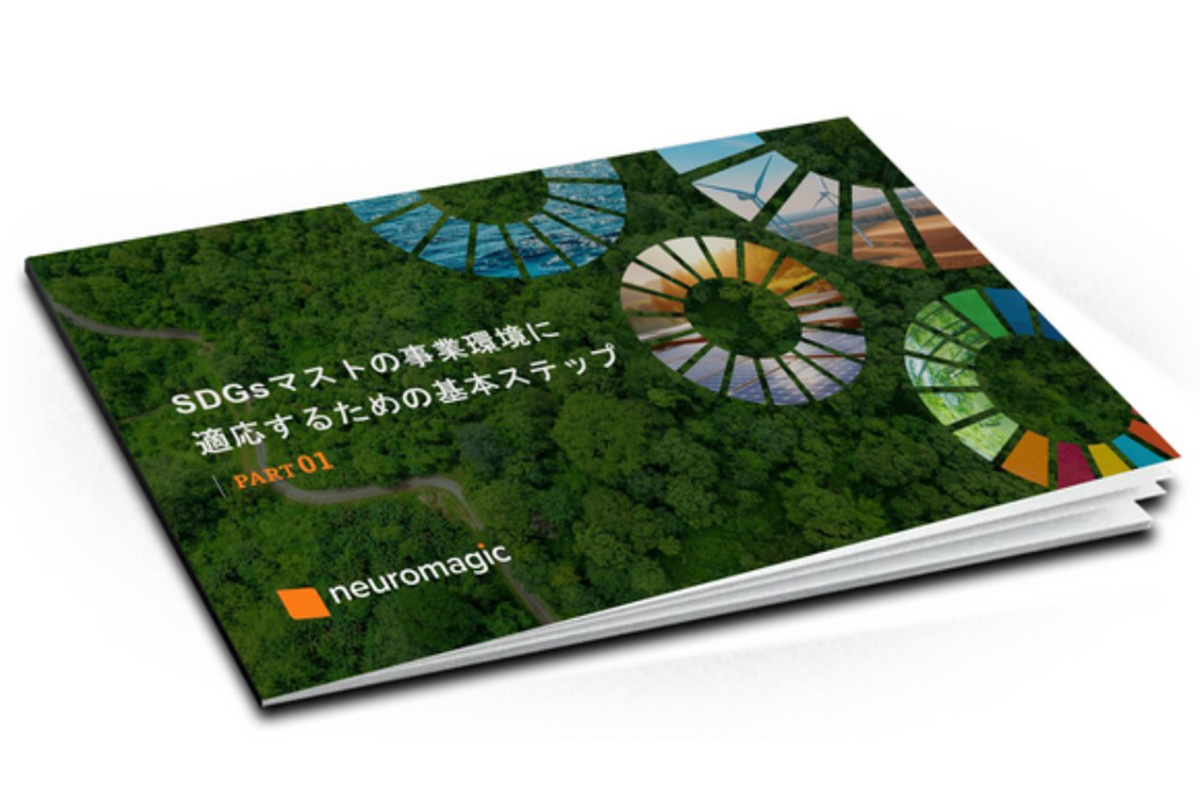
ニューロマジックでは、4つのパートにまとめた「SDGsマストの事業環境に適応するための基本ステップ」のパート1(30ページ)を無料で公開しています。SDGsの概要を改めて整理し、ビジネスにおける重要性や手法をまとめたガイドブックです。
その他資料も無料で公開しています
公開資料一覧:
https://landing.neuromagic.com/sx#downloads

ニューロマジック(Neuromagic)SusSolグループ
ニューロマジックのSusSol(サステナビリティソリューションズグループ)は、デジタルデザイン、戦略、サステナビリティの豊富な経験を活かし、企業のサステナビリティ戦略統合を支援します。コンサルティング、リサーチ、ワークショップを通して、マテリアリティ評価、KPI設定、ブランド強化、情報開示をサポート。さらに、Neuromagic TokyoとAmsterdamが主導するCSRDコンサルティングを通じて、EUにおける日本企業の子会社が規制遵守と適合を果たせるようサポートします。





