本当に明日届かなくちゃダメ? 持続可能な物流のために必要な意識変革とDX

家にいながら欲しいものを気軽に手に入れられるインターネット通販(EC)の普及で、当日配送や送料無料など、消費者にとって便利なサービスも当たり前になった。しかし、「便利」の裏側には課題も多く、最近は物流の「2024年問題」が社会的な関心を集めている。そこで、配送車両の走行ルート最適化システムを提供する、株式会社オプティマインドの齋藤貴也さんに、三菱電機イベントスクエアMEToA Ginza 「from VOICE」編集部が話を伺った。
"ワクワク"するサステナブルのヒントを教えてくれた人
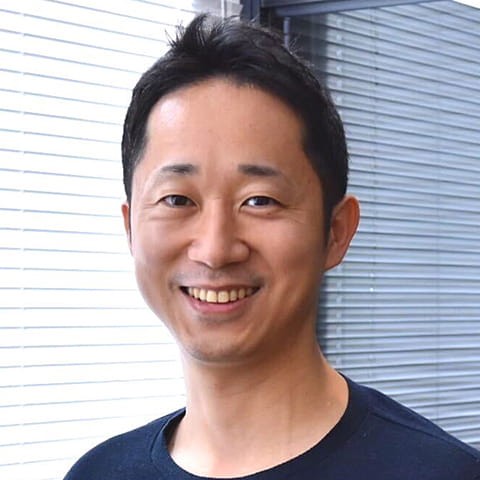
齋藤 貴也さん
株式会社オプティマインド マーケティング統括責任者。大学卒業後、野村證券株式会社入社。富裕層・法人の資産運用・事業承継などのコンサルティング業務に従事。2019年4月にオプティマインド参画。SMBセールスチームを立ち上げ、インサイドセールスチームの推進を経験したのち、現在はマーケティングを統括。
法改正後も深刻化する配送業界の問題

「EC市場が広がっていく中で、販売業者が強化してきたサービスの1つが、『早く届ける』ということ。各地に倉庫などの物流拠点を増やして、そこから消費者までの『ラストワンマイル』と呼ばれる区間を短くすることで、注文した商品が当日に届くほどの配送スピードを実現してきました。消費者としては、早く届くのは嬉しいことに違いないのですが、その裏では配送ドライバーの負担が大きくなっているんです」
こう話すのは、配送ルート最適化システム「Loogia(ルージア)」を手掛けるベンチャー企業・株式会社オプティマインドで、マーケティングを統括する齋藤貴也さんだ。スマートフォンの普及が進んだ2010年頃から爆発的に拡大したEC市場。世の中の買い物のあり方が変化したことによって、配送ドライバーの負担が大きくなる理由を、齋藤さんは次のように解説する。
「たとえば、以前なら自分で実店舗に行ってまとめ買いしていた品も、今はネットで個別に注文できますから、配送する荷物の数が爆発的に増加するのも当然です。倉庫などの物流拠点は、ロボットの導入などで効率化を進める余地があるのですが、配送ばかりは自動化する訳にはいかないので、運ぶモノの数だけ車両とヒトが必要になります。結果として運ばれるモノの数に対してマンパワーが足らず、ドライバーの負担や長時間労働が増えてしまっているんです」
人々の生活に欠かせない物流インフラが、時間外労働などの過剰な負担を前提としたものでは、持続可能性に大きな懸念がある。そこで、国は2024年4月から改正労働基準法を施行。ドライバーの年間の拘束時間の上限は現行の3,516時間から3,300時間までに引き下げられ、残業時間は新たに960時間までとするなど規制が強化された。しかし、ドライバーの就業者数が変わらないままでの稼働時間の減少は、配送力不足に直接つながってしまう。そうして生じる様々な課題が、物流の「2024年問題」と呼ばれるものだ。
「物量に対してドライバーの人手が減少傾向にある中で、配送業者は給料を上げなければ人員を確保できなくなります。ただ、物流業界は多重下請け構造が一般的。配送の依頼元である『荷主』企業や、元請けの運輸会社に価格交渉して、ドライバーの給料を上げるといった対応がとれる企業は多くありません。このままでは、人件費で利益が圧迫され、倒産してしまう中小の配送事業者も出てきてしまいます。また、運賃が変わらなければ、ドライバーは稼働時間の減少分だけ収入も下がり、さらに離職が進んでしまう。これらの課題に有効な手立てがとられなかった場合、2030年には国内全体で34%もの配送力不足が生じると試算されているんです。つまりこのままでは今、消費者が当たり前に受けられているサービスが、受けられなくなってしまいます」
術によってラストワンマイルを効率化
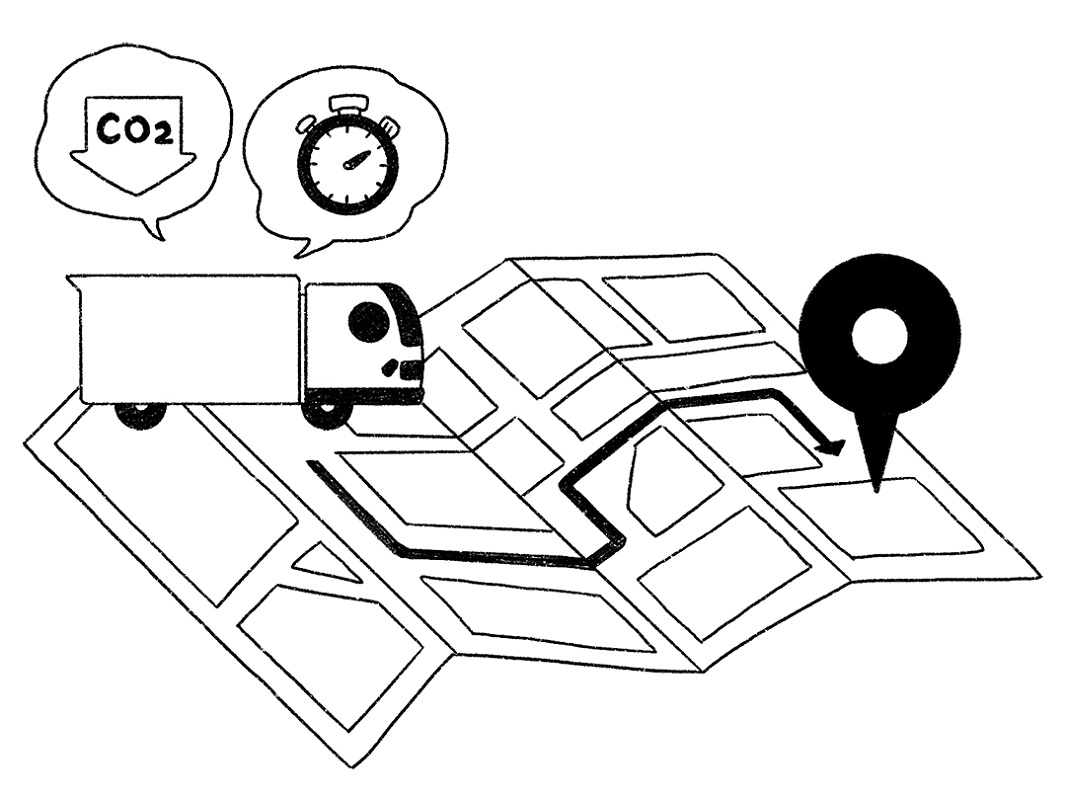
齋藤さんは配送業者の労働環境の課題について、「消費者も含めたサプライチェーン全体で解決すべき」と語りつつも、まず業界内に長年をかけて根付いた業界構造や商慣行が前提としてあることを強調する。
「代表的な例では、倉庫などの物流拠点に到着したドライバーが、荷物の積み降ろしのために待機する『荷待ち』時間の問題があります。物流拠点側の都合でこの時間が長くなりがちなため、配送業務の非効率化を招いています。また、荷物の積み降ろしを荷主側が行うのか、ドライバーが担うのかという線引きも明確ではなく、荷役作業を無償で行っているドライバーも少なくありません」
こうした課題の改善を図るため、政府は2023年6月に「物流改革に向けた政策パッケージ」を策定。荷待ちをはじめとする商慣行の見直しと、物流の効率化に加えて、荷主・消費者の行動変容についても、それぞれ具体的な施策を明示している。このうち物流の効率化における施策として挙げられている項目の1つが「物流DX」の推進であり、オプティマインドはこの分野でサービスを展開している。
「私たちが提供するLoogiaは、配送計画を自動作成するサービスで、配送業者が担うラストワンマイルの効率化に特化しています。配送計画とは、複数の車両がどの順番で集荷・配送していくのかを定めるもの。配送計画の作成は一般的に、ドライバー経験を積んで地域を熟知したスタッフが配車係となって、荷主から届いた伝票を机の上で並び替えるなどアナログな方法で、ある程度の時間をかけて行います。Loogiaでは必要な情報を打ち込めば、AIが最低限の車両数と走行距離・時間で配送を行えるルートを算出することができます」
実際の導入事例によると、ドライバー1人当たりの配送時間が1日2時間削減されたり、従来は48台の車両が必要だったルートを44台で回れたりといった効果が表れているという。
「Loogiaは、配車計画の作成だけではなく、各車両の走行状況を管理でき、またドライバーのナビゲーションアプリとも連動しています。このサービスによって、ドライバーの労働と事業者のコスト面での負担を減らすとともに、CO2削減が図れるため、環境面でも社会の持続可能性に寄与できると考えています」
人を想うことが、健全な社会システムをつくる

オプティマインドは、創業者である松下健氏が名古屋大学で研究していた「最適化アルゴリズム」の理論を活用して産業の課題を解決するベンチャーとして、2015年に設立。配送業界に着目し、Loogiaをリリースしたのは2019年だが、当初から現場に快く受け入れられた訳ではないと齋藤さんは振り返る。
「開発を手掛けたのは物流に関して専門外のメンバーだったので、実際に働く方々のニーズに応えられる性能ではなかったんです。そんな中で私たちは、実際に配送の仕事に立ち会わせていただきながら、現場の声をサービスに反映させていきました。そうして機能を拡充することで、今では大手メーカーや小売なども含む200社以上に導入いただいています」
Loogiaが算出するのは、ただの配送順ではなく「配送」に最適なルート。たとえば配送先の路肩への左付けでの停車や、事故が多い右折を抑制することをルートの算出条件に組み込むこともできる。これらは、現場の声を聞きながら搭載されていった機能だという。
「ラストワンマイルを担うドライバーには、郵便物を運ぶ方や、自動販売機の補充を行う方、自社倉庫から店舗へと商品を届ける方など、さまざまな方がいます。Loogiaは、そうした幅広い声をいただくことで、汎用性の高いサービスに『鍛えてもらった』と思っています」
実際に現場の人たちと接してきた齋藤さんたちが願うのは、配送業界に"ゆとり"が広がることだ。
「ドライバーは人手が少ない中で日々業務に追われていますし、配車担当の方は長年の知識と感覚が必要なので、業務が属人化しがちです。そこに、技術による業務効率化でゆとりを生めれば、職場や配送先の消費者、またはそれぞれの家族とのコミュニケーションなどに時間と気持ちを割くこともできるはず。それによって人間味に関わる部分までを配送業務に織り込んでいけたなら、業界の魅力はより大きくなっていくと思うんです」
齋藤さんは、最適化アルゴリズムのシステムを、訪問医療車両や過疎地域のオンデマンド交通といった配送以外の業界、さらには自動運転技術が発展した未来の社会全体の交通環境に役立てていきたいとも展望している。オプティマインドのように、技術で社会課題の解決を図る企業がいる一方で、消費者一人ひとりが今日からできる行動には、どんなことがあるのだろうか。
「バラバラに注文していた商品をまとめることで配送回数を減らしたり、再配達をしなくて済むように、宅配ボックスを設置したり、きちんと指定時間に荷物を受け取っていただいたり、色々なことが挙げられます。大事なのは、こうした小さな行動なんです。当たり前に思われてきた便利な世の中は、実は当たり前に成り立っているものではなく、誰かの負担によってなんとか支えられている。そうした意識のもとで、消費者の皆さんを含む社会全体が、物流システムの健全化に協力する行動を選んでいくことが大事だと思います」
元記事はこちら

三菱電機イベントスクエア METoA Ginza
「from VOICE」
「ワクワクするサステナブルを、ここから。」を掲げ、三菱電機社員が社会の皆さまと共に学び、共に考えながら、その先にある"ワクワクする"社会を創るべく活動しています。日常にある身近な疑問"VOICE"から次なる時代のチャンスを探すメディア「from VOICE」を企画・運営しています。最新情報はインスタグラムで配信中です。皆さまのVOICEも、こちらにお寄せください。





