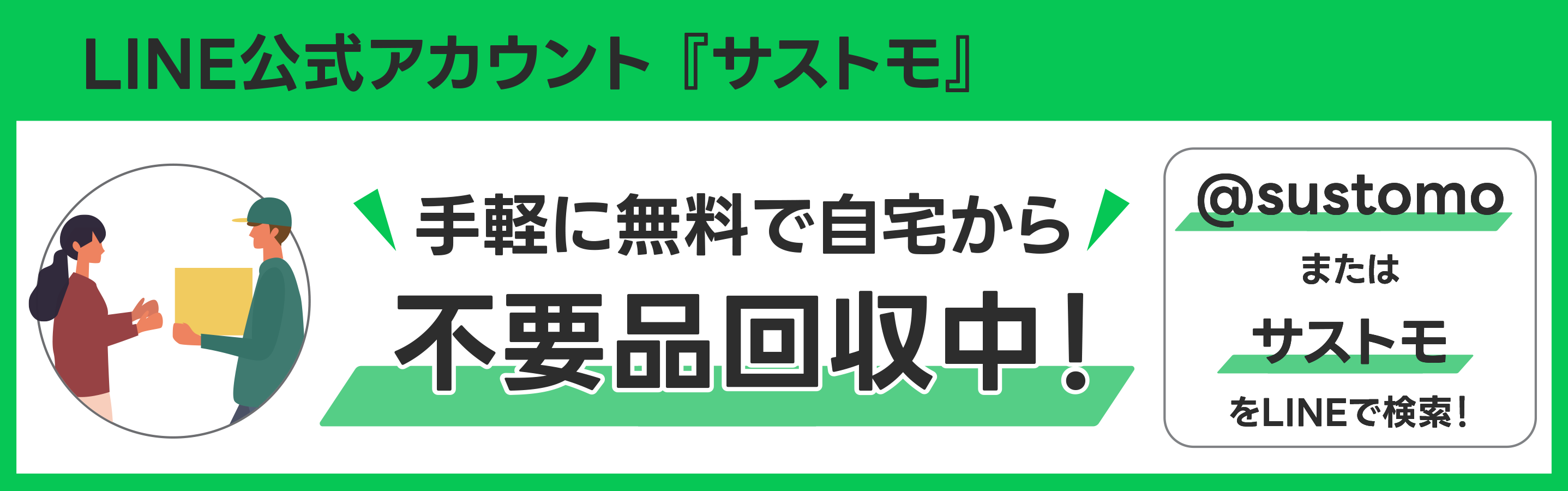トイレから読み解く社会課題|日本のトイレはなぜこんなに進化した?

安全かつ清潔で、便利な機能が備わっている日本のトイレ。それを私たちは当たり前に捉えがちだが、海外と比べると独自の進化を遂げているよう。その理由や世界のトイレ事情について、 "トイレハンター"として特徴的なトイレの観察を続けるマリトモさんに、三菱電機イベントスクエアMEToA Ginzaのfrom VOICE編集部がお話を伺った。
"ワクワク"するサステナブルのヒントを教えてくれた人

マリトモさん
トイレハンター・トイレ評論家。Webサイトの企画ディレクションやマーケティング、デザイン制作のほか、ライターやカメラマンとしても活動。その傍ら、10年以上かけて全国各地300か所以上のトイレを独自取材し、『ニッポンのトイレほか』(アスペクト刊)にまとめる。
世界から注目が集まる日本のトイレ

「日本人特有のおもてなし精神と、細やかな技術力。それが、衛生的で機能も充実した日本のトイレ空間をつくり上げる土台になっているのだと思います」
こう語るのは、"トイレハンター"の肩書きで、国内外のトイレを巡り、トイレ関係の文筆・評論活動などを展開するマリトモさんだ。マリトモさんに、現在の日本のトイレ空間が形成された経緯を伺うと、半世紀ほど前のことからさかのぼって教えてくれた。
「近現代の日本のトイレ事情で、大きな変化といえばやはり、和式から洋式へのシフトです。1964年の東京五輪に向けて建設された公営団地に洋式トイレが整備されたことをきっかけに、徐々に和式の需要が減少していきました。2015年には、TOTOが出荷する便座のうち、和式の割合が1%を切ったといいます」
そのような変化の過程で、日本のトイレメーカーは、暖房便座や乾燥に脱臭、ふたの自動開閉など、洋式便器に搭載するさまざまな機能を開発し、追加していった。そうした機能の中でも、日本のトイレの独自性を象徴するのが、温水洗浄便座だろう。
「温水洗浄便座を生み出すには、おもてなし精神とものづくり技術だけではなく、日本の水資源が不可欠だったと私は考えています。というのも、日本のように不純物の混じっていない軟水でなければ、温水洗浄便座の洗浄ノズルが詰まって壊れやすくなってしまうんです」
また、イギリスでは水周りにコンセントを設置することが感電防止のため法律で禁止されているなど、そもそも必要と考えられていないといった実態がある。それもまた、温水洗浄便座のような、電源を必要とする機能が海外で普及しにくい一因だという。
「トイレ機器メーカーさんの視点に立てば、海外展開の難しさは悩ましい課題だと思います。ただ私としては、インバウンド旅行客に現地でなければ味わえない日本らしさの一つとしてトイレ体験を提供することにも、大きな価値を感じています」
アートの力で公衆トイレの危険を減らす

「トイレからは、各国の文化や社会環境、時代背景などさまざまな情報が読み取れる」とマリトモさん。中でも公衆トイレには、それぞれの国の治安が表れていると語る。
「海外のトイレの個室は、ドアの膝から下の部分が空いているケースが多いのですが、これは外から見て不審な人がいないかどうかを確認できるようにするためです。日本でも、公衆トイレを隠れ蓑に使うような犯罪がゼロではありませんが、このような対策が必須とされるほどではありませんよね。言い換えれば、日本ほど安全に公衆トイレが利用できる国はないのです」
一方で、そんな日本の公衆トイレが、実際には「汚い」「臭い」「怖い」といったイメージを持たれ、使用を避けられる側面があることも事実だ。そこで日本財団と渋谷区は、2020年に「THE TOKYO TOILET」プロジェクトを始動した。
「このプロジェクトでは、安藤忠雄さんや隈研吾さんなど著名な建築家が手がけた、デザイン性と安全性が高いコンセプチュアルなトイレを渋谷区内の17か所に設置しています。デザインの力で公衆トイレのあり方を問い直そうという斬新な取り組みは、大変注目を集めています」
17のトイレの中でも、マリトモさんが特に感心したのは、カラフルなガラス張りの見た目が特徴的な、『はるのおがわコミュニティパークトイレ』。
「特殊なガラスを外壁に採用することで、誰も利用していない時には外からトイレの中の様子を確認でき、個室の鍵を閉めると不透明になる仕組みになっています。『自分が利用する際には外から見られたくないけれど、個室に入る前に中が見えないと不安』という、公衆トイレの利用へのハードルを、アート的なアプローチで解消してしまうのが、とても画期的だと思います」
プロジェクトではほかにも、ドアの開閉や便器洗浄などの操作がすべて音声式になっているものや、トイレ空間よりもコミュニティスペースを広くとったものなど、個性的なトイレがそろい、観光スポットとしても知名度を高めつつある。
「公衆トイレは利用者同士の善意できれいに維持される場であるとともに、絶対的な安全性が保たれるべき空間です。安全な公衆トイレをつくり出そうという取り組みを、トイレ先進国である日本が発信することは、世界中の犯罪に対して『NO』を宣言する意味合いがあるようにも感じます」
「究極のプライベート空間」を世界中に

「私は子どもの頃から不思議とトイレの夢を見ることが多くて、自分とトイレには何かしらの縁があるのかなと感じていました。そんな中で、"トイレハンター"としての活動に目覚めたのは、15年ほど前に、愛知県の刈谷ハイウェイオアシスという複合施設にある、『デラックストイレ』に出会ったことがきっかけでした」
マリトモさんは自身とトイレとのつながりの端緒についてこう語る。
「『デラックストイレ』には開設当初レッドカーペットが敷いてあり、トイレの中に展示物やソファが置かれていて、その豪華で広々としているトイレ空間に感銘を受けました。そこから日本各地にはこういう変わったトイレがもっとたくさんあるのではないかと思ったんです」
それからというもの、マリトモさんは日本中の個性的なトイレを独自取材し続け、2013年にはその成果をまとめた書籍『ニッポンのトイレほか』の出版に至った。
「取材を通して感じたのは、トイレは排泄という本能的な欲求を満たすだけでなく、気持ちを切り替えられる『究極のプライベート空間』だということ。そして、建物や施設の中のトイレには管理者の想いが色濃く表れているということでした」
出版後は、「面白いトイレを紹介する人」としてのメディア露出が増えたが、現在のマリトモさんの関心は、トイレをテーマに社会課題を啓発していくことに移っている。
「SDGsでも『安全な水とトイレを世界中に』という目標が掲げられているように、世界規模で見ると、衛生的なトイレの普及は喫緊の課題となっています。日本のトイレが進化し続ける一方で、今でも世界の3人に1人、人数にして約34億人が衛生的なトイレを使用できず、そのうち約5億人はトイレではなく野外で排泄しています。不衛生な排泄環境が病気の原因となり、命を落としてしまうこともあるくらい、トイレの整備は重要な問題なんです」
発展途上国などの上下水道すら通っていない環境では、衛生的なトイレを設置することは簡単ではない。そんな中、大手住宅設備機器メーカーのLIXIL社が取り組むソーシャルビジネス「SATO」では、トイレの衛生問題の解決に向けて、現地の実態に合わせた簡易トイレシステムの普及に取り組み、事業の黒字化を達成しているそうだ。
「高い技術を持つ日本企業だからこそ、世界のためにその技術を活用することで、世界中の誰もが『究極のプライベート空間』で安らぎを感じられるような未来を実現できるのではないかと思います。そのためには国境を超えた協業や、持続可能なビジネスプランの構築が重要になります。私個人で大きな活動はできませんが、より多くの人に世界のトイレ問題を知ってもらえるよう、声を上げ続け、啓発活動に努めていきます。そして、日本の皆さんにも、日ごろ当たり前に使っているトイレの素晴らしさを、改めて認識してほしいと思います」
元記事はこちら

三菱電機イベントスクエア METoA Ginza
「from VOICE」
「ワクワクするサステナブルを、ここから。」を掲げ、三菱電機社員が社会の皆さまと共に学び、共に考えながら、その先にある"ワクワクする"社会を創るべく活動しています。日常にある身近な疑問"VOICE"から次なる時代のチャンスを探すメディア「from VOICE」を企画・運営しています。最新情報はインスタグラムで配信中です。皆さまのVOICEも、こちらにお寄せください。