週4勤務、労働時間短縮、ベーシックインカム。世界の働き方改革の実験

世界でkaroshi(過労死)という言葉が認知されて久しいですが、日本の"働きすぎ問題"はいまだに大きな改善を見せてはいません。新型コロナウイルス感染症が広まったことで、急速にリモートワークが普及し、働く環境に大きな変化が生まれましたが、パンデミックの終息が近づくと共にオフィス回帰を進める企業も少なくありません。日本政府や一部の企業も働き方改革をさまざまな形で推進してきましたが、高度成長期以降に根付いた「長時間労働=美徳」という価値観は、企業文化や労働慣習に深く影響を与えています。これを払拭するのは容易ではないでしょう。
本記事では、そんな風潮に一石を投じる、各国で行われてきた働き方改革の実験やトレンドを紹介。歴史や文化と深く絡まっているため、他国の例をそのまま日本で反映するのは難しいかもしれませんが、新しい視点を持つためのヒントとなるのではないでしょうか。
アイスランドの「労働時間短縮」の実験

アイスランドで、レイキャビク市の職員と国家公務員を対象に2015年と2019年の2回にわたり、労働時間短縮実験が行われました。生産性を維持したままワーク・ライフを改善できるかが検証目的でした。参加者はアイスランドの労働人口の1%強に当たる2500人。週に40時間近く働いていた職員の労働時間を35〜36時間に減らしたところ、ストレスや極度の疲労が軽減してウェルビーイングが改善されたといいます。そして生産性やサービスは、維持、または向上したそうです。この結果を受け、アイスランドの労働組合が交渉を実施し、同国の労働人口の86%が労働時間を短縮、もしくは短縮の権利を獲得したそうです。(参照元:CNN)
イギリスの「週4日勤務」の実験

イギリスで、労働生産性の向上と従業員の幸福度向上を両立するため、2022年6月から12月にかけて、60社以上の従業員が試験的に週4日勤務を行いました。この実験は、「100:80:100」モデルに基づき実施されました。これは、労働者が生産性を100%維持することを約束する代わりに、以前の80%の労働時間に対して100%の給与を支払うというものです。結果、参加者の大半は、生産性のレベルが維持され、従業員の定着率と幸福度が改善されたそうです。事業収入はほぼ変わらず、病欠は65%減少。71%の従業員が燃え尽き症候群のレベルが低下したと報告しました。参加した61社のうち、56社は週4日勤務制の試験的な実施を継続し、18社は恒久的に導入すると決めたそうです。(参照元:World Economic Forum)
フィンランドの「ユニバーサルベーシックインカム(UBI)」実験

フィンランド政府は2017年からの2年間、「ベーシックインカム」給付実験を行いました。ベーシックインカムとは、Basic Income Earth Networkの定義によると「すべての人に個人単位で資力調査や労働要件を課さずに無条件で定期的に給付されるお金」のことです。フィンランドの他にも、ベーシックインカムの事件を行った国はありましたが、全国規模での初のランダム化比較試験(対象者を2つ以上のグループにランダムに分け、効果を検証すること)を行ったことが特徴です。実験の目的は、失業者が職場復帰しやすくなるかどうかを検証することでした。
この研究の結果、失業者の復職には至らなかったものの、ベーシックインカムが普及されたグループは比較対象グループよりも6日長く働いたそうです。ただし、2018年1月より政府が現金給付受給者に対しより多くの条件をつける施策を行ったため、それらが複雑に影響している可能性は否定できません。生活の満足度については、10段階で比較したところ、自己評価がベーシックインカムのグループの方が高いという結果がでました。(参照元:国立社会保障・人口問題研究所)
欧米で広がる「ノンリニアワークデイ」

ここ数年、従来の「何時から何時まで」と固定された枠に縛られず、従業員がそれぞれ最適な時間に働くノンリニアワークデイが広まっています。これは、決まった時間に働くのではなく、個々の生活に合わせて最適な時間に働くことで生産性を上げる試みです。この働き方は、労働を時間の消費で測るのではなく、成果ベースで見ることを促しています。(参照元:BBC)ただし、従業員同士のコミュニケーションを円滑に進めるためにコアタイムを設けることや、マネージャーが目標とビジョンを明確に設定する必要があります。この働き方は、生産性を向上し、燃え尽き症候群を回避するとして主にフレキシブルな性質を持つIT業界を中心に注目されています。
まずは自分に最適な働き方を考えてみる
今回紹介した働き方の実験やトレンドはごく一部にしかすぎません。世界中で従来の「週5日で9時から5時」という働き方が再考されはじめています。そしていくつかの実験が、よりフレキシブルで個人の生活を尊重した働き方が、生産性や利益につながると示唆しています。働き方改革には、個々のマインドセットの変革が必要不可欠です。従来の働き方にとらわれず、先進的な世界の取り組みを参考に、まずは自分に合った働き方を考えてみるのはどうでしょうか。そして周りと共有したり議論したりすることで、より生産性が高く、健康的な働き方を模索していく必要があるのではないでしょうか。
元記事はこちら
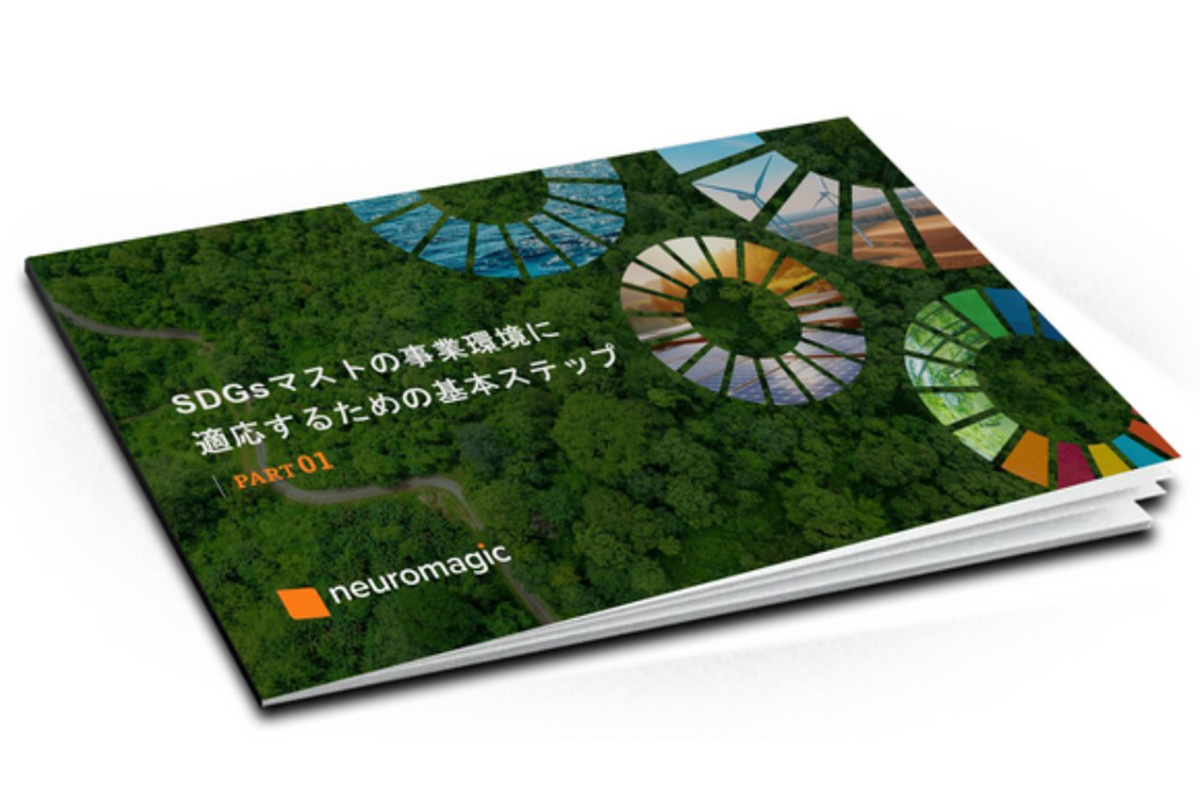
ニューロマジックでは、4つのパートにまとめた「SDGsマストの事業環境に適応するための基本ステップ」のパート1(30ページ)を無料で公開しています。SDGsの概要を改めて整理し、ビジネスにおける重要性や手法をまとめたガイドブックです。
その他資料も無料で公開しています
公開資料一覧:
https://landing.neuromagic.com/sx#downloads

ニューロマジック(Neuromagic)SusSolグループ
ニューロマジックのSusSol(サステナビリティソリューションズグループ)は、デジタルデザイン、戦略、サステナビリティの豊富な経験を活かし、企業のサステナビリティ戦略統合を支援します。コンサルティング、リサーチ、ワークショップを通して、マテリアリティ評価、KPI設定、ブランド強化、情報開示をサポート。さらに、Neuromagic TokyoとAmsterdamが主導するCSRDコンサルティングを通じて、EUにおける日本企業の子会社が規制遵守と適合を果たせるようサポートします。





