水産業を未来につなぐ ~震災から8年。「担い手」プロジェクトのその後。~

水産業を「かっこよくて、稼げて、革新的(新3K)な仕事にすること」をビジョンに掲げ、漁師たちが立ち上げたフィッシャーマン・ジャパン(FJ)が誕生して5年。「魚をとる人がいない」未来に立ち向かうために始動した「担い手を増やす」プロジェクトは、いま東北の海で仲間を増やし、新たなる挑戦に漕ぎ出していた。
水産業を変える。ひとりの漁師がたどり着いた結論
「震災で辞めていった漁師仲間を浜に戻したい、これが原点でした」
FJの代表理事である阿部勝太さんは8年前を振り返る。

石巻市北上町のわかめ漁師で、祖父も父も漁師という漁師一家の長男。彼の浜では震災直後、働き盛りの漁師たちが、復興工事で需要が増す土木事業に職を求め、クレーンなどの重機免許を取りに行き始めた。ベテラン漁師たちも、流されてしまった船や漁具を新調する難しさから、漁業を再開する気力を失っていた。
水産業には、阿部さんが生まれる前から課題があった。
例えば、海洋環境の悪化や、かつての過剰な漁獲による水産資源の枯渇。「魚がいなくなる」危機を地球規模で抱えている現状は日に日に悪化している。
1992年32万人いた漁師は、2016年には16万人にまで半減した。
近年漁師の平均年齢は60歳を超え、「魚をとる人がいなくなる」問題も深刻だ。
安定した収入が見込めないこと、体力資本であること、命がけであること。ある時から親が「大変だから」と子供に跡を継がせなくなったことも担い手減少の一因になっている。

浜を離れていく漁師仲間の背中。
悔しさがこみ上げた。
- 阿部
- 「この浜を本当に元に戻せるのか不安でした。でも状況が悪くなればなるほど、なにがなんでもどうにかしなきゃ、という思いがこみ上げてきたんです」
ここがなくなるのはさみしい。いやなことがあれば変えればいい。
一生住むなら楽しくすればいい。一生やるなら水産業を変えればいい。
この後、阿部さんは2年もの年月をかけて、同じ志をもつ漁師や魚屋などを探し集め、2014年FJを立ち上げる。
ミッションは漁師になりたい若者を増やすこと
FJは、水産業を「かっこよくて、稼げて、革新的(新3K)な仕事にすること」「子どもたちが憧れるような仕事にすること」をビジョンとして掲げている。
発足から5年たったいま、デザイナーや元商社マンなどさまざまな職業経験をもつスタッフが加わった。それぞれの得意分野を活かし、あらゆる角度から水産業に光を当てることで、その魅力を発信している。

そしていま、大きな前進を遂げようとしているのが、新たに漁師になりたい人を募り、彼らを受け入れる仕組みをつくるプロジェクト「TRITON PROJECT」だ。
発起人は、先に紹介した阿部さんと出会い、大きな挑戦の道へと進むことになった鈴木真悟さんだ。彼もまた、宮城県女川町で銀鮭を手がける漁師であり、水産加工会社を家族で経営している。

「TRITON PROJECT」は、漁師という職業の間口を広げ、担い手となる若者を増やすために2015年に始動した。漁師の住む場所を確保するための「漁師専用シェアハウス」が稼働し始めた2016年にも、鈴木さんはYahoo! JAPANが実施した「3.11企画」特集上で思いを静かに語り、多くの共感者から支援を集めている。
2016年「3.11企画」の記事はこちら
この当時、鈴木さんの会社の社員の平均年齢は60歳を超えていた。20〜30代の若手漁師が5名いたが、他は皆50代以上だった。
- 鈴木
- 「若い世代が入ってこない。この業界の魅力を若い人たちに伝えきれていないんです。新しく漁師を目指す人たちが増え、自ら水産業の魅力を発信することで、若い人がさらに若い人を呼ぶ、新しいサイクルが生まれたらいいなと思っています」

新たな出会いが変える、師弟がつなぐ水産業の未来
あれから3年。「TRITON PROJECT」が始動してからは4年目を数える。
- 鈴木
- 「新しく漁師になった若者は30人近くになりました。もちろん、後継ぎがいることに越したことはないけれど、父から子への世代継承が当然の業界で、『世襲ではない』漁師を30人近く宮城県内に呼び込めたことは全国的にも例を見ない事例だと思います」
東北に限ったことではないが、移住者へ吹く風は時に厳しい。ちいさな浜ならなおさらだ。しかし、師弟となった漁師たちは、その関係性を「親子」「家族」「友達」のようだという。担い手たちが「なくてはならない存在」となっている。

今年2月、石巻市雄勝町に明るいニュースが舞い込んだ。大阪から移住した担い手が、准組合員(共同漁業権)の資格を取得したのだ。漁をするライセンスとでもいうべき漁業権の取得は、海の資源を守るための大事な仕組みであるとはいえ、新規参入者にはハードルが高い。
このハードルを乗り越えたのが三浦大輝さんだ。就職したばかりの証券会社を退職し、2017年の夏、大阪から漁師になるためにこのまちに飛び込んできた若者だ。

三浦さんが「きっかけ」と話すのは、FJが行政や大学、漁協と連携して開催した「漁師学校」だ。漁師志望の若者が本格的な体験ができるカリキュラムが特徴で、その時講師をしていたのが、のちに三浦さんの親方となる佐藤一(はじめ)さんだった。
- 三浦
- 「最初は厳しそうやな......と思ったんですが、いつか自分の筏で漁がしたかったし、銀鮭、ホタテ、牡蠣といろんな魚種を扱っている親方からいろんなことを学びたいと思った。それにずっと先のことを考えている人でしたから」
佐藤さんのところで働きたい、三浦さんはFJのスタッフに「精一杯の思い」を託した。
一方、佐藤さんは、当初弟子を雇うことに消極的だった。しかし三浦さんの漁師になりたい熱意に打たれ「一人前に育てる」ことを決意する。
- 佐藤
- 「大輝を雇う時、戸惑いがあったのは確か。でも純粋にうれしかったよね。漁師がだんだん減って、まちが過疎化して行く中で、外から若い子たちが来て『俺らがやるよ』と言ってくれるのは、やっぱりうれしい。これも『縁』だしね」

2人は早朝から同じ船に乗る日々を重ね、徐々に信頼関係を築いていく。常に体当たりで挑戦と失敗を繰り返しつつも「へこたれずに」働く三浦さんを、佐藤さんは「かわいい自慢の弟子」だと笑う。
三浦さんが石巻に来て初めての誕生日には、佐藤さんや地域の漁師とその家族、FJのスタッフなどを巻き込んでの誕生日会が盛大に開かれた。
それから1年。24歳。漁師歴1.5年。三浦さんは日に焼けた肌と筋肉質の体格を手に入れた。そして、親方の背中を追ってたくましくも優しい海の男になっている。

「地域の一員に」新米漁師を迎え入れた地域にさし込む光
三浦さんが石巻に暮らし始めた当初、地域の住民は見慣れぬ「よそ者」に警戒心を抱いた。しかし浜で他の漁師の手伝いをしたり、大きな声であいさつする三浦さんの実直な姿をすっかり気に入り、笑顔で迎え入れてくれるようになった。最近では「若い人はいっぱい食べなきゃ」と三浦さん用の米が飲食店に用意されるほどだ。
石巻市雄勝町は人口が震災後4,300人から1,200人までに減ってしまった地区だ。漁業に支えられてきたまちは、人口の流出とともにまちを支える産業自体も衰退の一途をたどる運命にあった。
「漁業者として地域の一員に迎え入れたい」
三浦さんの准組合員資格の取得の裏側には、本人の努力、親方の熱意、地域の後押しがあった。突然現れた漁師志望の20代の若者の存在は、震災で傷ついた地域を照らすあたたかな光となっている。

彼らのように誰をも笑顔にする師弟の関係性は、担い手たちのまっすぐな漁師への憧れと、親方漁師たちの覚悟と人柄によるところが大きい。それと同時に、FJが担い手不足に悩む親方漁師と、漁師になりたい若者とをマッチングする過程を大切にしていることにも理由があるだろう。
- 鈴木
- 「ほとんどの漁師は家族単位で生計を成り立たせています。『他人様の息子』を雇うこと自体が挑戦であり、『革命』的な出来事なのです。その《初めての雇用》にチャレンジする漁師に寄り添い、弟子を迎え入れるサポートをすることが重要です」
このサポートに日夜徹しているのが、「漁師の女子マネ」と呼ばれるスタッフたちだ。ホテルでの接客や雑誌の編集の仕事など水産業とは縁のない業界から飛び込んできた女性スタッフであることも注目したい。

ひとりの若者の人生を決めてしまうかもしれない。
彼女たちは、親方となる漁師の人柄や浜のくらしが想像できるように、求人情報を掲載するまでに、何度も浜に通い取材を重ねているという。「ここで生きる」かもしれない若者のために、本格的に就業する前も後も、常に真正面から彼らと向き合うことで、信頼と愛情がつなぐ理想的な師弟コンビを生み出してきた。
漁師が暮らすシェアハウスを中心に生まれたコミュニティ
鈴木さんには、復興支援がきっかけで東北を訪れ、海の世界に興味を持ってくれる人がいても、「被災したまちには住む場所がない」という理由で引き止められなかった苦い経験もある。
この住む場所の確保という課題を解決したのが、空き家をリノベーションした漁師専用のシェアハウスだ。当初2軒から始まった「漁師専用シェアハウス」は、4年たったいま、宮城県内に6軒まで増え、10人の新人漁師たちが暮らしている。
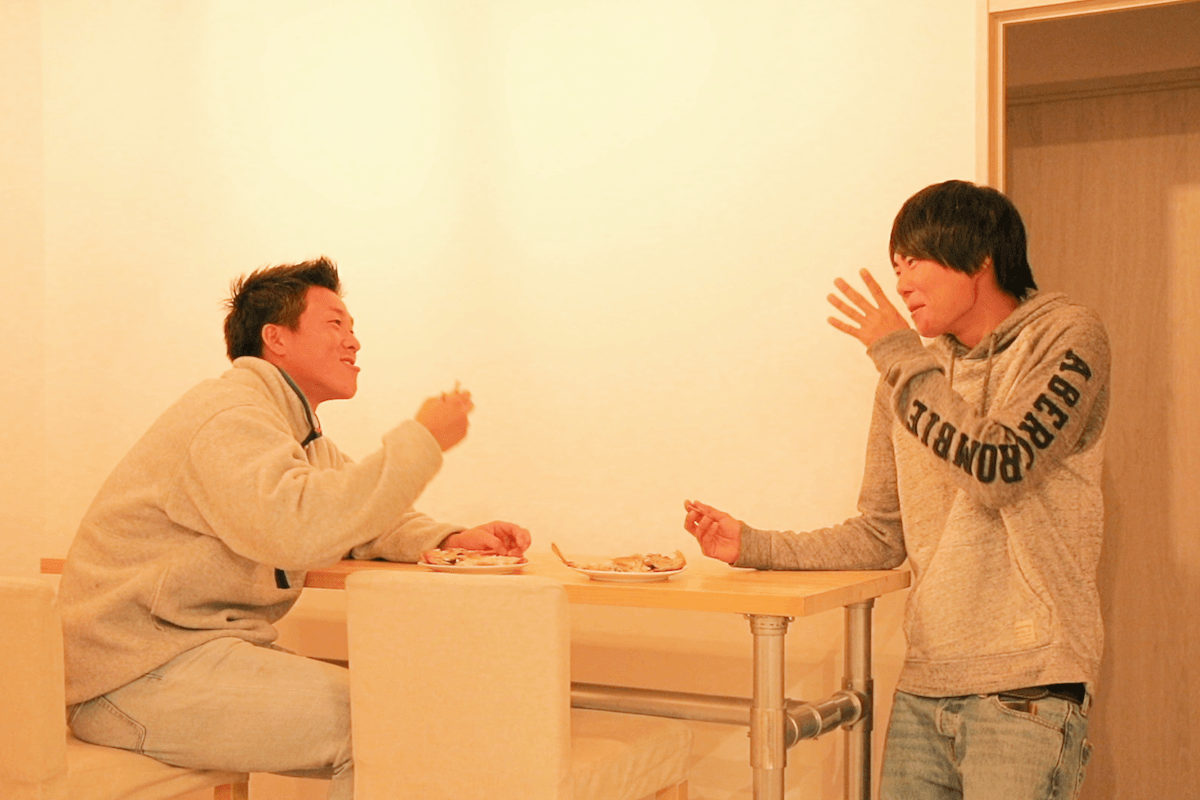
このシェアハウスでは、同じ年代の漁師たちが時々集まり、お互いが育てた海産物を交換したり、みんなで一緒にご飯を食べたりすることも。地域の人からの差し入れをつつく時もある。今までになかったコミュニティが、漁師を囲む世界に出来つつある。
- 鈴木
- 「新しく漁師になった若者たちは、厳しくも温かく見守る親方漁師やその周囲の人たちに支えられながら、ひたむきに海の仕事と向き合っています。漁師に憧れ、いきいきと働く若者が、東北の海にいるんです」

今動けば未来は変わる。みんなで動けば未来はもっと変わる。
漁業センサスによると、日本の漁師の数は年間6,000名から8,000名のペースで減少している。特に震災で多くの漁師が海を離れた東北では、このままのペースでは漁師を「増やす」どころか「減らさない」ことにもつながらない。もし奇跡的に100人も1,000人も漁師になりたい若者が増えたとしても、受け入れるベテラン漁師自体が足りず、そして高齢化とともにますます減っていく。
三陸の漁場は豊かだ。震災後、海の中ではなにごともなかったかのように魚が戻り、牡蠣やホヤなどの養殖棚をつるせば、その種は見事なまでに大きく育った。海が豊かさを取り戻しても、それを獲る人がいない。と、漁師たちは口をそろえて言う。

「俺たちの活動が、いつか自分の浜に返ってくるかもしれない。いま自分が動けば、いつか子どもの世代に返ってくるかもしれない。それを信じて活動してきました。
- 阿部
- 「漁師の力だけでは、漁師は増やせません。海の仕事がどれほど面白いか、その生き方がどれほどかっこいいか、その生の姿を突き詰め、発信する仲間が必要です。そして海からの思いを受け取り、一緒に考え、動いてくれる仲間が必要です」

漁師たちの思いで始めたTRITON PROJECTは、石巻市や宮城県漁協と連携した「事業」となり、日に日に仲間を増やして大きくなっていく。
昨年からFJは宮城県内だけでなく、北は利尻島、南は北九州まで、同じ思いをもつ漁業関係者と連携し、魚価向上のための魚のブランド化に向け、チームを組み動き出している。日本中の漁師たちが「俺たちも」と動き始めたのだ。
魚のブランド化で漁師たちの収入を安定させることもまた、水産業の担い手を増やし、未来へバトンをつなぐための挑戦だ。
水産業はチーム戦。
挑戦はますます加速していく。
フィッシャーマン・ジャパンの「TRITON PROJECT」は、関わるすべての人の力と、寄付をはじめとした支援のおかげで、ここまで来ることができた。東北の復興も進んでいる。しかし、解決すべき課題は残されている。被災の影響で経済的に困窮する子どもたち、人や地域とのつながりが失われたことにより長引くメンタルヘルスの問題......。
東日本だけではない。3年前には熊本地震が起こり、昨年は地震や水害も相次いだ。これらの地域にも、いまだに仮設住宅で暮らし、生活再建の見通しがつかない人たちもいる......。
全国には、まだまだ支援を必要としている人たちがいる。
3.11を機に、"いま、わたしができること"を考えてみてもらえると、うれしい。
\ さっそくアクションしよう /

「一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン」は、2024年までに三陸に多様な能力をもつ新しい職種「フィッシャーマン」を1000人増やすというビジョンを掲げ、新しい働き方の提案や業種を超えた関わりによって水産業に変革を起こすことを目指しています。




