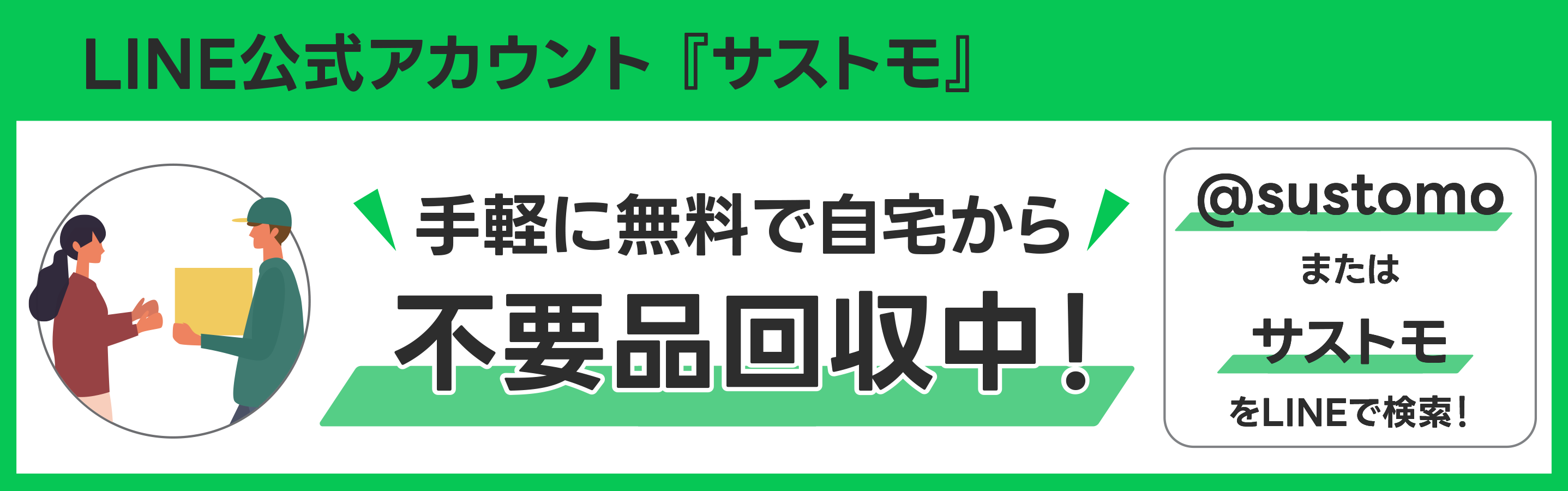世界初、自分の行動データが「収入源」に。ブラジルで実験開始

SNSやインターネットを使う度、私たちはデータにアクセスすると同時に、気づかぬうちに大量のデータを「提供」している。位置情報、買い物履歴、睡眠パターンに至るまで、その情報の多くは企業が利益を生むためのソースとなり、私たち自身には直接的な見返りがなく、むしろアルゴリズムなどで潜在顧客としてターゲットにされてしまう。
個人にもとづくデータは、本来、一人ひとりの資産ではないのか。
そんな問いに向き合い、新たな解を提示する実験がブラジルで始まる。2025年4月、国営IT企業・Dataprevは、個人が自らのデータを管理する権限を持ち、データの使用ライセンスを提供した場合にはその対価を得られる仕組みを設立すると発表した。データ評価や収益化を事業とする米企業・DrumWaveと協働する。全国規模で展開するのはこれが世界初となる見込みだ。
実験の主要ツールは、DrumWaveが提供するデジタルウォレット・dWalletだ。このプラットフォームが一人ひとりの「データ貯蓄口座」となり、ここに格納されるデータが商品となる。
プロトタイプの対象は、給与担保ローンの契約を持っている市民。彼らが新規ローンを契約する際に、契約内容の使用ライセンスを企業に提供するかどうかをオプトアウト式で選択する。使用が許可されたローン契約のデータは「データ貯蓄口座」に貯蓄され、企業や研究機関はそれを商品として入札。
入札のオファーに個人が合意すれば、取引が成立して個人のデジタルウォレットに入金される。これは普通のお金として使える通貨なので、入金後すぐに銀行口座に振り込むこともできるのだ。

個人の意思にもとづいたデータ利用は、人工知能言語モデル(LLM)などへの投資がもたらす利益を企業に留めず、個人の収益に広げることに繋がる。健康情報や公共交通の利用履歴など、さまざまな個人データが商品になりうるだろう。
また、マクロな視点で捉えると、dWalletの普及は「データ(デジタル)植民地主義」の解消に貢献する可能性がある。データ(デジタル)植民地主義とは、グローバルノース側の企業が、世界中のデータを収集しているものの主にグローバルノース社会への利益を創出していることから、グローバルサウスのデータ主権が損なわれる不均衡な状態を意味する(※1, 2)。個人のデータ主権が守られることで、この不均衡をならすこともできるはずだ。
特にブラジルでは、10人に3人(※3)が機能的非識字者(※4)であり、そのうち95%の人はデジタルスキルが不十分であるため(※5)、脆弱な立場にある人のデータが不当な価格で取引されることなどを予防する策も必要だ。
データは「21世紀の石油」とも言われる貴重な資源。そんな個人のデータが貨幣に近い価値を持つことは、新たな市場が生まれることでもある。この市場が健全であるためには、自分のデータを自分で管理できる権限が確固たるものでなくてはならない。そのルール作りをどう実現できるか、dWalletを含めた各地での探索を注視していきたい。
元記事はこちら
【参照サイト】Dataprev announces pioneering data property management initiative in partnership with Drumwave at Web Summit Rio
【参照サイト】Dataprev anuncia iniciativa pioneira de gestão de propriedade de dados em parceria com a Drumwave no Web Summit Rio|Dataprev
【参照サイト】In a world first, Brazilians will soon be able to sell their digital data|Rest of World
【参照サイト】Government-backed savings accounts could let Brazilians profit from their digital data|TrendWatching

仲原菜月(なかはら なつき)
大学在学中にスウェーデン・ウプサラ大学にて交換留学。大学1年次から難民支援や環境問題、ソーシャルビジネスに触れる。一般社団法人Social Innovation Japan / mymizuや一般社団法人Earth Company、上勝町内にてインターン。ウクライナ避難民の写真展「OnOurWayHome」を都内で開催。現在関心のあるテーマは、脱成長、紛争予防、自然観など。(この人が書いた記事の一覧)