日本文化が海外で盗用されたら? 文化の盗用の本質を小川さやかさんに聞く

近年、「文化の盗用」問題が世界的に注目されているのを知っているだろうか?
「文化の盗用」とは、ある文化圏の文化やアイデンティティの要素を、他の文化圏の人が私物化すること。
たとえば、数年前にアメリカのタレントが、自身の下着ブランドに日本の伝統的衣装である「着物」と同じ名前をつけたとき、「文化の盗用ではないか」といった議論が巻き起こった。
白人の著名人がドレッドヘア姿をSNS上にアップすることや、ハロウィンのコスプレでネイティブアメリカンの衣装やチャイナ服など伝統的な衣装を身にまとうことも、文化の盗用に当たるとされている。
それは、「かっこいいから」「かわいいから」を理由とした無邪気な行為のひとつでしかないのかもしれない。しかし、誰かを傷つけている可能性があるとしたら?
日本でも昨今は、人口減少危機の対応として外国人の受け入れを拡大したり、都市部では帰国子女がクラスにひとりはいるという多様な世の中が加速している。そんな社会に生きる今、私たちはこの「文化の盗用」問題にどう向き合っていくべきなのだろうか。
アフリカ・タンザニアでフィールドワークを続け、多様な文化を肌で感じている文化人類学者・小川さやかさんに、「文化の盗用」の本質的な問題点から私たちが意識すべきマインドセットまでを聞いた。

小川さやか(おがわ・さやか)
文化人類学者。立命館大学先端総合学術教授。1978年愛知県生まれ。大学院生だった2001年からタンザニアでフィールドワークを始める。国立民族学博物館機関研究員、同助教、立命館大学准教授などを経て現職。『都市を生きぬくための狡知』(世界思想社)で第33回サントリー学芸賞、『チョンキンマンションのボスは知っている』(春秋社)で第8回河合隼雄学芸賞、第51回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。ほかの著書に『「その日暮らし」の人類学』(光文社新書)などがある。
津波、広島、アイヌの人たち......。自分ごと化で見えてくる「無意識の差別」の実態
異なる文化圏の者がアフリカ系アメリカ人のドレッドヘアの真似をしたり、他の国の民族衣装をまとったりして、しばしば炎上の火種となる「文化の盗用」問題。
文化の盗用は必ずしも差別意識から生まれるわけではない。むしろ、「かっこいいから」といったカジュアルな感情や、ファッション感覚から生まれる、無意識の差別であることが多い。
それゆえに、文化の盗用の問題点を尋ねられても、いまいちピンと来ないのが正直なところだが、小川さんは「私たちの身の回りの話に置き換えてみたらよくわかると思います」と語りかける。

「海外の人が茶道や書道を習ったり、それを普段の生活に取り入れたりすることを多くの人々は問題に思いませんよね。むしろ、『私たちの文化を楽しんでくれているんだなぁ』とうれしく感じる人が多いんじゃないかと思います。
ですがたとえば、茶道が海外の映画で悪役によって怪しい儀式におもしろおかしく使われたりしたら、『そんな怪しいものでない』とショックを受ける人もいるかもしれない。
またもう少し身近な関係で考えてもいいと思います。私たち日本人の多くはアイヌ民族の方々と日本社会とのセンシティブな問題を知っていますよね。アイヌの民族衣装をまとって和太鼓を叩くようなお祭りを開催し、それをアイヌの人たちとの交流イベントではなく、さも日本文化のような見せ方をしたら、アイヌの人たちはそれまでの複雑な歴史や自文化をないがしろにされたと思うのではないでしょうか。
文化の盗用というのは、文脈を大きく変えられることによって盗用された側を傷つけてしまう行為なんです」

小川さんはさらに、日本人にとってセンシティブな物事を例に挙げ、文脈を大きく変えられることの"悲しみ"について語る。
「これは文化の盗用の例ではなく、文脈を無視された側の気持ちを想像するための比喩ですが、たとえば、海外で『フクシマ』や『ツナミ』という名前のお菓子やTシャツが単なるおもしろい商品として販売されたらどう思いますか?『いまだ苦しんでいる人がいるのに』と、悲しみや不快な気持ちを抱く人は多々いると思います。
誰かの苦しみや困難が続いていたり、誰かがアイデンティティとして大切にしているにも関わらず、その歴史的な背景や文脈を理解しないまま、その人たちの文化を使っていることが文化の盗用の問題だと思います」
どこまでが無意識の差別に当たるか。その線引きは問題の本質ではない

私たちが「文化の盗用」問題について考えるとき、どこからが該当し、どこまでが当てはまらないのかという線引きをつい求めてしまいがちだ。しかし、「問題の本質はそこではない」と小川さんは指摘する。
「学生たちから『アフリカの衣装を着た写真をSNSに挙げても文化の盗用になりませんか』と聞かれることがよくあります。無意識の差別によって批判されないようにしたいという気持ちはよくわかります。しかし本来私たちが目を向けるべきは、これをしたら文化の盗用になるか否かという線引きよりも『問題の原因となっていることは何か』であるはずです。
大事なことは、その国や社会に生きる人にとってセンシティブな問題が軽視されていること。そして、その原因となった文化や歴史がなかったかのように、当事者たちが置き去りのまま勝手に議論を進めることがいかに暴力的かを理解することだと思います」
たとえば、アフリカ系アメリカ人にとってのヘアスタイルは、奴隷制度や公民権運動といった政治的背景やアイデンティティが複雑に絡み合う、非常にセンシティブな問題だ。
小川さんは、『髪を装う女性たち―ガーナ都市部におけるジェンダーと女性の経済活動―』(織田雪世著/京都大学アフリカ地域研究資料センター)を用いて、こう説明する。
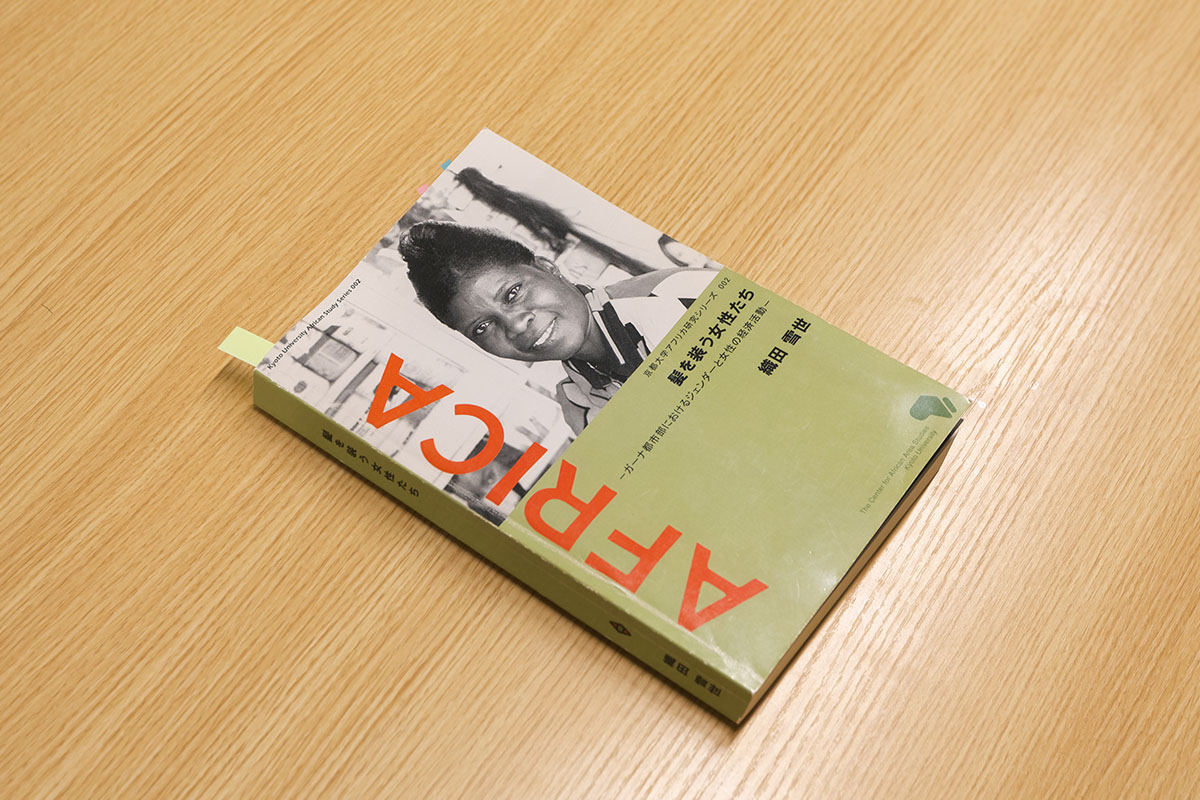
「アフリカの人々がアメリカに連れてこられた17世紀初頭、当時の白人たちは彼・彼女たちの細かくカールした髪の毛(縮毛)を劣ったものとして扱っていました。以降、奴隷制度下のアメリカでは肌の色と同様に、あるいはそれ以上に彼らの髪質は低い地位を特徴づけるものとなりました。同じ奴隷の中でも、肌の色が薄かったり、髪の毛のカールがゆるかったりすると、労働や食事、教育など優遇されることもあったと言います。
こうした中で、アフリカ系アメリカ人たち自身も、本来は称えるべき存在だったはずの髪のカール具合を基準とする優劣のつけ方を内面化します。男女ともに地肌や髪を傷つける壮絶な努力をして髪の毛を真っ直ぐに整えるようになります。それは1863年の奴隷解放宣言後も、白人社会で生き延びていくために継続していきます。以降も、直毛はモダンで魅力的だとされ、アフリカ系アメリカ人は自分の髪型に自信を持つことができないという感覚を抱かされ続けてきました」
1950年代後半になると、公民権の適応と人種差別の撤回を求めたアフリカ系アメリカ人公民権運動が起こる。
「公民権運動の中でアフリカ人の自然な美しさが叫ばれるようになり、髪を櫛で丁寧にとかすことで成形するアフロヘアが流行します。その過程で、ストレートヘアにするか、もともとのカールを生かした髪型にするかは、『民族主義者か』『白人迎合主義者か』という政治的な表明になっていくのです。それはアフリカ系アメリカ人自身にとっても大きな葛藤をもたらしました。好きな髪型をすると、それはファッションではなく、自身の政治的アイデンティティとして理解され、彼らが属するアフリカ系コミュニティとの関係を難しくする事態にもなったからです。
こうした奴隷制度や差別への抵抗、アイデンティティの政治など、アフリカ系アメリカ人のヘアスタイルの背景にある歴史は、アメリカ社会ではある程度知られています。自分たちは生まれ持った美しさを受け入れてもらうにも、好きな髪型をするにも葛藤しているのに、彼らを抑圧した側が『ファッションは個人の自由』とアフリカ系の人びとの髪型を真似したら、憤りが生まれるのは自然なことです」
キャンセルカルチャーと文化の盗用

昨今は、文化の盗用と見なされる発言をした個人が、キャンセルカルチャーによって社会から排除されることもよく見受けられる。
小さな声を拾えるようになったのはSNSの大きな効用ではあるものの、#(ハッシュタグ)をつけて、SNS上で意見を主張したり議論したりする社会運動『ハッシュタグ・アクティヴィズム』でも見られるように、その運動に興味関心がない人たちが失言をした当人を社会から引きずり下ろそうとする動きが活発に起きているのも事実。
「とくにSNSでは、差別的な表現を正すポリティカル・コレクトネスにより、むしろ問題の根本が議論されなくなりがち」と小川さんは指摘する。

そんな気運が漂う今、誰かがミスをしたら一発退場にするのではなく、それを切り口として世の中の課題や問題に目を向ける社会をつくるのが最も重要なことだと、小川さんは続ける。
「本当に大切なのは、その発言が意図的か否か、その人が差別的な人か否かを裁定することではなく、文化の盗用だという批判をきっかけに、どのような複雑な背景や文脈があったのか、なぜ今でもそれを軽視できないのかについて教えあったり、ともに考えたりすることではないでしょうか。
公共の面前で集中砲火を浴びてしまったら、なんとかして面目を保とうと防衛的になり、逃走したくなるのも心理的には理解できます。
発言や行為の是非が人生を左右する問題になると、批判と自己弁護や反論に終始しがちです。しかし文化の盗用のような問題は、盗用された側の当事者の意見も一枚岩ではないし、即時的な正解を決めるのは難しいです。それよりも『アフリカ系アメリカ人の歴史についてはこの本が読みやすいよ』と教えあうなど、背景や文脈についての理解を深め、しばらく考える時間を与えあう方がいいと思います。その方が当事者にとってもこの先の社会にとっても、実りあることではないでしょうか」
わかりあえない中でも、当事者と一緒に考えながら生きていく

一方、異なる文化圏で生きているからこそ、ほかの国の文化や歴史を理解するのは極めて難しい。
「人類学者として常々思うのは、人々が紡いできた文化なんてそう簡単にはわからないということ。他者を理解している、あるいは理解できるという幻想は暴力的でもあり、捨てた方がいいと思います。
そもそも他者とコミュニーションを取る際、傷つけ合う可能性をゼロにすることは不可能で、どんな方法を取ってもそれは必ず起こりうる。ですが、だからといって他者とのかかわり自体を諦めてしまうのも違う。文化の盗用問題の"その先"につながりませんから」
世の中に蔓延する「地雷を踏まないこと」を最優先とした価値観。小川さんは、その意識を少しずつ変えていく必要があると訴える。

「文化の盗用問題について語ろうとすると、『そもそも異文化をマネしなければいい』という人が出てくるかもしれません。しかし、こうした『地雷を踏まなければいい』という考え方では、異文化そのものに対する理解も深まらない。
異社会で人類学の調査をするとき、想像さえしていなかったことで現地の人々を傷つけたり、不快にさせたりすることは多々あります。気を遣ったつもりが、逆に怒らせることも。その時に私がまずすることは意味がわからなくても、とりあえず謝ったり、その場を取り繕ったりすることです。それで、しばらく関係を深めてから、改めて私は異なる文化を生きており、あの時に何が問題になったのかがいまいち理解できないとさりげなく相談します。聞いても納得できない時はまたしばらく放置して、ゆっくり理解の糸口を探します。もやもやするけれど、『この人は私とは違う価値観の人間だ』と片付けてしまうと、相互理解はそこで止まってしまいます。現地の人々の生活状況や文化的文脈、抱えている問題が少しずつわかってくると、相手の意見や感情を了解できるようになることも多々あります。相手の方が私がなぜ理解できないかを理解し、わかりあえなくても上手に付きあっていく方途を教えてくれることもあります。
こうしたプロセスには時間がかかるかもしれませんが、アフリカ系アメリカ人のヘアスタイルについて私たちは永遠に議論したいわけでも、あれもこれも文化の盗用だと規定することで地雷だらけになった社会をつくりたいわけでもないはずです。それよりも、アフリカ系アメリカ人に対する過去の問題や現在まで続く人種差別が本当の意味で乗り越えられ、『文化の盗用だ』と当事者が必死に叫ばなくても、誰もがファッションを楽しめる社会を築きたいわけですよね。そのためにはまず恐れずに関わり、文化の盗用が起きた背景や文脈を学ぶしかないと思います」
人の考え方も世界のあり方も、一気に変えることはできない。差別や偏見は当然なくすべきだが、何が差別に当たるかよりも、差別的だと感じる人たちが抱える問題から、ともに議論しあう時間と空間が必要だ。

-
取材・文 船橋麻貴
Instagram:funabashimaki
編集 くいしん
X(旧Twitter):@Quishin
Facebook: takuya.ohkawa.9
Web: https://quishin.com/
撮影 翼、
X(旧Twitter):@na283be
Instagram:na283be




