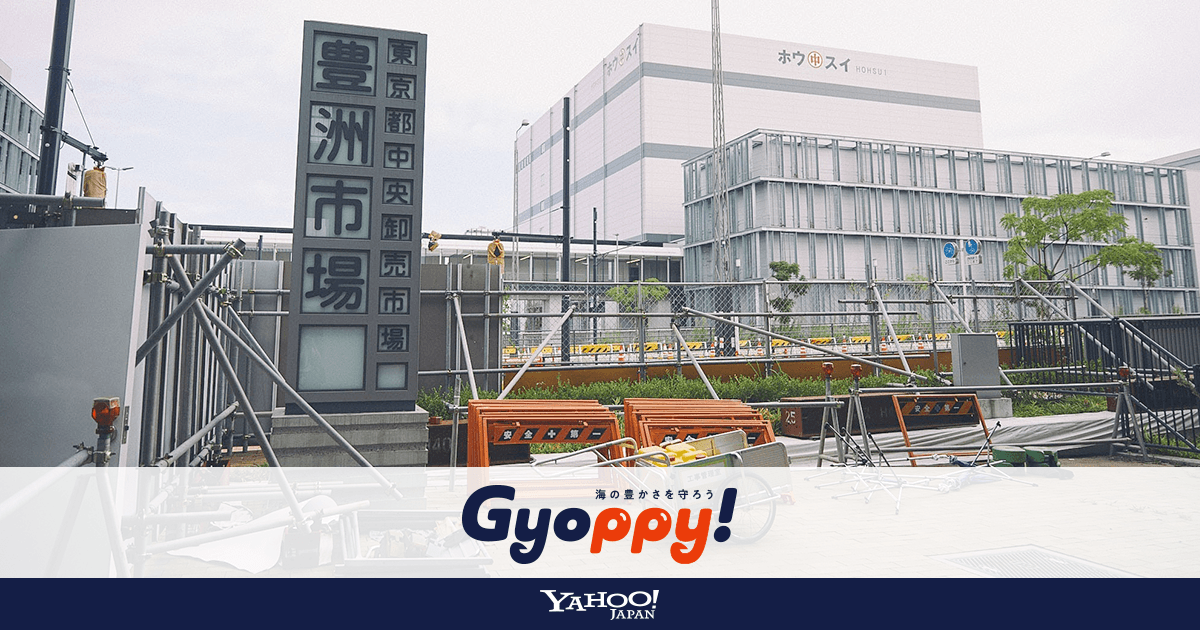豊洲を''魚食文化都市に''!? もったいない日本の漁業を変える「モッタイFISH(仮)」プロジェクトとは

2018年10月、日本の漁業は大きなターニング・ポイントを迎えた。
豊洲新市場、開場。
これまで「日本の台所」として漁業の中心を担ってきた旧築地市場が閉鎖し、その約1.7倍の面積を誇る豊洲への移転が開始されたのだ。
移転に関してはさまざまなメリット・デメリットが挙げられ、賛否両論といったところだ。とはいえ、それが私たちの食卓にどのような影響を与えるかということまでは、消費者にとってはわかりづらい。
しかし一方で、日本の漁業は大きな衰退期を迎えていると言われている。漁師人口の高齢化や、海外と比較して「持続可能な漁業」の整備が遅れているなど、さまざまな問題も挙げられている。
この大きな変化をキッカケに、起こせるアクションはないのだろうか。
たしかに消費者という立場では、仮に魚食を控えたとしても、生産や流通に関しては手の打ちようがない。とすればこのまま、そう遠くない未来に魚が食べられなくなる日を、なんとなく迎えるしかないのだろうか。
「豊洲モッタイFISH(仮)」プロジェクト
現状を変えるべく、動き始めた人たちがいる。
「豊洲を、日本の魚食文化都市にしたい」
そんなビジョンを熱を込めて語るのは、東京海洋大学准教授・勝川俊雄氏だ。

勝川氏は長年、水産資源の持続的利用について取り組んでいる。つまり魚や貝を未来に残しながらおいしく食べていく方法を模索するため、「資源管理」の研究を続けてきた第一人者だ。
それに加え書籍の執筆、さらには自ら世界の漁業の現場に赴くなど、消費者に向けた「日本の漁業の危機」の発信も行っている。すべては「未来につながる漁業の実現」という、一貫した信念による活動だ。
今回、そんな勝川氏が立ち上げようとしている新たな漁業プロジェクトのキックオフイベントを取材するため、豊洲へと向かった。
その名も「豊洲モッタイFISH(仮)」。

2018年10月に築地市場から移転した、豊洲市場。いわば、築地の次なる日本漁業の中心地。
そこには生産者、流通業者、場合によっては消費者まで、漁業に関わるあらゆる人が集まることになる。
勝川氏はこの地で、「漁業者と消費者をつなげ、魚の価値を伝える仕組み」をつくりたいという。

市場移転前に開かれた今回のイベントには、そんな豊洲の未来を先取りするかのように、漁師や仲卸業者、飲食店経営者、近隣住民、メディア関係者といった面々が参加した。イベント前半では、移転が予定されている実際の建物内を見学。

後半は、最寄りの会議室に集合。プロジェクトのビジョンや日本の漁業の現状について、生産、流通、消費それぞれの立場から意見を発表した。
日本漁業の節目を機に、勝川氏が描く豊洲の未来の姿とは?
プロジェクトのネーミングにも込めた、日本の漁業の「モッタイなさ」とは?
本記事では、勝川氏がプロジェクトにかける思いを語った、イベント後半の模様を中心に記録していきたい。

がんばっている漁業関係者を"消費者が"応援する仕組みづくり
「豊洲モッタイFISH」プロジェクトとは、一言で表すと「日本の中でも持続可能な漁業に向けてがんばっている漁業関係者を、"消費者が"応援する仕組みをつくること」であると、勝川氏は言う。
冒頭でも触れたように、日本は「持続可能な漁業」に対する現場の意識がなかなか高まらない状況にあると言われている。
そもそも、1970年代から排他的経済水域(※1)によって各国の漁業できるエリアが限定されて以来、世界の漁業は「いかに自国の排他的経済水域の資源から持続的に利益を引き出すか」という方向にシフトしていった。にもかかわらず日本は「とにかくたくさん獲る」という従来の方式のまま、限られた自国の海域内での過剰漁獲によって水産資源を減少させているというのだ。
(※1= そこにある水産資源や海底鉱物資源を、沿岸の国だけが利用できると決められたエリアのこと。それまでは世界中の海で魚を獲ることができたため、遠い海まで航行できる漁船の性能や効率的な漁獲技術がポイントだったが、これ以降、限られた範囲内でいかに漁業を持続させるかを考える必要が出てきた)

- 勝川
- 日本の漁業は世界屈指のポテンシャルを持っています。排他的経済水域の広さは世界第6位で、その中に世界屈指の好漁場があります。適切な漁獲規制をすれば、良質な水産物を安定供給できます。また、世界からリスペクトされる魚食文化があるので、魚の価値を伸ばすことも可能です。日本の漁業は、世界一ともいえるポテンシャルを持っているのです。しかし、現状ではポテンシャルを発揮できずに、漁業を衰退させている。実に「もったいない」ことです!
- 勝川
- 漁業のもったいなさを解消するには、消費者も含めて、魚の食べ方を変えていかないといけないと考えるからです。日本人と魚の関係は戦後70年で大きく変わりました。昭和の時代は肉がぜい沢品で、日常の食事は魚でした。けれど、排他的経済位水域が定められるようになってからは漁獲量が減り、魚の価格も上がっています。結果、最近では魚のほうが肉よりも少し高い。
であれば本来、これまでのように「場当たり的に獲って市場に並べる」という漁業ではなく、「しっかりと魚の価値を伝えて、魚を選んでもらう」という漁業にしていくべきなんです。
それにもかかわらず今の日本の水産業は、商品だけが流通して情報が流れていかない仕組みになっています。だから、魚の価値を伝えることができていないんですね。
そういった現実がある中で、量販店は薄利多売を続け、かたや消費者は魚が減っているということも知らずに「魚をたくさん食べることが漁業のためになる」という風に、刷り込まれてしまっているんです。つまり、漁獲・流通・消費の全てが持続可能性を無視して、乱獲・乱売・乱食という負のサイクルに陥っているんです。
しかし、そんな生産現場の危機を目にしてきたはずの勝川氏が、なぜ"消費者"に着目するようになったのだろうか。
どうやら問題は、生産者の「獲りすぎ」だけにあるのではないらしい。いわば「魚が売れて当たり前」だった時代に成り立っていた流通販売体制、そして消費者の意識、つまり水産業に関わる仕組み全体が、古いままなのだ。

- 勝川
-
こういう話を知ると、多くの消費者が問題意識を持ってくれて、「私たち消費者にも何かできることはありますか?」と聞いてくださります。しかし残念ながら、「今すぐできることはありません」と答えるしかないんです。
たとえば欧米の市場では、持続可能と認められた魚にはエコラベルが貼られているので、消費者はそれを目印に商品を選べば持続的な漁業に協力することができます。でも、日本ではそういった制度は広まっていない。
単純に考えれば日本も同じ制度を導入すればいいことになる。
しかし残念ながら、日本で同じ制度を導入するのは困難です。もちろん、私もつくろうと計画したことはあるのですが、かなり厳しかったです。というのも、これは実際に私の研究室で調査したことですが、国連などで定められた国際スタンダードに照らすと、日本の水産物のほとんどは持続可能と認めることができないんです。
日本の漁業が衰退していく一方、欧米諸国は政府主導で漁獲制限を行い、持続可能な漁業の開発に成功している。漁獲規制によって、魚が増えている国も少なくない。しかし、日本の水産物には持続可能と認められるものがほとんどないので、無理に欧米のスタンダードを導入しても、消費者は持続可能な漁業に協力できないのだ。協力するとしても、それは国産の魚介類をほとんど食べないことになってしまう。
現状を打開するには、日本国内で、良い取り組みをしている生産者を、消費者が応援する独自の仕組みを造る必要がある、ということだ。

そこで勝川氏が考えたのが、生産者と消費者を直接つなぐということ。心強いことに、漁業者の中には「持続可能な漁業」に取り組む意識が高い漁師たちがいる。
それら一部漁業者と消費者をつなげ、価値を伝える仕組みをつくること。それがこの「豊洲モッタイFISH」プロジェクトの目的だ。
- 勝川
- 日本の中でがんばっている漁業者を消費者が応援して、伸ばして、増やしていく。そんな仕組みを、ここ豊洲を拠点に、つくっていきたいんです。
"豊洲"という、強み
生産者と消費者をつなぐ仕組みをつくる。言葉で表すとシンプルだが、全国に膨大な数のプレーヤーがいる漁業界において、生産から消費までを一気に結びつける仕組みをつくるのは、決して簡単なことではなかったそうだ。
そこで、まずは小規模な取り組みから始めようというのが、勝川氏の考えだ。具体的には、豊洲市場に信頼できるプレーヤーを集め、自分たちで理想のモデルをつくってしまおうというのだ。一つの地域だけで成功を収め、いずれ全国に魚の価値を伝えていく作戦である。

そしてそれは豊洲市場だからこそ成し遂げられると、勝川氏は語る。その根拠には豊洲という環境が持つ、さまざまな強みがあった。
- 勝川
-
今回、豊洲市場への移転が決まって、漁業関係者内部でも新しいことを始めようっていう機運がすごく高まっているんです。豊洲市場という大きな箱ができた以上、そこで新しいことをやろうと。やはりきっかけがないと、新しいことって始めにくいですからね。絶好のタイミングだと思います。
実際問題、豊洲市場はロジスティクス(物流システム)が非常に組みやすいというメリットがあります。中央卸売市場にはあらゆる漁港から水産物が届くインフラが既に存在するので、生産者と消費者を、物理的につなげる仕組みがとてもつくりやすいんです。
ここで重要なのが、市場には、魚のことを知り尽くした人材が豊富にいるということ。消費者を巻き込むためには、「面白い! 楽しい!」と思ってもらえるよう、食材の知識や歴史といった情緒的価値を伝えることが必要です。
その点で豊洲は、さまざまな魚種について、詳しい知識を持ったプロが働く場所。もはや日本で一番水産物の知識が集まる場所といってもいいくらいですから、消費者をひきつけるような魚の知識を消費者に提供することができるんです。
そして何より欠かせない要素が、消費者の存在です。築地市場の周りにはあまり人が住んでいないので、「地域住民」という感覚がなかった。でも豊洲にはそれがある。
市場の周りには、タワーマンションが林立し、四万人近い人が住んでいる。経済的な余裕がある子育て世代の方も多くいらっしゃいますから、「子どもたちのためにも、未来につながる魚を残そう」という形で、共感を集めることができると思うんです。

築地に代わる、新たな漁業の中心地となる豊洲だからこそ、価値を伝える仕組みがつくれる。そして何より肝心な、「受け手」の存在。これらがそろうことで初めて、消費者を巻き込んだ形での漁業が実現するのだ。
「もったいない」を軸に、生産から消費まで、ひとつにつながる
しかし、消費者へのメッセージが「サステナブル(持続可能)」のままでは、広く一般層まで広がっていくことは考えにくい。これは当の勝川氏が、10年の活動を通して実感してきたことでもあるという。

そこで登場するのが「もったいない」というキーワードだ。
- 勝川
-
「もったいない」って、子どもの頃からいろいろなところで聞いている言葉なので、すっと頭に入って来やすいと思うんです。
加えて「サステナブル」ともすごく相性がいい。だって、"もったいないこと"をひとつひとつ無くしていけば、それが持続可能性につながりますからね。例えば「魚が卵を産む前に獲ったらもったいないよね」「10年後にうなぎが食べられなくなったらもったいないよね」という形で、わかりやすくサステナブルを伝えていくことができるんです。
「もったいない」には、「サステナブル」を超える強みがあります。それは「味の保証」にもつながるということ。
サステナブルは味とは無関係です。資源が持続できるならまずくてもOKということになりかねないのですが、「もったいない」は単に持続性だけで無く、価値を引き出しているかどうかも問われます。つまり、「本当はおいしい魚なのに、マズい食べ方をしたらもったいないよね」という風に伝えることができるんです。環境のためであっても、おいしくなければ消費者はついて来てくれませんから、これは大きな強みであると思います。 - 勝川
-
最低限、「乱獲されていないこと」「適切な時期に漁獲されていること」「適切な調理がされていること」「生産者が特定できること」の4つを「モッタイFISH」のスタンダードとして定めようと考えています。
基準自体は欧米の「サステナブル」ほど厳しいものではありませんが、満たさないものはどんなにおいしくても認めない、と徹底させることで、日本の漁業の持続性を自信を持って見せていける形にしたいと考えています。
「未来につながる漁業」のためには、価値の持続・最大化というふたつの要素が欠かせない。ともすると小難しくなりがちなこれらの概念を、感覚的に、子どもでもわかるように表せる言葉。それが「"モッタイ"ない」なのだ。
日本人になじみやすいワードを中心にしたことで、プロジェクトの未来は動き出す。具体的にはまず、海外で定められた「サステナブル」に代わる日本独自の認定基準を、「モッタイFISH」の条件として決めることが必要だと、勝川氏は言う。
安全とおいしさを保証するための基準。これを現在の日本でも実現できる範囲内で徹底することで、欧米の基準を導入せずとも、無理なく「もったいない」を実践していけるという考えだ。

そしてこれらの条件を満たした魚を「モッタイFISH」として認定し、地域の消費者に価値を伝えていく。その上で重要なのは「生産者と消費者のコミュニケーション」なのだと勝川氏は言う。
- 勝川
-
地域の消費者に「モッタイFISH」を伝えるために、イベント運営、そして店舗の二つで進めていこうと考えています。
イベントでは月ごとにテーマとなる魚を決め、その魚を獲る上での工夫や思いなど、背景となるストーリーを生産者から消費者へ直接紹介していくつもりです。やっぱり食べ物はある意味で、自分をつくる原材料だと思うんです。いずれ自分の体になっていくものを、誰が、どんな思いでつくっているのか。それを直接聞くのって、すごくおもしろいですよ。
イベント後は、紹介された魚を扱っているお店へ食べにいってもらいます。あらかじめ生産者の話を直接聞いてもらっているから、お店で食べるとき、その人の顔を思い出してもらうことができるんです。これによって、生産現場と消費者の距離が縮まっていくと考えています。
生産者の思いを直接聞き、それから実際に魚を食べにいく。
筆者はこれまで魚を食べる際、おいしさや新鮮さや価格といった単なる「商品」としての情報にしか目を向けていなかった。しかし勝川氏の考えるこのプロジェクトなら、「魚を食べる」という行為がひとつの"文化的な体験"になっていきそうだ。これはさまざまな食の選択肢がある現在の社会の中で、大きな付加価値になっていくだろう。

もちろん生産者と消費者が直接つながるというスタイルは、一般にはそう簡単に実現できるものではない。これは新市場の設備と人材、そして経済的に比較的余裕があり、かつ食の安全性への関心が高い近隣消費者という豊洲の備える利点があって、初めて成り立つプロジェクトなのだ。
- 勝川
-
生産者と消費者を直接つなげて、まずはサポーターになってもらう。その上で、サポートできる場所、つまり実際に食べられる場所も用意する。魚を獲る人、流通、調理する人、食べる人、みんなが同じ目標でつながって、ひとつのプラットフォームで活動する。豊洲はそれをつくるのに、非常に適した環境なんです。
生産者から消費者まで、力を合わせて未来につながるおいしい魚を育て、食べ続ける。豊洲を、そんな魚食文化都市にしていけたらと思っています。
おわりに

日本は古くから、豊かな魚食文化を育んできた。
それは、周りを海に囲まれ、近海に好漁場を持つという環境の中、人々が自然と対話してきた証なのかもしれない。
魚は、自然から与えられた資源だ。土地を開拓して生み出された野菜や畜産物とは違い、魚は自然の持つ限りある総量から、分けてもらっているものだ。獲る人も食べる人も、自然に負担をかけ過ぎないよう、現在だけでなく未来にも意識を向ける必要がある。
その上で私たち消費者にできることは、まず、「知ること」。そして「応援すること」ではないだろうか。
「豊洲モッタイFISH」プロジェクトはそれを実践していくための、重要なモデルケースになるだろう。
-
文たくよ
-
写真八木 咲