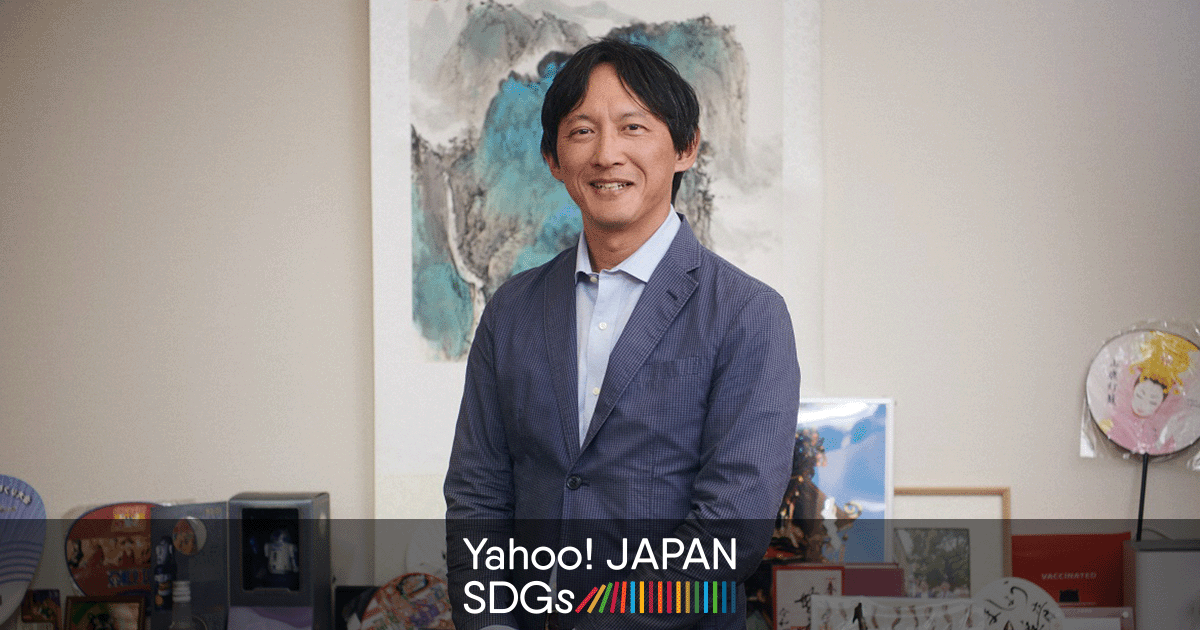自己への執着を捨て期待値を超えていく。打算のない挑戦が人も社会も成長させる。 #豊かな未来を創る人

2012年から8年間熊本県の副知事として務めた後、現在は衆議院議員として働く小野泰輔さん(東京7区)。
熊本県政時代は、ご当地キャラ「くまモン」の著作権無料化による県の経済活性化、若手農業経営者の育成などに取り組んできました。任期終了後に、東京都知事選に出馬。無名の新人ながら、約3週間で約61万票を集めて注目が集まりました。
そして今、国政の現場から社会の変革に挑む小野さん。どの環境においても、その挑戦を支えてきたのは、学生時代の恩師からもらったある言葉でした。社会やそこに生きる人々が抱える課題に、どのような姿勢で向き合ってきたのか。一人の政治家として、一人の人として大切にしてきた想いを伺いました。
小野泰輔(おの・たいすけ)
日本維新の会
1974年、東京都生まれ。1999年、東京大学法学部卒業。アクセンチュア株式会社、衆議院議員公設秘書(自由党・藤島正之氏)、明豊ファシリティワークス株式会社を経て、2008年に大学時代の恩師である蒲島知事に請われ熊本県政策調整参与へ転職。4年後に副知事に就任。「くまモン」の商標フリー化や川辺ダム建設問題、県南振興、阿蘇地域世界農業遺産登録などに関わる。2020年に任期終了後、東京都知事選挙に出馬し、約3週間で約61万票の支持を得た。2021年10月、第49回衆議院議員選挙にて初当選。趣味は三線(琉球民謡)、テニス、ゴルフ、ドライブ、日本酒、琉磨焼酎、泡盛。三児の父。
直観に従って飛び込んだ熊本県政
幼い頃から政治に関心や憧れがあったものの、自分が現実に政治家になるとは考えていなかったと、小野さんは振り返ります。
「家族や友人からは、『昔からお前、総理になる!とか言ってたぞ』と周囲に言われるんですが、僕自身はまったく記憶がないんです(笑)。
ただ、小学生の頃から歴史の伝記を読むのが好きでした。そこから感じたのは、誰が政治における意思決定をするかによって、世の中が平和になることもあれば、戦火に巻き込まれることもあるということ。政治というのは、人が生きることに直結する大事なものなんだなと、幼心に感じていました」
大学では政治学を学び、コンサルティング会社に就職。その後、2社目の企業に勤めていた頃、政治の道に入る転機が訪れます。大学時代の恩師、蒲島郁夫教授が熊本県知事に就任し、県政の仕事を手伝ってほしいと言われました。
「大学では、蒲島先生の政治学のゼミにはまっていました。そのゼミの最終課題は、学生が研究結果をまとめて共同で出版すること。僕は、これを完成させるために、1年留年したんです。それほど研究に熱中していましたね。ゼミの仲間たちが卒業していくのを見送りながら、渾身の分厚い一冊を完成させた思い出があります(笑)。
そのときの恩師の選挙戦ということで、有給をとってサポートしに行ったところ、当選後に先生から、『熊本で一緒にやらないか』と電話がかかってきたんです。蒲島郁夫という人と仕事をすれば、きっと面白いはず。そんなわくわくした直感がありました」
それから2週間後には会社を辞め、寝袋一つ抱えて東京から熊本に移った小野さん。最初の4年間は政策調整参与・政策参与として働いた後、当時全国最年少だった38歳で、副知事に就任します。

どの環境でも仕事の本質は変わらない
熊本県副知事としての8年間の任期中は、ご当地キャラ「くまモン」の著作権無料化、全国の若手農業経営者育成のモデルともなった「くまもと農業経営塾」の立ち上げ、県南の企業誘致による地域振興をはじめ、新たな取り組みを行ってきました。
中でも、「くまモン」の著作権無料化では、県がキャラクターの著作権を買い取り、県の許可を得た事業者や個人であれば、誰でも無料でイラストを使用できる仕組みを小野さんが提案。その結果、県内の中小企業やクリエイターが次々と関連グッズを販売し、それらの売上累計が8000億円を超える経済効果につながったと小野さんは語ります。
「当時ゆるキャラというのは、著作権を自治体が持っていて、自治体のパンフレットやノベルティーにしか使われないのが一般的でした。
ですがくまモンは、職員たちがSNS拡散やメディア露出に一生懸命トライしたおかげで認知度が上がり、全国で愛される存在になりつつあったんです。だからこそ、それを県内の企業が無料で使って商品化できれば売上が伸び、県の経済が元気になる。その分税収も増えて、県民のみなさんに還元できると考えたんです。
そこにある課題に対してできることをあらゆる角度から考え抜いたからこそ、これまでの枠組みにとらわれない、新たな手段で成果が出せました」

民間企業を経て県政に携わる中で、改めて仕事の本質はどの環境においても変わらないと感じたと小野さんは話します。
「民間でも行政でも、やることは同じなんです。それはつまり、『どこに課題があるのかを見つけて解決する』ということ。企業ではクライアント、行政では県民が何に困っているのか。それを見つけて、どのような手法と手順で解決するのか、自分の頭で考える。それが、仕事の本質だと思っています。
県政時代は、課題を見つけて解決するために、徹底的に現場に足を運び、自分の目と耳であらゆる情報を集めるようにしていました。そうして複眼的に物事を捉えることで、マルかバツの二択で思考停止をせず、より多くの人にとっての幸福を最大化できる新たな道を模索してきたつもりです」

打算のない情熱は伝播する
コロナ禍の2020年7月、小野さんは2期務めた熊本県副知事の任期が終わるタイミングで、東京都知事選挙に出馬。無名の新人が約3週間の選挙期間で約61万票を集めたことで、注目が集まりました。
それまでのライフステージで出会ったさまざまな人たちがサポートしてくれたという選挙戦。一人でも挑戦すると心に決めていた小野さんの強い想いが、周囲に伝播していきました。
「当時、現職の知事を始めとした顔ぶれだけでは、有権者にとって選択肢が少なすぎるのではと考えていました。東京では無名だったので、始めから負け戦だと言われましたが、ここで東京や日本のこれからを、この国に暮らすみんなできちんと議論せずに選挙が終わってしまうことに、相当な危機感を感じていたんです。
『そうだ、都知事選に出よう』というCMのコピーのような言葉が突然降ってきて、やはりここでも直感で選挙に出ることに決めました。何の打算もなく、ただただ自分の問題意識を大切にして、信じる道を進んでみようと思ったんです。
すると『あいつが挑戦するんだったら協力しよう』と言ってくれる人たちが、一人また一人と出てきてくれたんです。熊本で出馬会見を開いた当初、選挙戦の手伝いを依頼した友人は3人だけでした。そこから、それを見ていた現在の所属政党から推薦の声がかかり、さらに熊本の地域振興などで交流した若者たちが、東京の選挙事務所に連日集まって選挙活動を引っ張ってくれたんです。気づけば、550名ものボランティアの方々が共に戦ってくれました。

『選挙は人生の棚卸し』という言葉が政治の世界にはあります。今までの人生で関わってきた人たちが、手を差し伸べてくれるのか、無関心でいるのか、敵対するのか。そのどれかであるわけですが、このときたくさんの方が応援してくださったことは、身に染みて嬉しかったです。
振り返ると熊本時代では、厳しいことを言ってくる人に対しても、逃げずに向き合うことを心がけてきました。そして、もし相手の話が不当だと思ったら、行政の立場であっても正直に反論する。そうやって誠実に相手に向き合うことが、人間同士の信頼につながると信じてきました。そうして積み重ねてきたつながりが、新たな挑戦の背中を押してくれたことを実感しました」
都知事選の結果は4位で落選。その後、2021年10月の衆議院議員選挙に出馬をして初当選。現在は、国政の現場で課題解決に取り組んでいます。
「衆議院議員選挙に出馬した当時、僕が所属している日本維新の会は、まったく浸透しておらず、当選する可能性は正直極めて低いと思っていました。それでも国政に挑戦する意義を強く感じたんです。
というのもそれまで僕自身、社会に出てからこの国の成長を実感したことが一度もなかった。それはバブル崩壊後、今の政権が高度経済成長期から続く経済や社会の構造を変革してこなかったことが原因だと考えていました。だからこそ、日本維新の会でそれを再構築し、さまざまな社会的背景を持つ人たちが各々の道にチャレンジできる世の中を創っていきたい。そう考えて選挙に挑みました。その想いは今も変わっていません」

期待値を正しく汲み取り、超えていく
一人の政治家として、一人の人間として、小野さんが長年大切にしてきた恩師の言葉があると言います。
「学生の頃、蒲島先生からもらった言葉、それは『期待値を超えろ』でした。人が誰かに仕事をお願いするときは、必ず何かしらの期待値を設定しています。それを超える仕事ができた人には、次はもっと難易度の高い大きな仕事が与えられる。一方、そうでなければ、次から仕事は任せてもらえない。つまり期待値をいかに超えていけるかどうかが、その人の成長を決めるのです。
もちろんずっと期待値を超え続けることは難しいですが、少なくともいつもそこを目指して努力を積み重ねていくことで、人はステップアップしていける。だからこそ、僕はそれをずっと心にとめてきました」
そのためには、まず「期待値がどこにあるのか」を正しく把握することが重要だと語る小野さん。何をすれば相手が満足した状態になるのか、それをきちんと洞察して汲み取る力が大切だと話します。
「相手の求めていることを理解する感受性や想像力を育むために鍵となるのは、自分への執着から離れることです。自分が相手からどう見られ、どう評価されているのか。そこにばかりフォーカスしていると、自分を認めてもらうことが目的化する。そうすると、相手に媚びへつらったり自分が出過ぎたり、課題解決のためのアウトプットが疎かになってしまいます。
かく言う僕自身も、幼い頃から人の目を気にする神経質なところがあって、劣等感から生まれる自己承認欲求も当然ありました。ですが、それを変えてくれたのは学生時代から一緒にいる妻でした。
彼女は昔から誰にでもフラットに接していて、いつも友人に囲まれている人でした。悩みがあるのかと尋ねても『ないよ!』とカラッと笑う姿を間近で見ていると、自分の悩みというのは、結局自分をよく見せたいという執着から来るものだとわかったんです。
大事なのは、目の前の人や物事に集中すること。そう気づいてから、行動も変わっていきました。自分の意識がどこに向かっているのか、常に客観的に見つめるメタ認知が、どんな仕事においても大切なのだと思います」

挑戦をあきらめない社会を
前を向いて挑戦すれば、より良い世界を創っていける。それを次世代が当たり前に信じられる世界を、この先小野さんは目指しています。
「残念ながら今の社会には、人から期待してもらうことがあっても、『どうせ自分にはできない』というあきらめやニヒリズムのようなものが漂っていると感じます。挑戦を拒みたくなる背景には、個人の問題だけでなく、これまで長く続いてきた社会の閉塞感があると僕は考えています。
日本は今、『失われた三十年』の状態が依然続いていて、GDPの順位を見ても国の勢いは明らかに下り坂。人口もこれから減っていく。先の見えない社会を、政治の力で変えていきたい。そのために、教育はもちろん、エネルギー分野をはじめとした持続可能な産業政策など、具体的に取り組むべきことはたくさんあります。現場では、それらの課題解決に共に挑む若い仲間がたくさんいます。この先は、そうした次の世代がどんどん挑戦をしていけるよう、橋渡しの役割を担っていきたい。そして僕自身も、自分に求められていることを正しくキャッチしながら、課題を解決するための新たな挑戦をいつも続けていたいです」
挑戦の根底にあるのは、どんなときも「人に喜んでもらいたい」というシンプルな思いだと小野さんは語ります。
「学生の頃から、生徒会長ではなく、修学旅行や林間学校の実行委員のような役割が好きで(笑)。大学のゼミで行った伊豆旅行でも、行先の情報や当日のタイムテーブルをまとめたロジブックを作ったりしていたんです。
やっぱり自分が楽しいことをする。そして人を楽しくさせる。勉強以外にも、そういうことが大事だと僕は考えていて。それを仕事においても追求していくと、求められていることを突き詰めて考え、高い熱量を持って行動できるのではと思います。
誰かに期待をしてもらえること。そしてそれに全力で応えて喜んでもらえること。それはこの先どのような環境で仕事をしたとしても、僕自身にとって揺らぐことのない喜びです」

-
取材・文木村和歌菜
写真西田優太