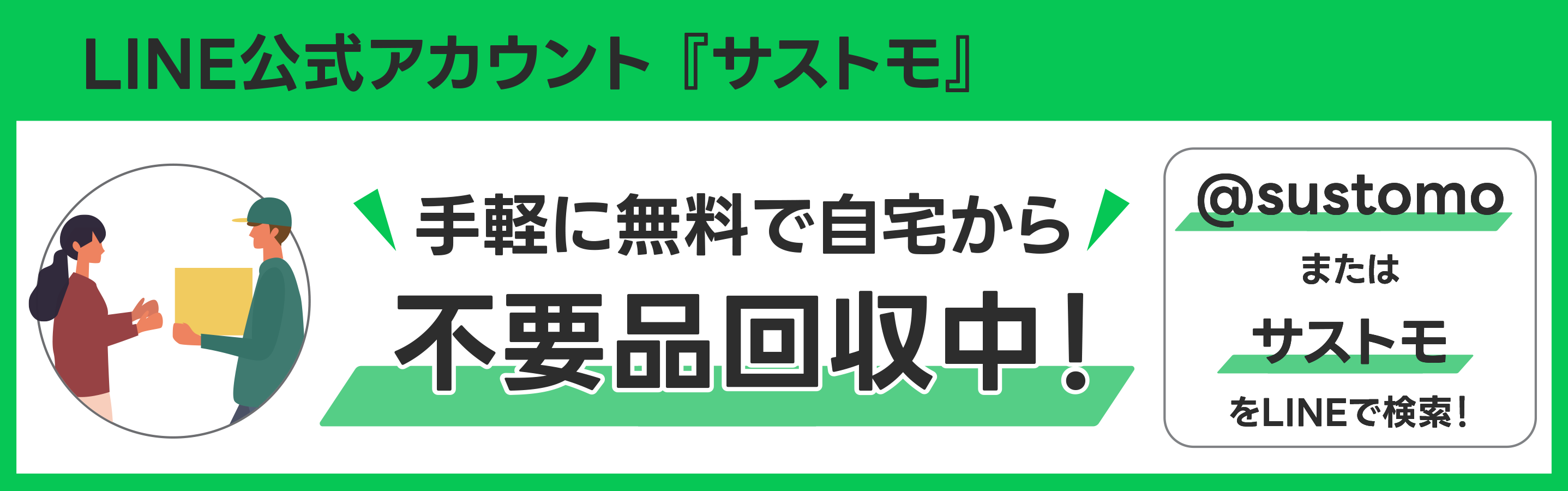「サッカーがあるから日本で生きていける」――祖国を離れ30年、在日ミャンマー人の「父」になった男

日本で暮らすミャンマー人たちのサッカーチーム「MFC Tokyo」。監督のハンセインさん(54)は元プロ選手だが、民主化運動の弾圧を機に日本へと逃れてきた難民だ。それからずっと、日本で暮らすミャンマー人の心をサッカーを通じて支えてきた。在日ミャンマー人の「父」とも慕われる、ハンセインさんの人生に迫った。(ジャーナリスト・室橋裕和/撮影・菊地健志/Yahoo!ニュース 特集編集部)
真夏の日緬「異文化交流マッチ」
8月16日。猛烈な暑さとなった神奈川県横浜市の「かもめパーク」で、キックオフのホイッスルが鳴った。素早くパスを回して前線にボールを送ろうとしているのは、ミャンマーの若者たち。彼らは日本に住むミャンマー人で結成されたサッカーチーム「Myanmar Football Club Tokyo(MFC Tokyo)」だ。

「どうにか、いい試合になればね」
ベンチで戦況を見守っているのは、監督のハンセインさんだ。ミャンマーでプロ選手として活躍し、来日後は20年にわたりMFC Tokyoを率いてきた。

一方、対戦相手の鎌倉インターナショナルFCは、現在神奈川県社会人リーグ2部。将来的にはJ1昇格を目標としているだけに、実力はMFC Tokyoをだいぶ上回っているようだ。終始ボールを支配し続けて、先制点を挙げた。
すかさず拍手が湧き起こったのは、MFC Tokyoのベンチだった。下を向かず、どんどん攻めていこうという意思だろうか。応援に押されるように、相手サイドに切り込んでいく。
「ミャンマーの選手たち、技術もあるし、なかなか強いと思いますよ」
そう語るのは、鎌倉インターナショナルFCの指揮を執る、サテライト監督の石井久和さんだ。

「それに気持ちも入っている。だからこういう親善試合にしては当たりも強いですが、そんなこともこちらの若い日本人選手にはいい経験になります」(石井さん)
直後、さらに2点目が追加される。たまらず、ハンセインさんが自らピッチに立つも、試合はそのまま0-2で終わった。
「もっと大差がついちゃうかと思ったけど、がんばったよね」
そう言うハンセインさんも晴れやかだ。
「本当だったらこれから、両チームで打ち上げをしたいんですが」
石井さんは残念そうだ。新型コロナウイルスの感染が収まらないいま、試合後の交流もなかなか難しい
それでも、と鎌倉インターナショナルFCのトップ監督、武田航平さんは言う。
「国や文化が違っても、パスをひとつ交換するだけでコミュニケーションできるのがサッカーです。違う国同士の試合となると、はじめはなんだかぎこちないですが、ひとつのボールを追ったあとは風景がぜんぜん違ったりするものです」

プロ選手として活躍するも、軍事政権の弾圧ですべてが終わる
ハンセインさんは、かつて国を追われた難民だった。
「男4人兄弟の3番目なんですが、みんなサッカーをやってましたね」
宗主国だったイギリスの影響もあり、ミャンマーではサッカーは国民的なスポーツだ。ヤンゴンの下町で生まれたハンセインさんも小さなころから自然とサッカーボールに親しむようになり、やがて期待の選手として頭角を現す。高校時代には全国大会に出場したことから注目されて、卒業後はすぐにプロとして契約した。1984年のことだ。所属チームは「港湾局」。
「あのころのミャンマーは社会主義で、サッカーリーグも省庁主体だったんです。軍や税務署など12のチームでリーグが行われていました」

だからハンセインさんは国家公務員でもあったわけだが、同時に名門ヤンゴン大学に進学した大学生でもあった。「三足のわらじ」を履く充実した青春は、しかし1988年に「すべてが流された」。
軍事政権に反対するデモが各地で激化し、政府は弾圧を強めた。5人以上での集まりが禁止になったことからサッカーリーグも中止となり、大学は閉鎖。活動の場を失ったハンセインさんも学生たちと民主化を求めて声を上げたが、軍は市民に銃口を向けて運動を鎮圧する。たくさんの若者が血を流し、そして海外へと逃れた。欧米へ亡命する仲間が多かったが、ハンセインさんは日本を選んだ。
「同じ仏教国で、顔立ちも似ているし、親近感があるでしょう」
1990年にはじめて日本へやってきた。時間はかかったが難民として認定され、それから異国での生活が始まった。飲食店で働きながら日本語学校に通い、必死に言葉を覚えた。

ミャンマー難民が集う高田馬場でチーム結成
MFC Tokyoの「ホーム」は1000~1500人ほどのミャンマー人が集住する東京・高田馬場だ。「リトル・ヤンゴン」とも呼ばれている。
チームの誕生は、偶然がきっかけだった。
「ミャンマーのリーグにいたプロ選手と、高田馬場でばったり会ったんです。彼も難民として日本に逃げてきていました。飲みにいって意気投合して、それならチームをつくろうと決めたんです」

ハンセインさんも、異国で生きていくにはなにか、仕事のほかに心の支えが必要だと実感するようになっていたころだった。
こうして2000年に、MFC Tokyoが生まれた。同じような境遇のミャンマー人が少しずつ集まり、やがて落合中央公園での週末練習が習慣になった。
選手たちの先生であり、お父さん
飲食店を経て日本語力を磨いたハンセインさんは現在、日本の法律事務所で働いている。ミャンマー人の在留資格などについての翻訳や通訳を行う傍ら、同郷の人たちの支援にも精を出す。
まだ日本語のおぼつかない人に頼まれて役所の手続きに同行したり、体調が悪いと聞けば病院へと一緒に出かけたり。銀行口座の開き方がわからないと連絡があればすぐに向かう。

本人は「自分たちが若いころも、大変だったから」と言葉少なに謙遜するが、キャプテンのミン・ヌエ・ウー(31)さんは言う。
「いちばん簡単な言葉で言うと、偉い人。これだけ、自分の時間を人のために使っている人はいません」
留学生でゴールキーパーのヒンダー・チャンさん(24)も「ハンさんは、先生でお父さん」なのだと言う。
日本に住む外国人の立場はさまざまだが、MFC Tokyoも同様だ。家族で定住して働いている人もいれば、留学生もいる。政治的な事情を抱えて難民として申請をしている人もいる。留学を終えてそろそろ帰国しようと思ったら、コロナ禍でアルバイトが減り生活が苦しい留学生も多い。故郷の家族に仕送りができずもどかしい思いを抱えている選手もいる。
日本は便利で、安全な国。選手の誰もがそう口をそろえる。しかし、ミャンマー人独特の遠慮深さからか、はっきりとは言わないが、どうも働いている先で同僚や客の日本人から見下されて傷つくこともあるようだ。
「どの国も同じ。いい人も、悪い人もいるからね」
ある選手はそう言うが、そんなストレスもサッカーが忘れさせてくれる。

あえて在日外国人チームと戦う、鎌倉インターナショナルFC
MFC Tokyoに、鎌倉インターナショナルFCが声をかけたのは今年5月のことだ。2018年に設立したばかりの若いチームだが、当初から海外展開を視野に入れている。オーナーの四方健太郎さん(42)はこう語る。
「グローバルツールであるサッカーを使って、国を超えた交流やビジネスを生み出していく。そんなコンセプトのチームがJ1まで駆け上がっていったら、きっと異色の存在になると思うんです」
シンガポール在住の四方さんは、アジアへのマーケティングを軸のひとつに据えたチームづくりを目指している。そのため設立当初からアジア遠征を繰り返し、一方でサテライトを中心に地道な国際交流も続ける。在日外国人チームとの「異文化交流マッチ」もその一環だ。
「うちはまだまだ知られていないチームです。それを日本にも海外にも、どう発信していこうかと考えたときに、やはりチームと世界をつなげてくれる人材が必要だと感じたんです。その懸け橋になってくれる存在が、在日外国人ではないかと」
そんな発想からまず在日ベトナム人チームと試合を行い、次はアイルランド人主体のチームと戦った。そして3試合目の対戦相手が、MFC Tokyoだった。

田坂公我選手(20)が振り返る。
「環境に恵まれた僕たちに比べれば、ミャンマーの選手たちはいろいろと苦労していると思うんです。でも最後まであきらめずに、それも楽しそうにプレーしていましたよね」
青木悠弥選手(22)も言う。
「海外を目指すうえでも、こういう国際交流試合は続けたいですね」
青木選手はもともと今ごろ、モンゴルリーグでプレーしているはずだったが、コロナ禍で渡航できずにいる。彼のように、海外を経験してステップアップしていこうという選手も鎌倉インターナショナルFCには集まっている。だから親善試合であっても、外国人チームと戦うことは大きな経験になる。
互いのチームにとって、格好の試合だったのだ。

30年間、一度も帰国しない理由
試合から1週間後の夜、高田馬場のミャンマー料理店「ルビー」でハンセインさんたちの「同窓会」が開かれた。
「久しぶりだよね、ハンセインさん。いっつも若い人たちの面倒とサッカーばっかりでさ。忘れられちゃったかと思ったよ」
日本語で軽口をたたきながら入ってきたのはチョウチョウ・リンさん(59)だ。
「コロナで会えない日がずっと続いていたからね」
「ルビー」の店主チョウチョウ・ソーさん(57)もそう言って笑う。ふたりとも、あの「1988年」をきっかけに日本へと逃れてきた難民だ。それからずっとこの国で暮らし、年齢を重ねてきた。3人はいかにも使い込まれた達者な日本語を話す。そこに長年の苦労がにじむ。

「リトル・ヤンゴン」のミャンマー人たちもずいぶんと世代が変わった。民主化が進んだこともあり、政治的な事情を抱えて逃げてきた人は減った。明るい未来をつかむために日本を選んだ留学生が主役だ。MFC Tokyoの選手にもそんな若者が増えてきている。
ミャンマーへ戻る難民も多くなってきた。生活の拠点は日本に置きながら、一時帰国する人もたくさんいる。それでもハンセインさんは、来日してから30年、一度も故郷の土を踏んでいない。
「自分たちの目指した民主化とは違うんです」
2011年に民政へと移管され、2015年には民主化のシンボルでもあったアウンサンスーチー氏の率いる国民民主連盟(NLD)が総選挙で大勝利を収めたが、いまだ軍の影響力は大きい。国会の議席の25%を軍に与えるという憲法は改正できていない。軍閥が経済も握るという図式もそのままだ。イスラム系の少数民族であるロヒンギャに対する弾圧や、少数民族との融和が進んでいないことも国際的な非難を浴びている。
「いまのミャンマーには、まだ帰りたくない」
そんな複雑な気持ちを抱えながら、30年間この異国で生きてきた。
「君らがまだ生まれていないときから、僕は日本にいるんだよってよく冗談で言うんです。そんな若い子たちと、この異国で出会って、ミャンマー語で話して、一緒にサッカーをしている。それがなんだか不思議だし、楽しいよね」
いくらか酔ってきたハンセインさんが笑う。
「ずっと、このチームを守っていければと思っています。異国暮らしの支えになる場所、仲間に出会える場所として」
この週末もまた、チームは落合中央公園に集まって、ひとつのボールを追いかけるのだろう。

室橋裕和(むろはし・ひろかず)
1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイ・バンコクに10年在住。帰国後はアジア専門の記者・編集者として活動。取材テーマは「アジアに生きる日本人、日本に生きるアジア人」。現在は日本最大の多国籍タウン、新大久保に暮らす。おもな著書は『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(辰巳出版)、『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』(晶文社)、『バンコクドリーム 「Gダイアリー」編集部青春記』(イースト・プレス)、『おとなの青春旅行』(講談社現代新書、共編著)など。
元記事は こちら
ジャーナリスト室橋裕和
撮影菊地健志