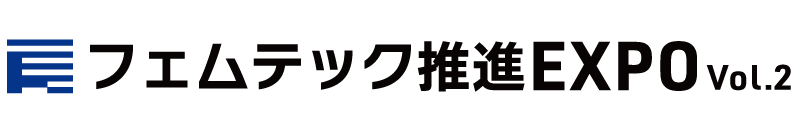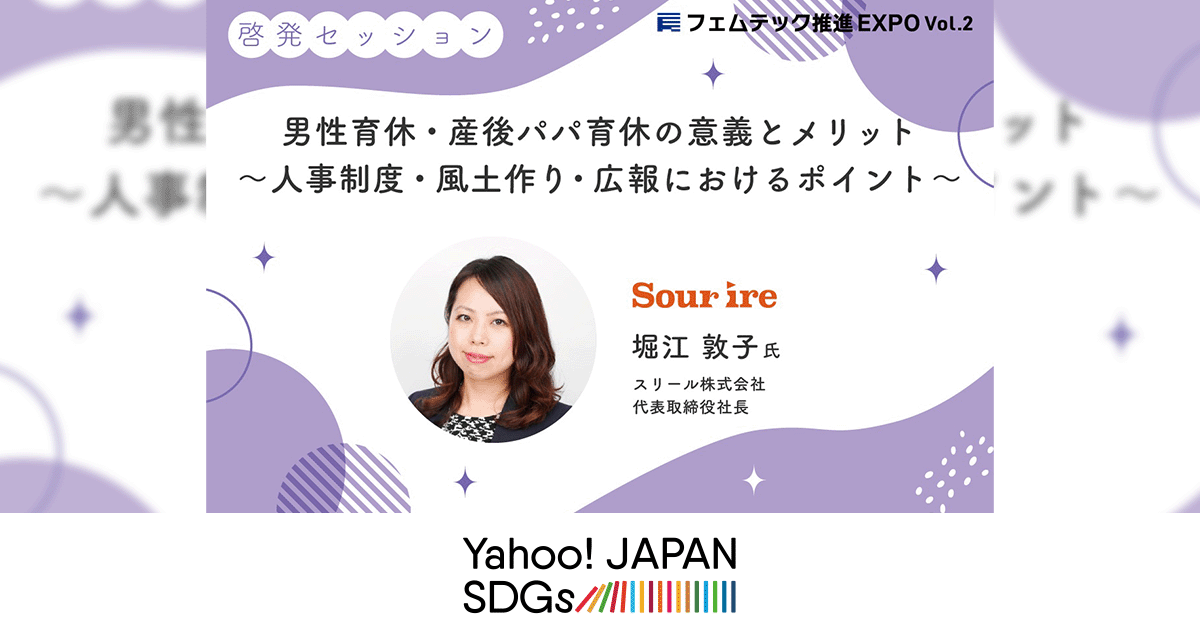男性育休・産後パパ育休の意義とメリット〜人事制度・風土作り・広報におけるポイント〜
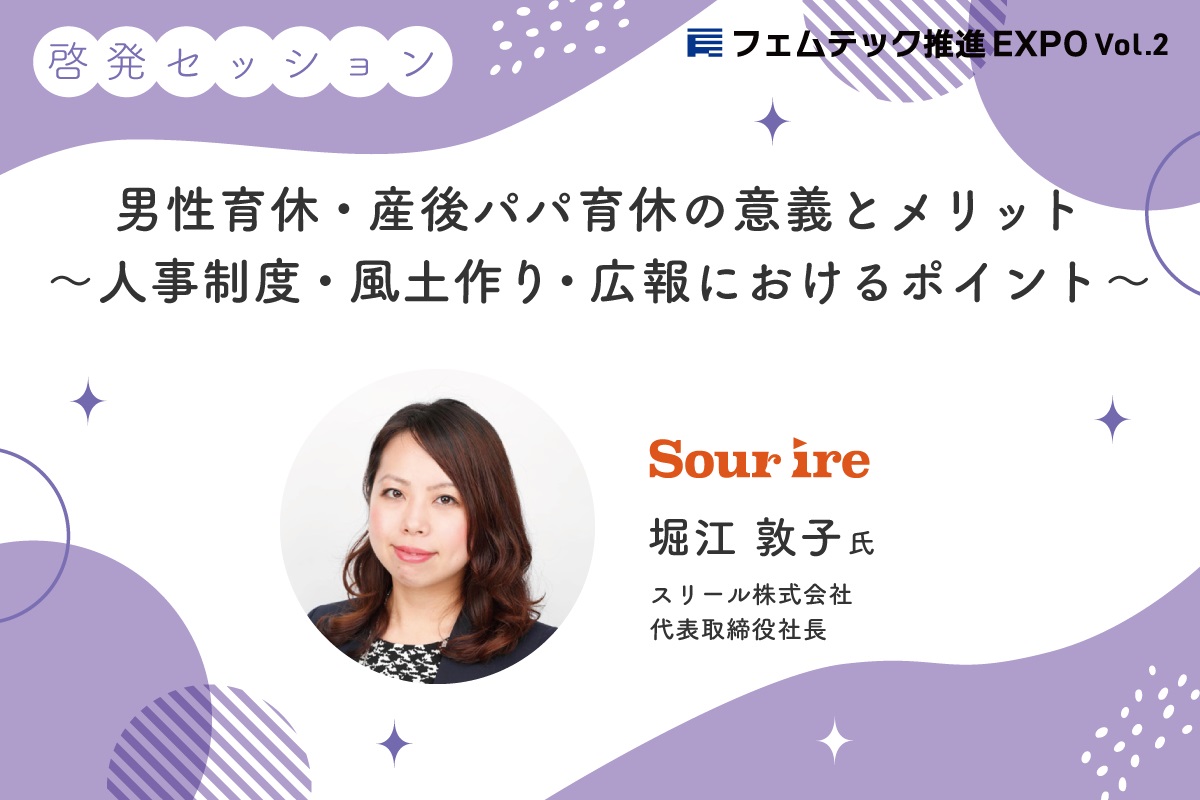

スリール株式会社 代表取締役社長 堀江 敦子
https://sourire-heart.com/
2010年スリールを起業。法人向けのダイバーシティ推進研修・コンサルティング、行政・大学向けのキャリア教育を展開する。内閣府男女共同参画会議専門委員など行政委員を多数経験。著書:『新・ワーママ入門』(Discover21)
動画URL
https://online-event.dmm.com/main/page/femtech2210/venue/schedule_detail.php?uid=631fd34c97559
スリールのミッション
皆さま、こんにちは。
この度は、「男性育休・産後パパ育休の意義とメリット〜人事制度・風土作り・広報におけるポイント〜」ということで、スリール株式会社代表の堀江からお話をさせていただきたいと思います。
弊社スリール株式会社は、2010年立ち上がりました人材育成の会社でございまして、女性活躍やダイバーシティの研修やコンサルティングを企業様向けに行っております。また弊社は社会課題を解決していくソーシャルビジネスでございますので、私も経営を行いながらさまざまな行政の任を務めております。内閣府男女共同参画局の専門委員や、厚労省イクメンプロジェクトなどを務めております。
そして現在、人的資本のコンサルティングだったり、また人材育成や組織開発についての経営学修士なども持っておりますので、人的資本全体についてもお話をさせていただくことが増えております。
弊社スリールは、「女性活躍から始めるサスティナブル経営の支援」をテーマに、大学生や若手社員、育児中やマネージャーさんまで幅広く研修をおこなっております。
社員一人一人のキャリア自立を促していくような研修、またマネージャーの方々が多様な人材をマネージメントできるような支援というのをおこなっております。
弊社がメインで行っているのが、体験型のプログラムです。
仕事と育児を体験する「両立体験プログラム(育ボスブートキャンプ)」というのを主軸に置いて、管理職の方に育児体験を行ってもらうというものを実施しております。これは会社を17時に退社してもらって育児体験をしてもらうというもので、これによって働き方の意識を変えていったり、多様なメンバーがどういった状況にあるのかを理解し、マネジメントに生かしていただく、そういったプログラムになっております。
こういった疑似体験ワークを取り入れた実践的な研修ですので、1日の研修であっても、コンサルティングにおいても、現場の声を生かしたコンサルテーションをおこなっております。
2022年4月〜「改正育児・介護休業法」順次施行
さて、今回のテーマである「男性育休の義務化」についてです。2022年4月から、改正育児・介護休業法が順次施行となりました。また今年の10月から「産後パパ育休」が施行になります。これはどういったものかというと、子供が産まれて8週間、2ヶ月の間に1ヶ月の育休が取得でき、さらにそれが2回に分割ができるというものになります。
また1歳までの育休も2回分割でとれるということになりますので、男性の場合は最大で4回取れるようになっています。
数が多くなり、かなり複雑になっておりますため、人事やマネージャーの方も悩まれている方もあるかと思います。
人事の方がやらなければならないことについてご説明いたします。今回の法制度によって、やるべきことが大きく4つございます。
まず「制度の説明・体制の整備」、そして「啓発・研修」「雇用環境の整備」、最後に「取得状況の公表」です。
こういったことを、もうすでに4月から整え始めてらっしゃるかと思うんですが、2022年10月からはいよいよ産後パパ育休が開始されますので、たくさん育休を取得される方が予想されます。これに向けての準備ができているのかというところですね。今日は確認していただきたいと思っております。
とはいえ、そんなことを言われても「属人的な仕事が多いので、1人抜けると仕事が止まっちゃうよ」とか、「チームワークで回せる仕組みが整っていないので、そもそも休みをとれる体制ではない」とか、または「仕事から離れる期間に、社員の心も離れていくのでは?と心配」などが、声として挙がっております。そういった心配、とてもよくわかります。
ただですね、皆さん。この状況がずっと続いていいのでしょうか? コロナだったり介護、そういったものもある中で、「誰かが抜けたら困る」、そういった組織でいいのでしょうか?
今回の男性育休をチャンスにしていって、組織変革をおこなっていただきたい、そのように思っております。
男性育休を推し進める最大のメリットとして、多くの多様な人材の社員が活躍できるような土壌を作れるということなんですね。
それはなぜかというと、育児期の社員が活躍できるために、労働環境面を整えていくこと、風土面を整えていくこと、この2つを整えていくことが必要になるからなんです。これらを整えていくことで、介護だったり育児だったり、またそれ以外の方々も活躍できる、そういった土壌を作っていくことができるんです。
1か月の男性育休取得率100%の積水ハウスの事例
とはいえ、男性育休の推進が風土醸成において本当に成果を出しているかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここで、有名な会社さんである積水ハウスの事例をご紹介いたします。
積水ハウスさんは、1ヶ月の男性育休の取得100%なんです。企業側が1ヶ月間育児休暇を取ることを義務化されたんです。それによって「男性育休1ヶ月はデメリットなし」と、社長さんもおっしゃっていらっしゃいます。
これは単純に育休を取ったからすごくよかったというわけではないんですね。やはり仕組みというところが大切になります。
今回、積水ハウス様が業務引き継ぎシートということで、育休に入る前にちゃんと引き継ぎをできるようにシートを作ったりですとか、あとは家族の方とミーティングをして、育休をどんなふうに取っていくのかを話し合っていく、そういったシートを導入されました。
このことによって、もちろん職場の中で働き方の改善が促進されたということと、取得された男性社員の98.3%が幸福度を感じている、という結果が出ています。そしてクライアントからも「家族を大事する会社から家を買いたい」と称賛の声が届いたということがありました。
このように、推進をしていくことによって個人にとっても会社にとってもメリットがあるという実例があるんですが、とはいえ推進していくことを、なかなか踏み切れない会社さんもあるかなと思います。
ですので、今回は「調査から見える男性育休のメリット」をご説明したいと思います。皆さんにはこのデータを持ち帰っていただいて、生かしていただきたいと思っております。
調査から見える「男性育休のメリット」
1つ目は「社員のエンゲージメント&ロイヤリティアップ」、2つ目が「採用面において、優秀な人材へのPR」、3つ目が「脱・属人か組織」、4つ目が「生産性が高い働き方にシフト」というこの4つのメリットが挙げられます。こちらに関してお話しをしていきます。
まずは、メリットの1つ目、「社員のエンゲージメント&ロイヤリティアップ」について。
調査によると、男性育休の取得経験がある人のほうが、「仕事にポジティブに取り組んでいるか」という質問に対して「YES」と回答した人が16.7ポイントも多かったんです。なぜ育休を取ったのに、仕事にポジティブに取り組めるのか。
その一つの例として、パーソル総研の「はたらく幸せ実感とワークエンゲージメント」という調査結果をご紹介します。働く人の幸せ因子として「リフレッシュ」「チームワーク」「自己裁量」などいくつかある中で、男性で育休を取ったことによって「リフレッシュ」が高まると。そして、自分が抜けても大丈夫な状況というのを実証していただくこと「チームワーク」も高まる、それいよって、ワークエンゲージメントの元になる働く幸せ実感というのが向上します。そしてさらに仕事をもうちょっとがんばろうだったり、この組織に貢献しようという気持ちが生まれて、それがパフォーマンスだったり、組織のパフォーマンスにつながる、ということになってきます。
なので、仕事でチームワークが発揮できるようになり、プライベートの充実という環境になり、それが幸せの実感を生んで、最終的にはエンゲージメントやパフォーマンスにつながっていくということなんですね。
さらには、育休を取ったことで組織にもポジティブな変化が起きたという調査結果もございます。
「男性が育休を取った時に、組織に対してどんな影響があったか」という質問の回答として、「男性の育児休暇に対する理解が深まった」「ライフスタイル、働き方について見直すきっかけになった」、そして「職場の中で仕事の進め方について話し合ったり見つめ直すきっかけになった」というスコアが高くなっています。このスコアは男性育休取得を歓迎した職場ほど、より高く表れています。
このように、実は個人にも組織にも影響があるということが見てとれます。
次にメリットの2つ目、「採用面においての優秀な人材のPR」について。
今現在、就活層の中で「男性育休を取得している、推進している企業を選びたいか」という質問に対して「YES」が77.5%。女性より男性のほうがスコアが高いという傾向がありました。そして「取り組みができていない会社をどう思うか」という質問には、「世の中の動きに対して遅れていると思う」とか、「経営者の考えが古そう」などのネガティブな印象が出てきており、先進的な考えを持っている人ほど、こういったことを受け入れているということが考えられると思います。
そしてメリットの3つ目、「脱属人化の組織」について。
今回、積水ハウスの社員の方に聞いたところ、65%が「職場でのポジティブな変化を実感している」という結果でした。
「これまでの仕事のやり方を見直した」ということで、生産性の向上を実感された方が多かったり、「女性が活躍できる組織へと変化している」との回答が目立っていました。
最後、メリットの4つ目、「生産性が高い働き方にシフト」について。
「育休取得は、生産性向上にも役立つ思うか」という直接的な質問に対して、「YES」と答えた方が6割を超えています。さらに20代では8割の方が生産性向上に役立つと回答しています。
このように、男性育休を取ることは、個人に対しても組織に対してもメリットが高まっていくということが見てとれたかと思います。
これらの成果を出すには
どういった仕組みが重要なのでしょうか。職場と家庭という両面を考える必要があります。
職場から見ると、面談の中で育休に入る前に自分がどんなキャリアを描いていきたいか、また育休中にどんなことを家庭の中でやっていきたいと考えているのか、そしてその後のキャリアをどう考えているのか、ということを上司と話し合うシートだったり、しっかりと業務の引き継ぎをやることによって、属人化を防いでいくことを仕組み化していくと。
また、「取るだけ育休」にならないように、家庭の中で家事分担などどうしていくのかをしっかりと仕組みとして持っていくということですね。
そういったことを促すためにも、本人向けの研修を行なっていくことも有効な手かと思います。基礎的な知識だったり、実際に取られた人がどんなふうに実施をしてきたか、そしてキャリアについて見直すきっかけにもなってくるので、しっかりとキャリアビジョンについても考えていくといった研修を行なっていくとよいかと思います。
研修を行うことによって、育休を突然取られて職場が大変になってしまうといったことがないようにやっていくことも必要になります。
また、管理職自身の理解を深めたり、多様な状況下にある部下のマネジメントを学んでもらうためにも"管理職向け"の研修も行っていくと良いかと思います。
制度の説明が義務化になっていますし、面談のポイントというのも必要になってきます。何よりもチームで働いていく働き方に変えていかないと、男性育休はなかなか取ることができませんし、会社の中でも属人化していくことになりますので、チーム内の働き方改善といったところもできるような研修をしていくことも重要になってきます。
こういったことを進めていくために、人事の方が施策を行うだけではなく、経営陣の方が啓発していくことが重要です。これは個人にとっても社内にとっても大事なことなんだと、社内に向かって発信をしていく、こういったことをやっていくことで、会社全体の組織変革につながるきっかけになるということも考えていただければと思います。
ご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。「男性育休、人事は何から始める?」というかたちで、何から始めたら良いのかをまとめた資料と、先ほどの面談シートというものを、無料でダウンロードできるようにしておりますので、ぜひ皆さんの施策に役立てていただければと思います。以上になります。