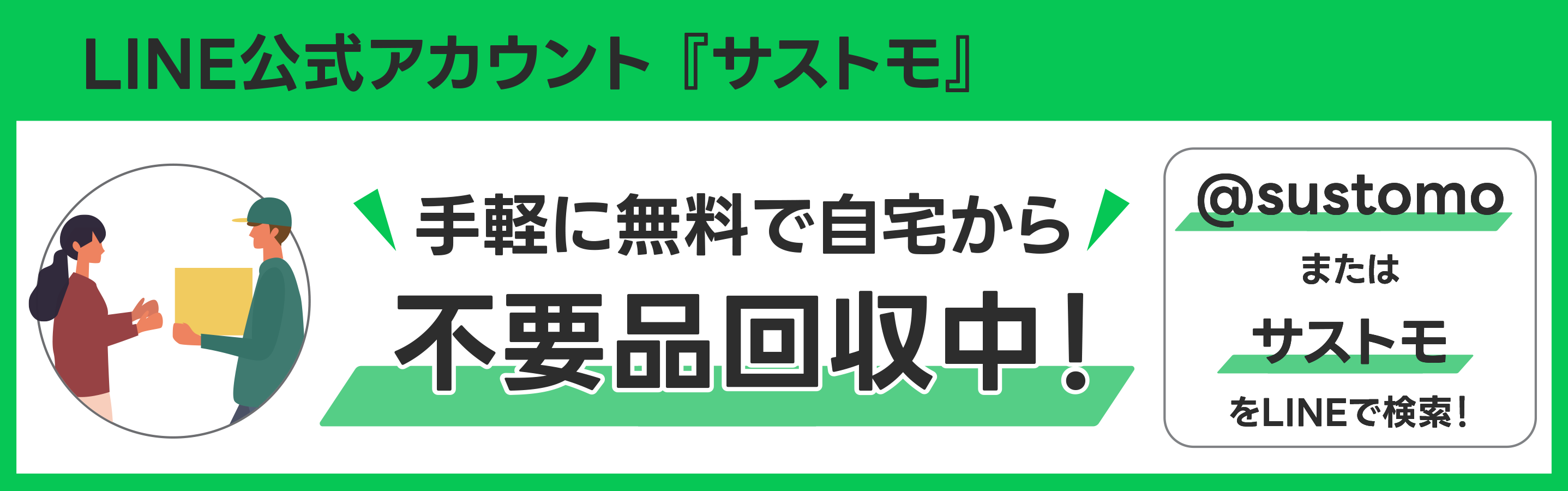全盲ながら子供3人を育てた両親 毎日の苦難と工夫、温かかった周囲のサポート

2年前、視覚障害者専門のナレーションサービス「みみよみ」が誕生した。視覚障害者の強みである声を生かし、彼らの就労機会の増加も目指す取り組みだ。代表の荒牧友佳理さんは、全盲の両親に育てられた。そのときの生活が「みみよみ」のビジネスにつながっている。一方、両親は友佳理さんら3人の子どもを育てたというが、苦労も多かった。両親と荒牧さんに話を聞いた。(ライター・庄司里紗/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
視覚障害者がナレーターに

ある配管企業のPR動画。女性の明瞭な声でナレーションが語られる。
<コロナ禍であっても私たちが工事を続ける理由は......>
このナレーションをしているのは、「みみよみ」(東京都千代田区)に所属するナレーターだ。同社には20代から50代までの6人のナレーターが所属するが、共通しているのは視覚障害者であることだ。
「ナレーションの技術は奥が深く、一朝一夕に身につくものではないので、プロによる指導や研修は必須です。ただ、視覚障害のある人には、目が見えないからこそ他の人たちよりも優れている声がある。そのことを社会も、視覚に障害がある人たち自身にも、もっと気づいてほしいんです」
みみよみを運営する合同会社ゆるりの代表、荒牧友佳理さん(37)が言う。
視覚障害者にとって声は重要な伝達手段だ。発声や滑舌、抑揚のつけ方に高い意識を持つ人は少なくないという。その声を生かし、働き方の選択肢を増やしたい――荒牧さんはそんな思いで2020年6月に「みみよみ」を起業した。
起業のきっかけは身近にあった。荒牧さんの両親は全盲だったのだ。
「父も母も、わずかな物音や声の抑揚の変化から、驚くほどいろいろなことを感じ取ります。視覚に頼れない部分を補完するため、音や声に対する感性が豊かに育まれたんだと思います。幼いころから両親を見てずっとそう感じていました」
全盲両親の精力的な暮らし

埼玉県の中ほどに位置する滑川町。緑豊かな住宅街に荒牧さんの父・宮城正さん(61)と母・好子さん(59)は暮らす。2階建ての一軒家で、周囲に広がる住宅と大きな違いはない。
「よく来てくださいましたー!」。自宅を訪れると、よく通る大きな声で好子さんが話しかけてきた。挨拶もそこそこに、カメラマンの持つ一眼レフカメラに興味を示すと、その重みを感じながら「牛乳2本分ぐらいかな?」と笑顔を見せる。そんな好奇心旺盛な好子さんを、正さんがほほ笑みながら優しく諭す。

大きなダイニングセットが置かれたリビングに整頓されたキッチン。火災防止のためIHコンロであることと、全てのドアが安全に開閉しやすい引き戸になっていること以外、設備は一般家庭と変わらない。
正さんは1階で鍼灸院を営む。好子さんはあん摩マッサージ指圧師の資格をもち、東京都内の大手企業で社員の疲労回復を担うヘルスキーパー(企業内理療師)として働く。平日は毎日、都心の職場まで片道2時間かけて電車通勤している。
「朝は6時20分に家を出て、夕方までフルタイムで働いています。通勤を始めたころは、改札で半年分の定期を落として失くしてしまうなど苦労もしましたが、もう20年以上そういう生活なのでさすがに慣れましたね」
好子さんは家事も一通りこなす。包丁やガスコンロの扱いなどは盲学校(現・特別支援学校)で学んだ。電子レンジや炊飯器は、音声ガイド機能のついたものをそろえている。
料理は野菜炒めやポテトサラダなどシンプルなメニューが中心だ。大皿に彩りよく盛り付けるのは難しいので、小皿に取り分けて出すことが多い。思わぬやけどを防ぐため、粗熱を取ってから食卓に並べるのも、宮城家ならではの工夫だ。
掃除は、掃除機のパイプを外し、ホースの先に直接ノズルを付け、床を触って確かめながら行う。「そうしないと、落ちている靴下を吸い込んじゃったりするから」
もちろん見えない中での家事は完璧ではないが、「今は国の制度でヘルパーさんが来てくれるので、ふだんの生活で困ることは特にないですね」と話す。
猛反対された結婚

正さんと好子さんは、埼玉県内の盲学校の高等部で出会った。1985年、正さんが24歳、好子さんが22歳のときに結婚した。ともに若く、視覚障害を抱えていたため、親たちは当初、結婚に猛反対だった。好子さんが振り返る。
「夫婦そろって車も運転できない、文字も読めない。いったいどうやって生活していくつもりなんだ、と親たちは大反対。でも、当時はとにかく親元を離れて自立したかった。全盲の私は授かりでもしなければ、一生結婚できないとも思いました」
2人は計画的な"授かり婚"で周囲の反対を押し切った。
苦労も多かった子育て

埼玉県坂戸市の公団住宅で新生活を始めて間もなく、長女の友佳理さんが誕生した。その1年5カ月後に次女の多喜さんが生まれると、生活は多忙を極めた。当時、病院のマッサージ師だった正さんは早朝から出かけてしまうため、育児は好子さん一人。粉ミルクは計量ができず、完全母乳。当時高価だった紙おむつは使えず、毎日60枚近い布おむつの洗濯に追われた。
「おむつ交換のタイミングは、においでわかる。お湯で固く絞った布おむつでお尻を拭いていました。多少の拭き損ないは気にしませんでしたね。洗濯も汚れが完全に落ちたかどうかは確かめられないので、においがしなくなればよし、と割り切っていました」

育児に慣れないころは、床に寝ている娘を踏んでしまいそうになったため、娘たちがいる部屋では足先で床を探るように歩くようになった。
「いまだに忘れられないのが、娘がハイハイで付いてきていることに気づかず、お風呂場のドアで娘の手を挟んでしまったこと。思い出すと胸がギュッと苦しくなります。以来、家の中のドアはなるべく開けたままにして、閉めるときは大きな声で『閉めるよ!』と声かけするのが習慣になりました」
料理では、揚げ物の油に引火してあわや火事になりかけたこともあったという。
絶え間ない授乳、おむつ交換、料理。その合間を縫って買い物にも行かなければいけない。背中に長女をおんぶし、前に次女を抱き、白杖をつきながら片手に買い物袋を提げて歩く好子さんの姿は、近所の人たちの目に留まるようになった。
「地域の人たちにはたくさん助けてもらいました。八百屋さんに行くと、じゃがいものカゴを蹴飛ばしちゃったりするんだけど、そのうち『今日は何が欲しいんだい?』なんて声をかけてくれて。品物をカゴに入れてお会計まで手伝ってくれたりして、ありがたかったですね」
一方、マッサージ師として働いていた正さんは、月の手取りが20万円に届かなかったため、次女が生まれた後、独立を決意。埼玉県ふじみ野市に住まいを移し、自宅で鍼灸院を開業した。ところが、完全に裏目だったと正さんが苦笑する。
「お客さんが全く来なかったんです。親からの援助も貯金もなく、経済的に行き詰まってしまって。妻からのプレッシャーもあり、鍼灸院の営業終了後に近くのサウナで夜間のマッサージの仕事も始めました」
「体温計を見て欲しい」とスナックへ

好子さんも仕事を探したが、幼子を抱える視覚障害者への求人は皆無に等しかった。働く方法を模索し、仲間たちと福祉作業所を立ち上げたり、視覚障害者向けの専用ラジオ放送局で番組のアシスタントを務めたりもした。

長女・友佳理さんが4歳のころには、三女・琴音さんも生まれた。好子さんは、自由に動き回る娘たちが外にいても居場所がわかるよう、靴に小さな鈴をつけることにした。効果的だったが、しばらくして予想外の結果を招くことになった。
「娘たちの通う保育園で、他の子たちも真似して靴に鈴をつけだしたのです。迎えに行くと、園庭のあちこちからシャンシャンと音がするわけですよ。もう、どれが我が子の音なのか全然わからない(笑)」
最も困ったのは子どもが風邪を引いたときだ。当時の体温計では、熱を測っても目盛りが読めない。深夜に子どもが高熱を出したときには、近所のスナックに駆け込んだこともある。
「頼れるのが2軒隣のスナックだったんです。場違いだと思いつつも、カラオケで盛り上がる店内に娘を抱いたまま入って、『どなたか体温計の目盛りを見てもらえませんか!』と大きな声でお願いしたこともありました」
宮城家をサポートする人たち

助けを求めるといつも誰かが支えてくれた。当時の宮城家には、視覚障害者の仲間やボランティア、地域の母親など大勢の人が出入りしていた。現在、都内の福祉施設で働く女性(55)も、当時、宮城家をよく訪れていた一人だ。
「外出の際、正さんと好子さんが電車ごっこのように2本の白杖の先を握って、よちよち歩きの娘さんたちを守って歩いていた姿を今でも覚えています。お子さんたちが成長してからは、お二人が我が子に頼る場面も多かったと思いますが、当時のお二人は子どもたちを危険な目にあわせないよう、工夫しながら一生懸命に子育てしていた印象が強いです」
埼玉県蕨市の松村雅子さん(77)も、点訳ボランティアとして40年近く、宮城家を支えてきた。娘のための絵本から学校の配布資料まで、点訳したものは数知れない。
「好子さんは『目が見えないからできない』ではなく、常に『どうやったらできるようになるか』と考える。あるとき、手編みのチョッキを作りたいと相談されて、『編み図の点訳なんてないわよ』と答えたら、『それなら一緒に作りましょう』と。点訳ボランティアの仲間たちを巻き込んで、編み図の点訳に試行錯誤しました。彼女は率直に伝えてくれるから、私たちも自然な形で手助けできたんだと思います」
友佳理さんが幼少期に感じたつらさ

長女・友佳理さんは両親と暮らすなかで、物事を正確に伝える力は視覚障害者に共通する特長だと気づいた。
「母は何かを説明するときに、誰が聞いても正確に理解できる言い方をします。例えば、背中がかゆかったら『背中をスマホの画面だと思って、5番のところを掻いて』と言う。何事も具体的でわかりやすく表現する能力は、両親に鍛えられた気がします」
ただ、幼いころにつらさを感じたことは少なくない。目が見えない両親のために、誰よりも早く数字や文字を覚えたこと。保育園の親子イベントで切り絵をしたとき、何もできない母が恥ずかしくて泣いてしまったこと。小学校に入学して教科書を配られたとき、みんなは親に名前を書いてもらうのに、一人だけ自分で記名しなければならなかったこと──。友佳理さんは"親を支える良い子"という立場に葛藤し、次第に反発するようになった。中学に入ると学校を休みがちになり、夜遊びや家出を繰り返した。
両親はそんな娘を辛抱強く信じ続けたという。「子どもは子どもなりに自分で考え、育っていくもの」という考えがあったからだ。

「教育理念とか、そんな大層なものはないです。でも、最近知ったアドラー心理学の本に、子育てで大事なのは『手伝わない、手を出さない、できるチャンスを奪わないこと』という趣旨の記述があって。それって、まさに我が家の子育てそのものだなと。子どもたちが自分なりに考え、行きたいと思った道を歩んで幸せになってくれれば、それでいいんです」
友佳理さんは大学卒業後、英語を学ぶためフィリピンに留学し、その後は同国や南アフリカの企業で働いた。両親は、海外を目指した友佳理さんに、何も言わず貯金から120万円を工面してくれた。
好子さんは言う。
「やりたいと思ったときに行動しなければ、チャンスは逃げてしまう。娘たちがやりたいと言ったことは、多少無理をしてでもかなえてあげようと思っていました」
その考えは、宮城夫妻の生き方そのものでもある。子育てが落ち着き、40歳を過ぎてからマラソンを始めた好子さんは、今やフルマラソンを完走するベテランランナーとなった。今年からは全盲の暮らしを伝えるYouTubeチャンネルも始めた。夫の正さんも3年ほど前からベンチプレスを始め、大会で好成績を収めている。
視覚障害者の能力を生かしたい

そんな両親の姿を見続け、自身も2児の母になった友佳理さんが妹たちとともに「みみよみ」を設立した。それは必然かもしれないと友佳理さんは言う。
「子どものころから、すごく悔しかったんですよ。視覚障害があっても、彼らには素晴らしい"声"や"語り"という能力がある。なのに、それを生かす場がないのは不公平じゃないか、と」
幼い友佳理さんの心に刻まれた悔しさともどかしさ。それは、視覚障害者の就労状況の数字にも表れている。

現在、日本の視覚障害者の数は約30万人。「令和2年度 障害者の職業紹介状況」(厚生労働省)によると、身体障害者全体の就職件数が約2万件あるのに対し、視覚障害者が占める割合は約7.5%(1500件)にとどまっている。視覚障害者には、デスクワーク中心の事務職の求人が少ないことがその一因とされている。彼らの多くは「あはき業」(あんま・はり・きゅう)に就いているのが現状で、就労機会は限定的だ。友佳理さんは視覚障害者の可能性を広げたいと言う。
「多くの人々に、同じ社会に生きる身近な隣人として、視覚障害者の持つ能力を知ってもらいたい。『みみよみ』のサービスを通じて、そんな未来が実現できたらいいなと思っています」
元記事は こちら
庄司里紗(しょうじ・りさ)
ライター。1974年、神奈川県生まれ。大学卒業後、ライターとして多数の雑誌、Webメディア等に寄稿。現在は地方創生、共生社会、ゲノムデータをめぐる倫理問題などを関心領域に執筆している。