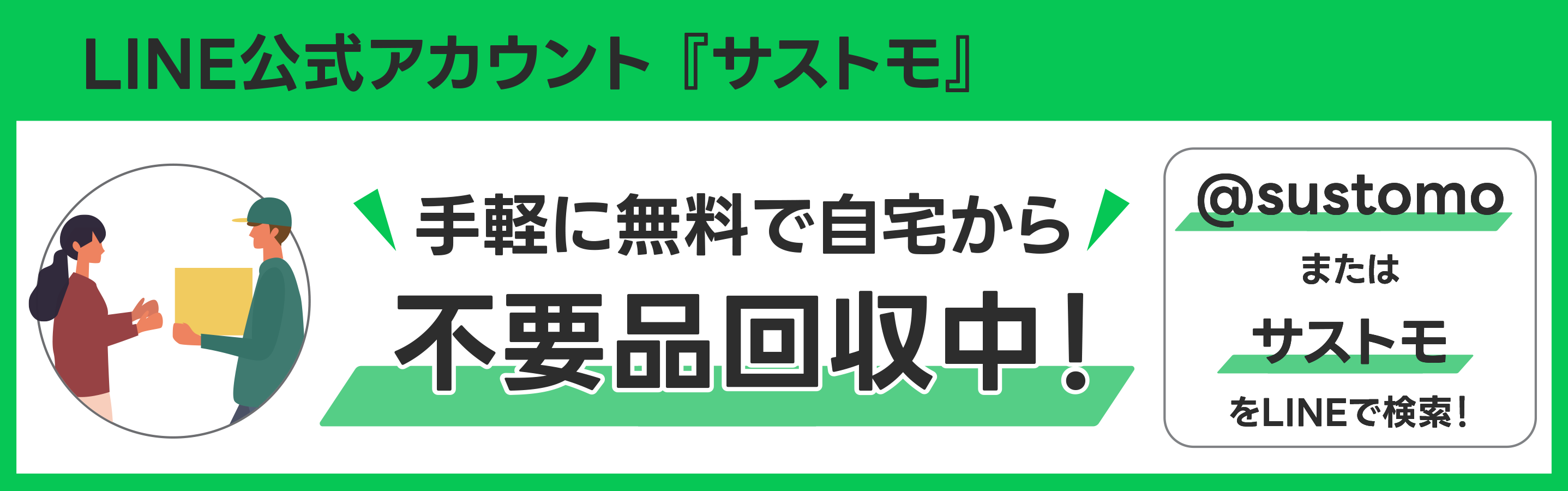「避難所には行きたくない」奥能登で被災したろう者が経験した「壁」──支援ニーズの掘り起こしとその先の対応 #災害に備える

能登半島地震から3カ月。今回、奥能登では、避難所へ行くことを諦めて、半壊した自宅にとどまったろう者がいた。高齢者・障害者の避難支援が制度化されてきているが、見落とされがちなのが、「普段は福祉サービスを利用していない障害者」である。平時には、さまざまな生活上の工夫や当事者コミュニティーの助けで問題なく生活できているが、いざ災害が起きると、それが機能しなくなる。困った状態に置かれても、代わりに手をあげてくれる人はおらず、避難所コミュニティーにも入りづらい。結局、半壊した自宅で我慢して過ごすしかなくなる。繰り返し起きていることだ。奥能登のろう者の場合、当事者団体の強い支援で2次避難所にコミュニティーをつくることができた。支援にあたった人たちと専門家に取材した。(取材・文:長瀬千雅/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
自宅が被災、でも避難所へ行きたくない

能登半島地震の2次避難所になっている石川県白山市の体育館。受付の長テーブルの端に、「聴覚障害者」の貼り紙が下がっている。
この避難所では、輪島市からの避難者に交じって、能登町や珠洲市のろう者9人とその家族2人が避難生活を送っている。
石川県聴覚障害者協会の職員、沖田耐芽(おきだ・たいが)さん(29)は、金沢市からこの避難所に通って、被災したろう者のサポートにあたる。
沖田さんの職場は、能登町にある「やなぎだハウス」という聴覚障害者が多く通う就労支援事業所で、ほとんどのろう者と顔見知りだ。沖田さん自身もろう者で、手話で話す。
「高齢の方が多いので、やっぱりみなさん、能登に帰りたいとおっしゃるんですね。僕としても、地震が起きる前のような、みんなで集まって楽しく暮らせる環境に戻りたいという気持ちがあります」
被災したろう者が、奥能登2市2町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町)のあちこちから、白山市の体育館に集まったのには理由がある。協会の専任手話通訳者が伴走できるよう、一層の情報保障を求めたからだった。
情報保障とは、障害のあるなしにかかわらず、誰もが必要な情報にアクセスできるように保障すること。ろう者・難聴者の場合、文字情報や手話通訳、要約筆記などがそれにあたる。

これまでの災害で、被災したろう者・難聴者は、食事のアナウンスが聞こえず、みんなが並んでいるのを見てあわてて並ぶ、ふだん飲んでいる薬が切れかけていると言ってもわかってもらえない、行政手続きや生活に関わる情報が入手できないなど、避難所生活に苦慮してきた。
また、情報保障というと、聞こえる人は、文字情報を掲出したり筆談をしたりすればよいだろうと考えがちだが、手話を第一言語とするろう者には、筆談のみで込み入ったことを伝えるのはストレスがかかるうえ、日本語の読み書きが苦手な人もいる。だから手話通訳者にいてほしいのだが、その重要性を聞こえる人になかなかわかってもらえない。
そういった気詰まりを見越して避難所に行かない人も少なくない。そうなると、支援の手が届かなくなってしまう。
今回の地震で被災して、白山市の2次避難所で暮らすろう者にも、1次避難所に行かず自宅にとどまった人がいた。
避難所でぽつんと一人、「情報の壁」
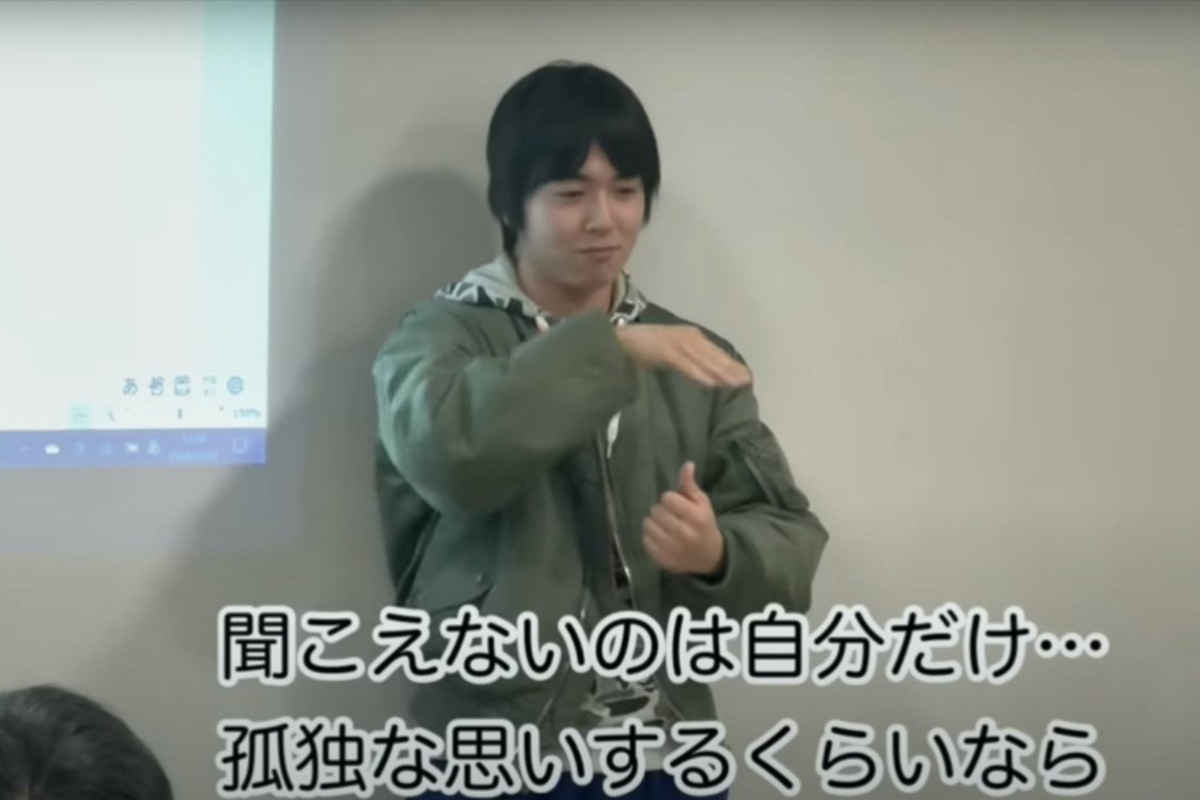
被災したろう者の支援には、当事者団体が果たした役割が大きかった。
沖田さんが勤務するやなぎだハウス(2017年開所)は、「奥能登ろう者の集い」を前身とする。2007年の能登半島地震をきっかけに、孤立しがちだった奥能登のろう者のために、手話で話せるコミュニティーをつくろうということから始まったものだ。
現在、奥能登ろうあ協会の会員は15人。沖田さんを除いて全員60歳以上で、平均年齢は75歳。80代の人もいる。
沖田さんは、地震が起きた1月1日、正月休みで岐阜県の実家にいた。「まずびっくりして。とにかく落ち着こうと自分に言い聞かせました」
職員のグループLINEで、職員間で「大丈夫ですか?」とメッセージを送り、そこからすぐに、利用者の安否確認が始まった。沖田さんも「大丈夫ですか?」「けがはないですか?」とメッセージを送った。返信はなかなか来なかった。
「やなぎだハウスの利用者の方は、スマホやLINEを使いこなせる方ばかりではないんですよね。スマホを自宅に置いて避難した方も多かったのです」
翌2日に金沢に戻り、3日に車で奥能登へ向かった。道路状況が悪く、ふだんは2時間のところ、7時間かかった。渋滞で止まっている間も余震がきて、身のすくむ思いがした。

3日かけて、ろう者の自宅や避難所を訪ねてまわった。無事であることは確認できたが、自宅が半壊・全壊で住めなくなっている人が多かった。
穴水町に暮らす兄弟は、外出時に被災。自宅に帰ると玄関の扉がなかなか開かず、やっと開けて中に入ると、家じゅうの物が散乱していた。車中泊をしたり母家の脇の倉庫で過ごしたりしていたが、灯油が尽きて暖が取れず、寒さで震えていた。沖田さんは避難所へ行くことをすすめたが、「避難所は聞こえる人ばかり。孤独な思いをするぐらいなら行きたくない」と拒んだ。
能登町の一人暮らしの女性は、近所の人と一緒に避難所に行っていたが、手話で話せる人はおらず、かなり気落ちしているように見えた。
石川県聴覚障害者協会で業務執行理事を務める藤平淳一さん(51)は、被災したろう者の状況をこう話す。
「奥能登の特徴として地域のつながりが強く、近隣の方の支援をいただいて一緒に避難所へ行ったり、食事の時間だよと声をかけてもらったりということはあったようです。ただ、問題は、運営からの情報保障がなかったことです。奥能登のろうあ者は、それぞれ避難所でぽつんと1人、情報の壁を抱えて避難生活を送っておられたのです」
「みんなと一緒に」聞こえない仲間のいる避難所へ

藤平さんらは、県に対して「被災したろう者をできるだけ1カ所に集めてほしい」と要望した。
県がいしかわ総合スポーツセンター(金沢市)に1.5次避難所(2次避難先に移るまでのつなぎの施設)を開設すると、障害福祉の担当部署に掛け合って、何かアナウンスをする際は必ず視覚情報も掲出することや、手話通訳者が常駐する態勢を整えてもらった。
「聞こえない人たちが、必要な時に自分の言葉(手話)で話して安心を得られる環境は、非常に大切です。ひとつの例をお話ししますと、輪島市の、あるろうの方が、近隣の小学校に避難されていました。その方は、野々市市の2次避難所に移るという話があったのですが、『1.5次避難所には聞こえない人たちが集まっているよ』とお伝えすると、『みんなと同じ避難所に行きたい』とおっしゃいました。今回、被災したろう者の支援にあたってみて、聞こえない仲間がいる避難所を選びたいという方がたくさんいたと感じています」
その後、白山市が2次避難のろう者を受け入れることになり、現在の施設に移動した。穴水町の兄弟も合流した。
一方で、藤平さんらがリーチできない人たちもいる。例えば、ろう者でも協会と接点がなかったり、手話を使わない難聴者だったりする人たちだ。奥能登で身体障害者手帳を持つ聴覚障害者約270人のうち、協会が把握するのは50人ほどだという。
能登半島では、昨年5月にも大きな地震があったが、その際、被害の大きかった珠洲市で、藤平さんらは市と連携して聴覚障害者の支援にあたった。市の職員と保健師の戸別訪問に、手話通訳とろうあ相談員が同行し、困りごとを聞き取って解消につなげた。
しかし今回は被害の甚大さもあってそのような連携ができなかった。
「残存聴力がどれくらいあるか、読話が得意か、筆談はできるか、文字起こしアプリを使ったことがあるかなど、聞こえない・聞こえにくい人のコミュニケーションは一人ひとり違います。自治体と連携できれば、困っている方を見つけ出して支援できるのですが、かなわない状況です」
能登半島では、これまでにも大きな地震が繰り返し起きていたことから、藤平さんらは各自治体に、聴覚障害の特性に合わせた福祉避難所(障害者や高齢者など、配慮が必要な人を受け入れる避難所)の設置を求めてきたという。藤平さんはこう話す。
「昨年5月の地震を受けて、やなぎだハウスに福祉避難所的な機能を持たせられないかと考え、独自の災害対策マニュアルの作成を進めていました。障害特性に合った対策を、全国の市町村の防災計画に盛り込んでいっていただきたい」
避難所運営の現場で「合理的配慮」を当たり前に
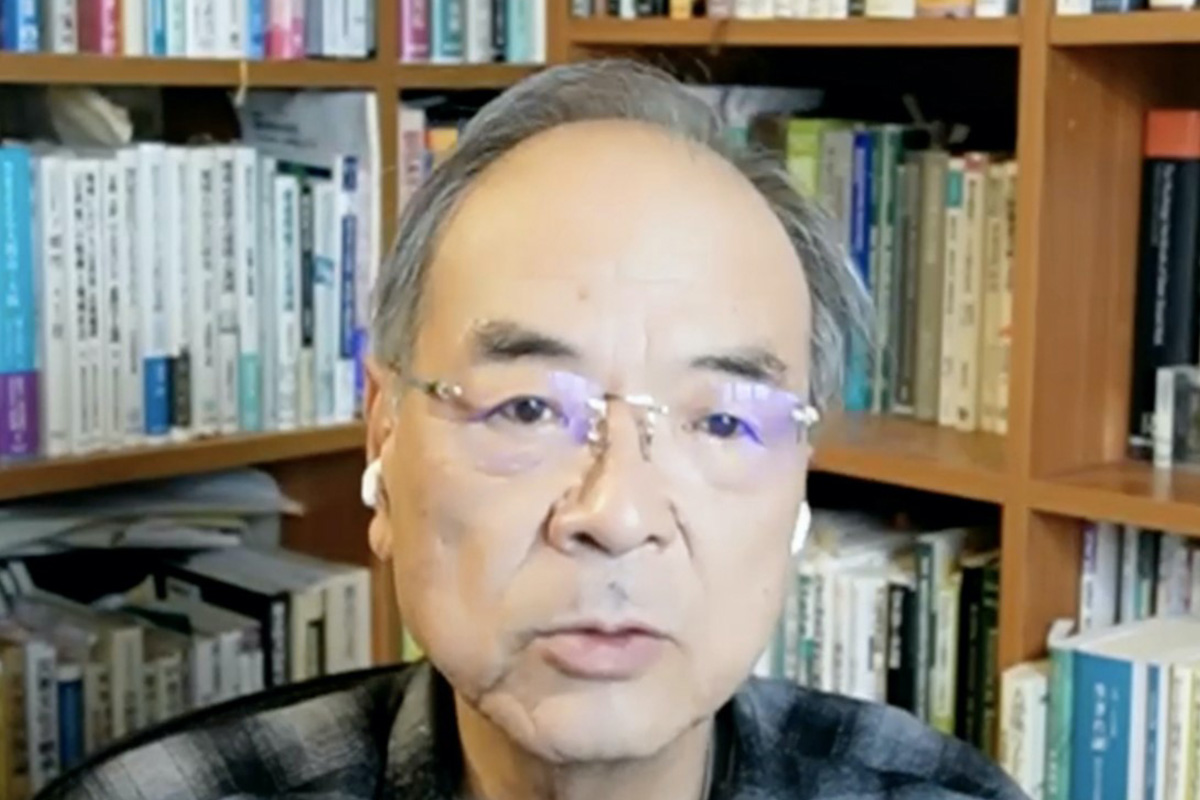
福祉避難所は重要だ。一方で、指定されている施設が被災したり、職員が被災したりといった理由で、開設できないことも多い。今回の地震でも、福祉避難所の設置が進まなかったことが報じられている。
福祉と防災に詳しい立木茂雄さん(同志社大学教授)は、「要配慮者は福祉避難所でというだけでなく、よりユニバーサルなプランも持つべき」と説く。
「協会が一軒一軒避難所や自宅をまわり、困っている当事者を掘り起こして支援されていることには、頭が下がります。一方で、協会とつながれない人はどうするのだという課題は残ります。ろうあの方だけでなく、視覚障害や車いすの方もそうです。普段付き合いのある当事者コミュニティーの仲間がすぐに駆けつけられるとは限りません。避難所に行っても、車いすユーザーは靴が散乱していると入れない。通路が狭い。トイレがバリアフリーであるとは限らない。自分たちは避難所では暮らせないとはなから諦めて、自宅でひっそりと我慢して暮らす当事者の方が出てくる。これは災害のたびに繰り返し起きていることです。
障害を『社会モデル』でとらえれば、どの避難所でもバリアがないように合理的配慮を提供するのが本来の姿。ところが、避難所運営の現場では、そのことがまだ常識化していないんですね」
「社会モデル」とは、障害を、その人個人の問題とするのではなく、社会の側にある障壁によって生じるものとする考え方。
「避難所に来られない人がいたら、どこにバリアがあるのかを見直して、当事者が参画して運営マニュアルを検討し直すなど、改善するプロセス自体を地域防災計画に盛り込むといいと思います」
先進的な取り組みをしている自治体はある。
「例えば、大分県別府市は、部局の垣根を越えて、庁内連携で誰一人取り残さない防災計画づくりに取り組んでいます」
障害者にとっての災害は「新たな障壁が立ち現れること」

2021年に災害対策基本法が改正され、避難に支援が必要な人に個別避難計画を作成することが、市町村の努力義務になった。実際のプラン作成は、ケアマネージャーや相談支援専門員が、地域の方々と一緒になって担当する。
立木さんによれば、今回の地震では、介護保険サービスの利用者や障害者福祉サービスの利用者など、日頃から福祉の専門職が伴走している人たちは、大規模な避難所へ行けた。
しかしすべての障害者がそれに当てはまるわけではない。
「障害者手帳を持っている人の6、7割は福祉サービスを利用していません。なぜかといえば、日常生活で困っていないからです。ところが、災害によって環境が激変して、新たに障壁が生まれると、急に困るわけです。突然脆弱な立場に置かれる。これが障害のある人にとっての災害です」
当事者にできることは、自分で個別避難計画をつくることだという。
「もし私が被災したらどうなるんだろうと、自分の個別避難計画を自分でつくることが、まずできることです。水道が止まったら家にいられない、でも避難所へ行っても、アナウンスはスピーカーだけだし、何が起こっているのかわからないかもしれない。何か要望しようと思っても、ちゃんと聞いてくれるかどうかわからない。じゃあどうしようと、具体的にシミュレーションしてみる。そうすると、隣近所とつながる必要があるぞといったことがわかってくる。そのつながりを平時からつくっておくことが大事になってくるわけです」
これは障害者だけでなく、小さい子どもがいる家庭や一人暮らしの高齢者などにも言えることだ。
「子育て中のお母さんも障害のある方も、いざという時に配慮が必要なのは同じ。じゃあ、配慮を引き出すためにどうするか、と考えるんですね。いわば、縦割りではなく、横につながるプランです。そういったプランをつくる場に、当事者がどんどん参画してほしいと思います」
元記事は こちら