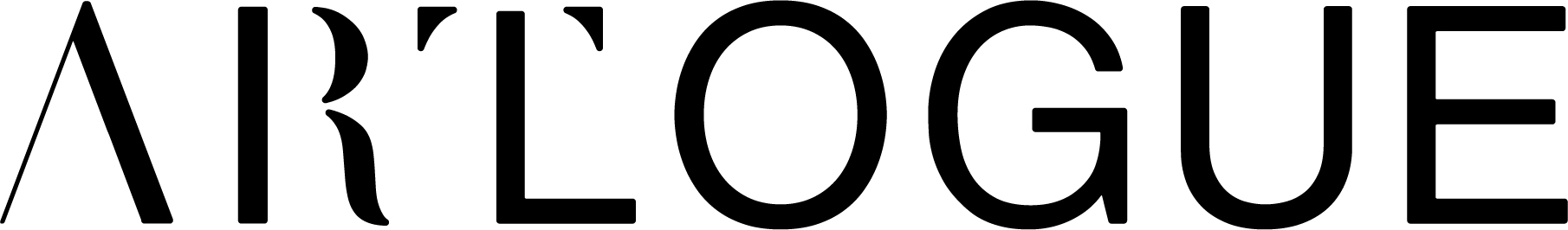アートは、社会課題に対して無力か。 「アート×ヒト×社会」の関係をStudyする芸術祭

「ソーシャルインパクト」をテーマに、国内外の現代アートを集めた「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」が開催されている。社会が直面する様々な課題に対し、アートは何ができるのか。2022年からStudy(実験・研究)の場として小規模なプレ芸術祭を重ね、本祭ともいえる今年は、大阪・関西万博と同時期に、夢洲の万博会場、安藤忠雄設計の大阪文化館・天保山、西成や船場地区など大阪の象徴的な場所で行われる。
「単なる一過性のイベントではなく、ここから街にアートがあふれ、雇用が生まれ、発展する国際芸術都市大阪を目標にしています」と、同芸術祭の総合プロデューサを務める鈴木大輔さん。アートの役割とは何か。芸術祭から生まれるより良い社会とは?
鈴木大輔 SUZUKI Daisuke
ARTLOGUE(株式会社アートローグ)www.artlogue.org
代表取締役CEO / アートイノベーター
・Study:大阪関西国際芸術祭 創設者・総合プロデューサー
・大阪経済大学 国際共創学部 客員教授
・大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ(SSI)招へい研究員
アートの力で未来社会を創造する

鈴木さんは、大阪市立大学(現・大阪公立大学)でグローバルCOEプログラム「社会的包摂と文化創造に向けた都市の再構築」に携わり、2017年に株式会社アートローグを設立。アートを活かした社会問題の解決を目的に、アートと社会、経済、政治などを結ぶ様々な企画をプロデュースしてきた。
アートは都市にどんなインパクトを及ぼすのか。
「例えば、スペインのビルバオは1980年代に基幹産業の鉄鋼業が衰退し、失業率25%で街は荒れ果てていましたが、1997年にビルバオ・グッゲンハイム美術館を誘致したところ、最初の3年間に400万人の観光客が訪れ、5000人以上の地元雇用を創出。街は現代アートの聖地に生まれ変わりました。そういった例は国内外にたくさんあります」
世界では、貧困や飢え、環境問題、戦争やテロなど多くの問題が山積。日本でも、子どもの貧困や高齢者の孤独・孤立、人口急減による労働力不足など社会課題は複雑化、多様化している。
こういった問題に対し、「アーティストは"炭鉱のカナリア"として、問題提起をする力があります」と、鈴木さん。「アートは、未来を切り開く創造力と人や社会を思いやる想像力をもたらす。新しい価値の創造や共生社会の実現など様々な役割が期待されています」
一方、日本のアート事情をみると、国の国民一人あたりの文化支出額は922円と、フランス6784円、韓国5842円と比べて非常に低い(2019年、日本円に換算)。美術品市場は約900憶円と世界の美術品市場の1%程度しかなく、十分に文化・芸術の力が生かされていない。東京一極集中なのも課題になっているという。
「2025年の大阪・関西万博を契機に、アートの力を大阪・関西のみならず、日本の成長戦略として生かすことでよりよい未来社会を創造する。そのためにアート×ヒト×社会の関係を集合知型でStudyするこの芸術祭を立ち上げました」
20の国・地域から65組のアーティストが参加。新たな対話と発見の旅にいざなう。
いよいよ2025年の万博イヤーに本祭が開幕。「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」は、20の国・地域から65組のアーティストが参加し、大阪・関西万博会場、大阪文化館・天保山、西成や船場地区など多彩な場所で繰り広げられている。その一部を紹介しよう。
万博会場では「多様なる世界へのいざない」をテーマに、13組のアーティストがパブリックアートを出展。株式会社ヘラルボニーがプロデュースする田﨑飛鳥の壁画、車いすを素材にした檜皮一彦の彫刻、「空気と水と太陽」を題材にした奥中章人のバルーン状のインスタレーション、総合地球環境学研究所のSceNEプロジェクトによる作品など。5大陸の石をみんなでハート型に磨いて交流する冨長敦也のラブストーンプロジェクトも参加者が広がっている。




安藤忠雄設計による大阪文化館・天保山では、「Reshaped Reality」と題し、ドイツの研究機関と共に「人間とは何か」を問いかける。ロン・ミュエクらハイパー・リアリスティック彫刻は、鑑賞者を視覚的錯覚に陥らせる。

西成エリアでは、「労働者のまち」から「外国人や若者のまち」に変容する釜ヶ崎でアートの可能性を模索。上田假奈代氏が2012年に立ち上げた「釜ヶ崎芸術大学」、美術家の西尾美也氏が地域の高齢女性たちと立ち上げたファッションブランド「NISHINARI YOSHIO (西尾美也 + kioku手芸館「たんす」)」によるリサーチプロジェクト「後継者問題(仮)」などを展開する。


東西南北、文化が交差する船場エリアは、「Re:Human―新しい人間の条件」をテーマに、テクノロジーが進化する中、生と社会を見つめ直し新しい「人間らしさ」の可能性を探る。関西の作家を中心に映像や写真、彫刻、絵画、インスタレーションなどを通して人間の本質を問いかける。


クリエイティブ・エコノミーを創造する
「この芸術祭は、今回で終わりでなく、これからも持続可能な開催を目指して、関西でクリエイティブ・エコノミーを発展させたいと思っています」と、鈴木さん。
民間主導でお金を回すために、アートフェアを開催。今年は日韓国交正常化60周年を記念して、7月21日(月・祝)~23日(水)、日韓合同の国際アートフェア「Study×PLAS:Asia Art Fair」を大阪府立国際会議場で開催する。
アートや文化、ファッション、観光などクリエイティブ・エコノミーに特化したビジネスコンテスト「StARTs UPs」も実施し、クリエイティブ・エコノミーのスタートアップ企業を強力にバックアップしていきたいという。
芸術祭と共にアートの輪を広げる公式サテライトプログラム「Co-Study」も実施。芸術祭期間中、一緒に盛り上げるアート企画やイベントを全国から募集し、様々なアート作品や活動と芸術祭を双方向に連動しながら情報発信する。
「回を重ねるにつれ、"Study"は芸術祭の愛称になっています。これからも常に時代の要請、時代の状況に応じて新しい実験的な取り組みを続けていきます。より良い社会のためにぜひ共に"Study"しましょう」と、鈴木さんは呼びかける。