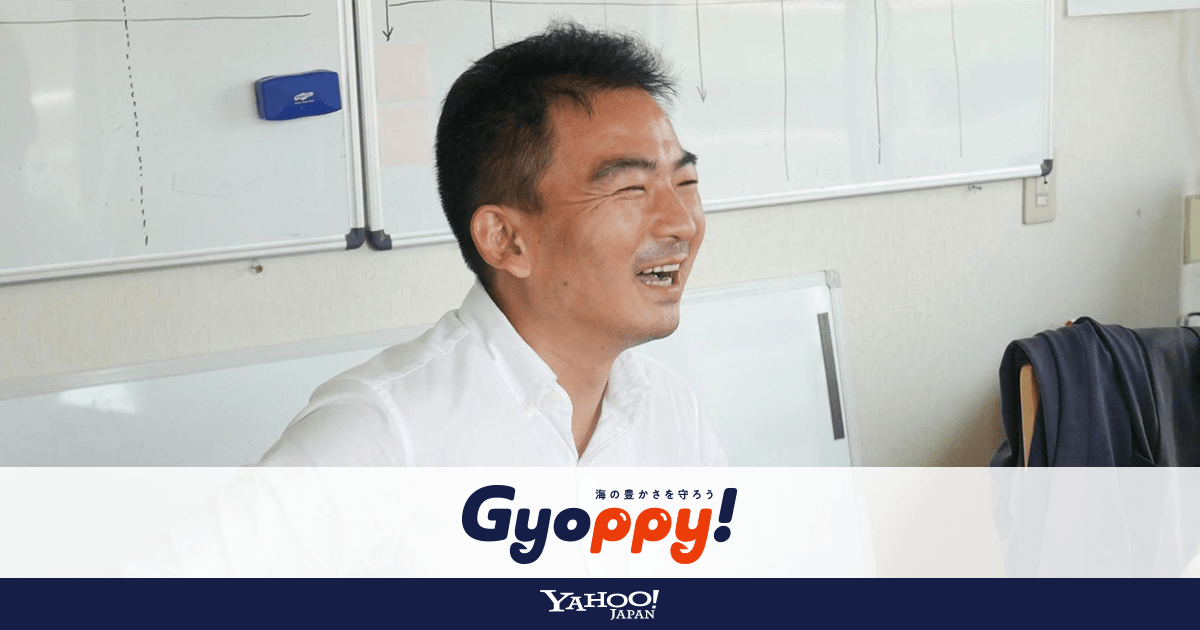「生きていれば、再生できる。生きている限り、世に尽くす」東京の居酒屋経営者が、三重県で漁業を始めた理由
「『あっ、終わってしまう』って思ったんです、漁業が」
株式会社ゲイト代表、五月女圭一さんの言葉だ。
神田、新橋、虎ノ門などを中心に都内にて展開する居酒屋チェーン「くろきん」「かざくら」などを運営する五月女さんは、現在、飲食部門と漁業部門を連携させる事業モデルを構築、三重県で漁業を再生させる取り組みに乗り出している。

不動産、コンサルティング、接骨院、居酒屋、そして漁業へ。
一見すると脈絡のない業界遍歴をたどって来た五月女さんだが、漁業の世界に足を踏み出した背景には、単なる使命感や危機感以上に、人生を貫く信念と哲学があった。
今回はそんなひとりの男の新しい取り組みと、出会い、そして"再生"の物語に迫る。
日本の漁業が終わってしまうと思った

── 最初に、三重県で漁業を始めた経緯を教えてください。
東日本大震災が、ひとつの大きなきっかけでした。東京に今ある居酒屋店舗の第1号ができたのが、2010年の10月。その後まもなく震災があって、魚を中心に、どんどん食材の値段が上がっていったんです。
ただし食材といっても、実際に値上がりしていたのは中間流通費、いわば問屋さんに払うお金でした。電気代が上がれば、中間流通にかかるお金も高騰するわけです。
ですから僕らとしては、既存の流通ルートから抜け出す必要がありました。そこで、何かいい方法はないかと地方を回っているうちに、たどり着いたのが熊野(和歌山県南部から三重県南部にかけての地域)でした。でも、熊野でいろいろと見て回るうちに「あっ、このままでは漁業は終わってしまうな」って思ったんです。
── 五月女さんが見た衰退の風景とはどのようなものだったんでしょうか。
初めて漁港を見に行ったときが決定的でした。市場もきれいで、5つくらいの漁協が合併しただけあって集約されているなと感じたのですが、なぜか定置網の船が8つしかなかったんです。
聞けば、明らかにその数は今後も減っていく。「獲る人がいなくなったら、日本の魚は食べられなくなる」と思いました。

── だから、自社で漁業に参入しようと。
飲食店として生産地とつながれば、ユニクロみたいに一気通貫のビジネスモデルを構築できるというメリットもありました。
でも、それとは別に、漁業をやる人を増やさないと日本の漁業が終わってしまうという危機感が強くて。だったら、飲食店として漁業をやるところまで、やってやろうと思ったんです。
── 漁業に手を広げることに、リスクは感じなかったのですか?
漁業だって居酒屋と同じ。"居抜き"でやれば、できるはずだと考えたんです。
── 居抜き?
僕はもともと、居抜きと呼ばれるやり方で居酒屋を展開してきました。一度つぶれた店や、つぶれかかっている店を引き受けて、そこにある設備を使って再生させるやり方です。初期投資を抑えられるため、時間と労力をかけて知らない業界の構造を把握しながら広げていくことができるんですね。
そんな風に、漁業も新しい何かをつくってみんなで使うやり方でなく、もともとある価値を生かしながら再生させるやり方なら、うまくいくはずだと思いました。

「今あるもの」を使い切り、漁業を再生させる
── 具体的には、どういったやり方をされているのでしょうか。
基本的には、「三重県で獲ったり仕入れたりした魚を東京の店舗に持っていく」というモデルですが、魚を選ぶ際に、地域の事情に配慮した選び方をしています。
具体的に言えば、市場に入札する際、みんなが欲しがるような魚には入札しません。逆に自分たちの船で値が高く付きそうな魚が獲れたときは、それを東京の店舗で使わずに市場に揚げて、値がつかないものを東京に持っていく。
つまり、みんなが欲しがらないような魚を仕入れて、それを東京の店舗でどうおいしく提供できるか、と工夫しているんです。
ですから、魚は絶対に現地加工。じゃないと、おいしくないですから。加工場では、働いている地域のおばちゃんたちに、いつも食べているおいしい食べ方を教えてもらってます。その上で、それをどうやって東京までうまく運べるか、工夫をしているんです。
たとえば小さいアジが獲れて、南蛮漬けにしようと考えたとします。その場合、急速冷凍ではなく、比較的高い温度でゆっくり冷凍させたほうが、油で揚げたあとにお酢がしみやすいんです。そうすれば冷凍でもおいしいので、夏でも、大きな保冷ボックスに入れて、普通車で東京まで持ってくることができる。
── 獲れた魚を捨てることなく、生かしきるということですね。
その通りです。やっぱり、海や自然の価値をちゃんと理解しないとダメですよね。日本は、こんなに素晴らしいものを持っているんだから、まずあるものを使い切らなきゃ。

事業も、自分の命も、"再生"させてきた
── 五月女さんは26歳のときにゲイトをつくったんですよね。もともとはどんな会社だったんでしょう。
父の経営していた不動産会社の管理会社としてつくったのが始まりです。バブル景気に乗るようにして会社を立ち上げた父でしたが、僕が24歳の頃には立ち行かなくなっていました。
そこでなんとかしようと、自分で不動産屋の仕事について調べて、営業や所有物件の修繕、銀行との金利交渉までしました。そのかいあって、なんとか会社のお金が回るようになったんです。
── すごい。まさに"再生"ですね。
ただし、ひとつ残ったのが費用の問題でした。不動産屋って、黒字倒産するケースが結構多いのですが、それもこれも、収入が高い割に人件費や材料費がかからないせいで、税金が高くなるからなんです。
どうにかしなくてはと思って、図書館に行って資料をスクラップしながら調べました。その結果、管理会社を別につくってそこにお金を払うことで費用を計上する、という方法しかないとわかりました。そこで26歳のときにつくったのが、ゲイトです。
── そこからすぐに居酒屋を?
いえ、実はゲイトを作ったあとに、もっとすごい人たちと仕事をしなきゃダメだなと思って、コンサル会社に就職したんです。
── ということは、当時ゲイトは副業ということですか......?
そうなりますね。就職先では一応、会社役員と兼業することはできない規定だったのですが、バレたらバレたでいいや、という感じでした(笑)。
でも、過労で倒れちゃったんです。当時は29歳で、月に450時間くらい働いていました。それで、身体が強制終了するかのように、いきなり倒れたんです。病院で検査したら、「自律神経が壊れてますね、社会復帰率4%です」とのことでした。
どういう状況だったかというと、意識と身体がうまくつながっていなかったんです。たとえば今、目の前にあるコップを持とうしたら、何も考えなくても「持とう」と思っただけで持てるじゃないですか。それが、できないような身体になっちゃって。鼻水が垂れても、自分で鼻を拭くこともできませんでした。
── すさまじい......どうやって治療されたんですか?
入院ではなく通院での治療だったのですが、当然、かなりキツかったです。特に薬が強かったから、飲みたくなかったんですね。おかげで自分に合う病院が見つからず、10以上の病院を回ることになってしまいました。
そんな中で、とあるお医者さんに出会ったんです。

とある医師に救われ、食の大切さに気づく
── お医者さん、ですか。
たまたまインターンで来ていた、新人のお医者さんを紹介していただいたんです。いろいろとしゃべってるうちに、彼女が「あなたは客観的に自分を見るもうひとつの人格を持ってるから、大丈夫です。私と一緒にやりましょう」って言ってくれて。
「なるべく薬は飲みたくない」という僕のわがままも聞きつつ、ていねいにカウンセリングをしてくれました。体調が特に悪かったときも「具合の悪いときこそ、はってでも来て」って言ってくれて。
── 心強い味方が現れたわけですね。
彼女に支えられつつ、僕はリハビリを続けました。具体的に何をするかというと、自分の身体と会話をするわけです。今まで身体に「こうしろ」と言っていたのが、うまく通じないので「どうやったら身体と交信できるんだろう」というのをひとつひとつ、頭で考えながら試していきました。
すると、まず「おなかが減る」という感覚を思い出しました。ただ、肝心の「食べたいもの」が見つからない。たとえば自分では「うどんが食べたいかな」と思って、うどんを食べてみるんだけど違ったり。そんなことを繰り返していました。
そしてある日、お寿司屋さんに行ったんです。

── お寿司屋さん......。
食べ物も喉を通らない状態だったのに、なぜか行ったんです。それも回転寿司などではなく、ちゃんとしたカウンターのお寿司屋さんへ。
店の人に「僕、病気で、いっぱい食べられないんですけど、いいですか」って聞いたら「いいよ」って言ってくれて。そこで僕、ヒラメを食べました。そうしたら身体が、「当たり!」みたいな感じになって。
感動したときに心が「じわー」ってなることがあるじゃないですか。それに似たような感覚で、新鮮な魚を食べたことで、身体が感動して「じわー」ってなったんです。
「これが身体が欲しがってたものを食べるということなのか!」と。それから身体と会話をするようになって、リハビリをしている中でも、食べ物の話が多くなっていきました。
── 食の大事さに、気づいたと。
思えば倒れる前の1年間、僕の食生活は悲惨なもので、毎日コンビニのものばかり食べている状態でした。でもこのことがあってから、ちゃんとしたものを食べないとダメなんだな、と気づかされました。
その後はずっと、「運動して、食べて、寝る」を繰り返す生活。日の出と共に起きて朝日を浴びて、とにかく歩いて身体を使って運動する。おなかが減ったら食べて、くたびれたら寝る。
リハビリが終わったのは、3年後でした。ある日、そのお医者さんに「五月女さん、今日でもう終わりです。そして実は、私は結婚したので、今日で病院をやめます。五月女さんはもうひとりで大丈夫だから」と言われました。
── うれしい言葉ですね。
すごく、救ってもらったと思っています。彼女が常々話してくださったのも、やはり食べ物のことでした。「身体をつくるのは食べ物なので、元気になりたければ食べ物をちゃんと選んでください」と。そのことは、今の仕事につながっていると考えています。

復活後、半年で5店舗も居酒屋をつくった
── その後、すぐに居酒屋を始めたんですか。
いえ、回復後に始めたのは接骨院でした。仕事をするにあたって、身体のことを整えたいと思ったんです。求人広告を書いて、先生を雇って、経営を始めました。
ちなみにその店は今、接骨院ではなくリラクゼーションサロンという形で残っていて。著名人や芸能人、経営者の方々などが使ってくださっています。
── 五月女さんは根っからの起業家なんですね。そのあと、居酒屋を?
そうですね。もともとはコンサル時代の先輩がオープンした居酒屋の手伝いで、フランチャイズ化のための営業を行いました。まったく売れなかったんですけど(笑)。わざわざつぶれかかった店舗を再生させる居抜きのやり方は、投資先からは魅力的ではなかったのでしょう。
でも少ない投資で試行錯誤をしながら知見をためていけるのが居抜きの利点ですから、自分でやるビジネスとしては可能性がある。よくできているから自分だったらやるけどなと言ってたら、フランチャイズの加盟店の立場でやってくれと言われて、「じゃあ、やります!」と言って始めました。

── 即答で(笑)。
手伝いとして携わる中で事業構造もわかるようになったし、成功パターンも失敗パターンも学んでいけたので、それを生かせばいいんです。飲食店って、1店舗目を始めるときが一番リスクが高いんですよ。だってその1個がつぶれた時点で終わりですから。逆に言えば、店舗が増えるほどリスクはどんどん減っていきます。というわけで僕は、半年で居酒屋を5店舗出店しました。
そして3.11をきっかけに、漁業と出会う
── すごいペースですね。それが、今のビジネスのやり方の原型になっているわけですか。
そうです。でも、そんな中、3.11を迎えました。当時はすでにいくつか店舗運営をしていましたが、スタッフで亡くなった方はいなかったし、店も完全に壊れたところはなかった。だから続けられたわけですけど、「このままやっていたらいずれ全滅するな」とは思いました。もう一発、地震が来ちゃったら、もう経営が立ち行かないかもしれないなと。
「じゃあ何ができるのか」と考えたときに、せっかく飲食をやっているのだから生産地に事業を分散しようと考えたんです。分散すれば、死ぬ確率は低くなるじゃないですか。とにかく、生きていることが大事だと思うんですよ。生きてさえいれば、また再生できるんで。

── すごく、説得力のある言葉です。しかし、なぜ漁業だったのでしょうか。
海をぼうっと眺めていて、思ったんです。農業では、人が手間暇をかけて育てている。それに対して漁業、特に天然の魚を獲る漁業は、海がつくったものを分けてもらっている。そういった農業と漁業の構造の違いに気づいたんです。これって、すごく可能性のあることなんじゃないかな、と。
つまり僕は、不動産も、居酒屋も、つぶれたところやダメになったところの再生をしているんです。バラバラなことをやっているように見えても、実際は同じことをやっています。加えて、僕には身体を壊したという痛烈な経験があります。そのことが僕の価値観に、大きく影響しているんです。
「生き残ったんだから、おれの命や人生は、世の中のために使おう。身近な人のために尽くそう」。そんな風に思っている部分が、どうしても強いんです。だからどうせ苦労するなら、それを海に向けようと思った。そっちのほうが、企業の活動としては正解だろうなって。
漁業を、"再生"させるには地域のストーリーを生かすこと
── 居酒屋事業と漁業での取り組みに、共通点はありますか?
(ゲイトが定置網漁を行う)須賀利では、大きく投資して大規模にするのではなく、まずは小さく始めて、工夫をたくさん積み重ねるやり方を選んでいます。これは、居抜きの経験が活きているところが大きいです。
実は須賀利の定置網のメンバーは4人だけで、海で定置網を持つのは基本3人だけなんです。もしかしたら少ないと思われるかもしれませんが、トライアンドエラーを繰り返して、だんだんと強くしていくことが大切なんです。そのほうがビジネスとして、持続可能な形になっていくと信じています。

── 新規参入だからといって、大規模に投資する道を選ばないわけですね。
もともと地域でやっていたスタイルを踏襲しなきゃな、と思っていますね。近くの加工場にも人がいて、必要なときは集合する、というように。
本当に大漁だってわかったときには、地域の他の人を呼んで協力してもらえばいいんですよ。大漁なんだから、お礼の取り分を渡したらいい。そうやっていけば、生存確率は上がると思います。
── たしかに、これまでの漁業も、地域があってこそ成り立ってきたものですね。
沿岸漁業は、地域ごとのストーリーを無視できないんです。その意味では、居酒屋の出店とはワケが違う。地域で獲れるものに対して、地域の人々は誇りを持っています。その価値についてしっかり考えながら進めていかなければならないし、それには時間がかかる。
そういったことを東京をはじめとした都会の人たちは理解すべきだと思うんです。実際、ゲイトが県外企業として漁協の准組合員になり、小型定置網をはじめたことで、水産庁の方にヒアリングしていただくのですが、単にルールを変えただけでは、日本の漁業はよくなるとは思えません。
── 地域を理解し、それぞれのストーリーに基づいた方策が必要である、と。
そうです。加えて、理解が足りないのは第三次産業の方々や一般消費者も同じです。もう、大量生産大量消費の時代は終わったと思うんですよ。その自覚を持ったほうがいい。もちろん、食べるなとは言いません。でも、買う側の責任だとか、食生活や買い物を見直さないと、地球は長続きできない。
願わくは、僕の取り組みをきっかけに東京の企業が、故郷や縁の地で活動しようと思えるようになって欲しいです。そうすることで、地域のストーリーに見合ったやり方で、地域を再生させていく例が増えればいいなと考えています。
おわりに

五月女さんは、インタビュー中、こんな風にも語ってくれた。
「広い視点で見た国の課題と、地元の課題。それらをすべて把握すると、共通して取り組むべきは漁業だってわかるんです。日本では衰退しているけれども海外では成功している事例も多い。可能性が大きい。だからこそ、海と水産業を豊かにすると、一番上まで突き抜けられます」
これまで、いくつもの事業を"再生"させてきた五月女さん。その活動は今や、日本の漁業の課題を、大きく動かそうとしている。
生きていれば、再生できる。生きている限り、世に尽くす。
そんな死線を潜り抜けてきたことで培われた五月女さんの覚悟は、日本の海と漁業に一筋の光を差そうとしている。
私たちの命を根本から支える、"食"を入り口にして。
-
文くいしん
twitter: @Quishin
facebook: takuya.ohkawa.9
web: https://quishin.com/
-
写真尾形希莉子
twitter: @kiriko_buntan