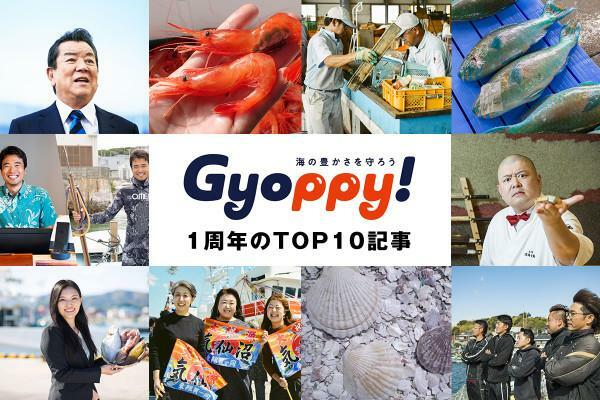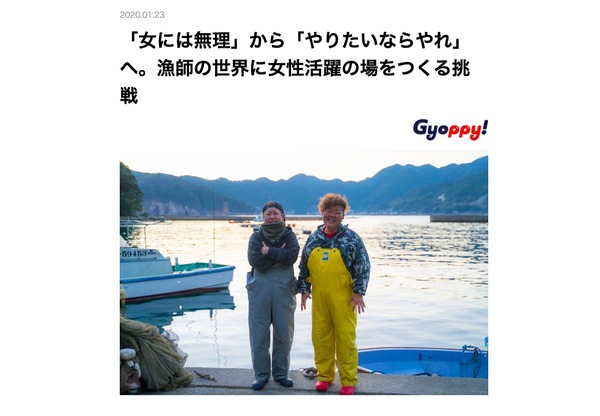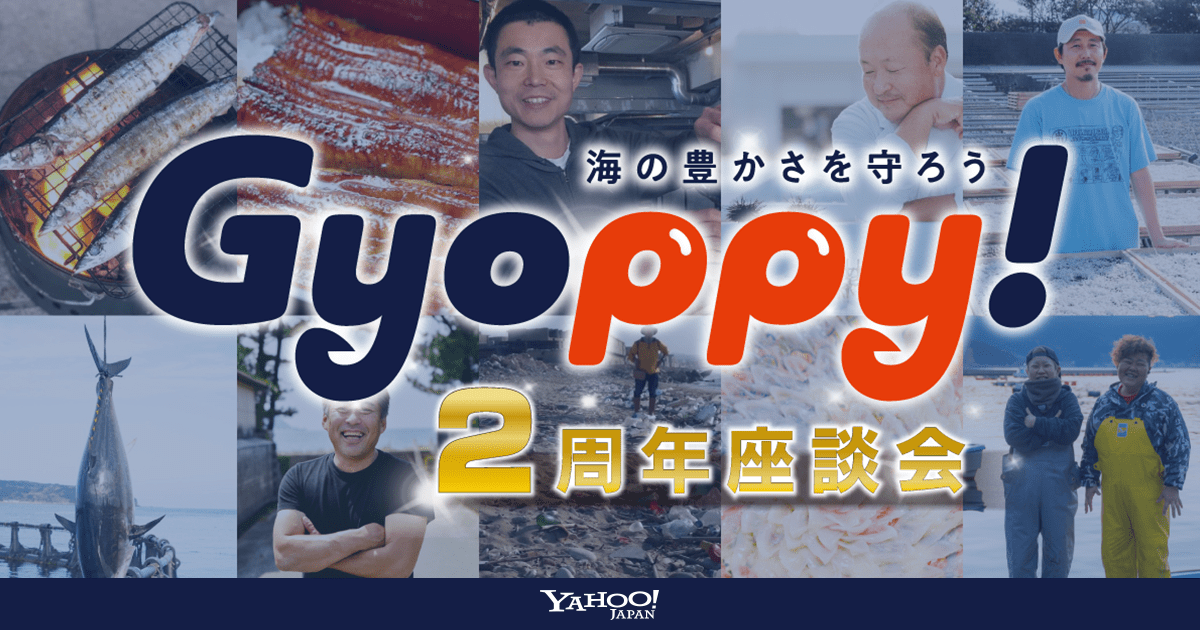この1年で読まれた記事は? いつ読んでも古くならない言葉たち【Gyoppy!2周年記念】

「海の豊かさを守ろう」「海から、魚から、ハッピーをつくる」を掲げるメディア『Gyoppy!』は、2020年10月3日にオープンから2周年を迎え、3年目に突入。
これまで、全国の漁村や海の専門家の元を訪ね、浜に古くから伝えられてきた漁に対する考え方から最新のテクノロジーまで、さまざまな知恵や知識をインタビュー記事に変えて発信してきました。
今回は、メディアのこれまでの歩みを振り返る「2周年記念座談会」を開催。プロデューサーの長谷川琢也、編集長の久保直樹(両名共、ヤフー株式会社)を迎え、オリジナルコンテンツ編集長・くいしんを聞き手に、メディアにとってのこの1年を振り返ります。

これまでにないほどの社会の変化が起きた2020年。座談会では、社会変容の荒波に揉まれたメディア編集部の苦労話が続出......するのかと思いきや、話に出てきたのは「やるべきことは変わらなかった」「海で働く人たちの言葉には、変わらない価値があった」という力強い言葉たち。
2年目のGyoppy!が、メディアとしてブレない活動をできたのは何故なのか? 多くの記事の根底には、「海の未来を考えることは、社会の未来を考えることにつながっていく」というメッセージがありました。いくつかの記事をもとに、海に関わる人々の言葉を振り返っていきます。
目指すべき姿が固まってきた2年目だった

── さっそくですが、本日はGyoppy!の2年間を振り返っていこうと思います。
── 初年度は、手探りな部分もありながら、『Gyoppy!ってどういうメディアなんだろう?』と考えていった一年でした。そして、2年目のランキングはこちらです。
Gyoppy!ページビュー数ランキング(2019年10月1日~2020年9月30日)
1位:サンマが獲れないのは中国のせいじゃない? メディアが伝えない不漁の真実
2位:ウナギを食べ過ぎると絶滅するらしいけど、結局食べていいの? 専門家に聞く4つの質問
3位:コロナで卸値は半分。美味しい魚がリーズナブルだから、いろいろ食べてみよう
4位:鉄腕DASHでおなじみ! 海を荒らすウニに廃棄キャベツを与えてプリプリに。マイナスの掛け合わせが海を救う?
5位:相手を変えるには、否定しないこと。有名人も薦める、しらす業者の対話力
6位:養殖マグロはなぜうまい? 人気寿司店が惚れた長崎「鷹島本まぐろ」の現場から知る
7位:競争をやめたら、生活も魚も守られた。30年前から続く「漁師の約束」
8位:人体に影響はない、はウソ。マイクロプラスチックの影響がわかり始めている
9位:政治のせいで高級になった魚!? 「ふぐ」が未来の人類を救うかもしれない
10位:「女には無理」から「やりたいならやれ」へ。漁師の世界に女性活躍の場をつくる挑戦
── この結果を踏まえつつ、2年目の振り返りをしていきたいと思います。はせたくさん(長谷川琢也、以下はせたく)は、特に印象に残ってる記事はありますか?
- はせたく
- 何と言っても、2年目が始まってすぐに「もうこれを超える記事は出ないんじゃないか?」と思えるくらいのヒット記事が出ました。東京海洋大学の勝川先生に取材した記事。ここから2年目の方向性が定まった感覚があるよね。
── 編集を担当した僕としても、強く印象に残っています。
- はせたく
- テーマとしては、1年目のヒット記事『たくさん獲るのをやめたら、儲かって休みも増えた。佐渡のエビ漁に見えた希望』とも近い資源管理の話なんですけど。「サンマが不漁で食べられなくなる」という世間の話題に対して、その実態を聞きました。
- 久保
- この記事に関して運営側として喜ばしかったのは、「ヒットにするつもりでヒットにできた」ということですよね。世間の関心、国際関係のこととか、いろんな要素を意識して「このタイミングでこう見せよう」というチャレンジをして、きちんとその結果が出た。
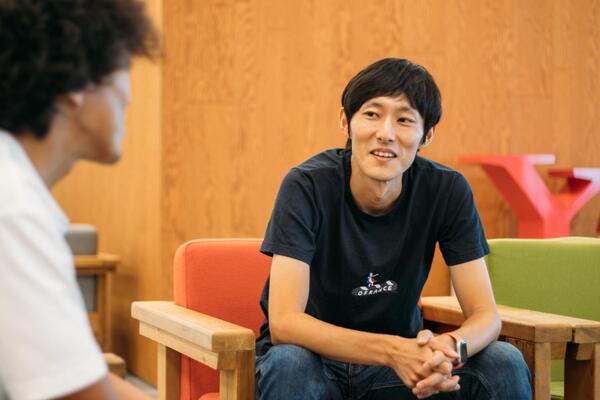
- はせたく
- やっぱり、「海の話だけでは読んでもらえないんだ」ってことは1年目に気づいたよね。佐渡のエビ漁の記事も、「たくさん働くのをやめたら」「儲かった」っていう、働き方改革やビジネスの視点があったから読まれた。「ビジネス層に刺さるテーマを工夫して組み込めば、より多くの人に読んでもらえるかも」という期待が、確信に変わった記事だった。
── 編集として思ったのは、「あれだけメッセージを盛り込んでも、きちんと読んでもらえるんだ」ということで。
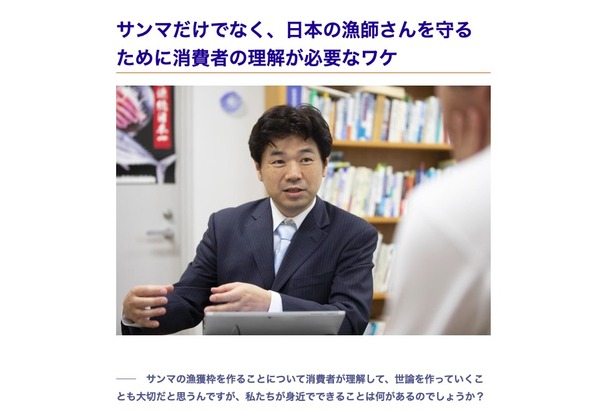
── 記事の後半にある「買い物をすることって、守りたい未来に投票することにつながる」って話は、消費者へのメッセージそのものなんですけど。「魚が高くなった!」って騒ぐんじゃなくて、未来のサンマを守るために、今の僕たちが適正な値段でサンマを買おうよって。
- はせたく
- 大切なメッセージだよね。
── 「サンマだけの話に絞るなら、後半のメッセージはなくても成立する。その上で、入れるかどうか」と、最後まで悩んだポイントだったんです。でもハードルが高いとしても、本当に伝えたい内容をしっかり入れた上で公開した。その記事が受け入れられたことで、複雑な問題を複雑なままに伝えても、ちゃんと読んでもらえるんだなって、メディアとしての自信を持てました。
- はせたく
- 「未来へつなごう」というメッセージは、自分もインタビューをするときに必ず意識するし、編集側でも記事に込めてくれるもんね。海や自然の生き物と向き合い続けてる漁師さんたちは、時間軸的にも長い視点で物事を見ている人が多い。海の未来を考えている。そういう話って、いつ読んでも古くならないと思う。

- はせたく
- 「未来に向けた、普遍性のあるテーマ」っていうのは、Gyoppy!の記事のひとつの方向性になってきた。それはサンマの記事でハッキリしたし、この記事があったから、未来のための資源管理をテーマにした『ウナギを食べ過ぎると絶滅するらしいけど、結局食べていいの? 専門家に聞く4つの質問』の記事も自信を持って打ち出せたしね。
- 久保
- うなぎの記事はSNSの反応も良くて。見ていると、「うなぎがどうなるかは、自分たちの食べ方とか、行動次第なんだ」と、うなぎの減少を自分ごととして考えてくれる声が多かったです。メディアとして、やはり「消費者の意識・行動を変えたい」という思いでやってきたので、少しずつではあるけど、ちゃんと届いているんだと嬉しくなりましたね。
SDGsはブームじゃない
── 自分で言うのもなんですが、Gyoppy!はすごく真摯にSDGs(※)と向き合えているのかなー、というのは2年目に改めて思いました。海について考えることって、自然と向き合うことだから、本質的にサステナブルに考えざるを得ないというか。
- はせたく
- SDGsってそもそも、「ブームだから実践しなきゃ」「発信しなきゃ」なんてものじゃない。それこそ漁業に携わる人たちは当たり前に考えてきたことで。もともと考えるべきだった「環境への配慮」と「持続可能性のある産業」について、俺らは正しく学んでいかないといけない。
── 「サステナブルであることが、人々の本質的な幸福につながっていく」みたいな価値観も、この2年間で急速に伝わり始めている感じがしますね。数年前に比べたら、Gyoppy!の記事も世の中に届きやすくなっているかも。
- はせたく
- そうだね。「社会課題はビジネスで解決しないといけない」って価値観が広まり始めている実感もある。1年目の『「場所を変えたら正当な評価を得られた」沖縄の''青い魚''がアジアで売れる理由』が多くの人に読まれたのも、社会的なアクションを起こすことで、ビジネスもちゃんと回るって意識が読み手にもあったからだと思うし。海の話から、持続可能性をどう考えるべきかのヒントを得てくれてるんだと思う。
── SDGsの文脈で言うと、2020年は、女性が漁業に参加する文脈の記事も読まれました。
- はせたく
- SDGsと一口に言っても、「海の豊かさを守る」だけじゃないもんね。Gyoppy!は海を舞台にしながら、広く、社会のことを考えられるメディアになってきたんだと思ってます。
コロナ禍のメディア運営
── 新型コロナウイルスの影響で、世の中が大きく変わってしまったわけですが。その点、メディアとして何を思ったかという部分もお話しておきたいなと思いました。
- はせたく
- 正直に話すと、そこまで大きな方針の転換はなかったよね。現地取材がしづらく、ほとんどの取材がオンラインになったという変化はあるけど。この状況になったから、メディアを決定的に考え直さないといけない、なんてことはなかった。

- はせたく
- 今回のことで多くの人が、自分たちの暮らし方や社会のあり方に疑問を持って、「持続可能になるために、どういう考え・態度・行動を取るべきなのか」って考え直したと思うけれど、それだって海に携わる人たちからしたら、昔も今も変わらず考えていることというか。普遍的なテーマなんだよね。
- 久保
- また別の角度から見ると、現地取材が難しい分、過去の取材記事を発掘できたのはメディアとしてよかったですね。工夫としては、運営母体であるヤフーの仕組みを利用してメールマガジンを配信しました。

- 久保
- 2020年5月に配信したメルマガで、2019年12月に公開した『相手を変えるには、否定しないこと。有名人も薦める、しらす業者の対話力』という記事がとてもよく読まれました。
── なぜ今の状況で、昨年の記事を配信しようと思ったんですか?
- 久保
- この状況になって、「自粛警察」みたいな人がたくさん出てきましたよね。その主張もわかるけれど、個人的には「押し付けるだけじゃ伝わらないのに」という歯がゆい気持ちも強くて。この記事で語られた「相手の事情を配慮しながら、目指すべき未来を共有する」というしらす業者さんの姿勢は、今こそ見直されるべきなんじゃないかと。
- はせたく
- 今の時期に読み返してみると、「押し付けずにどう伝えるか?」という悩みはGyoppy!の姿勢としても改めて勉強になった。「どうしてこうしないの? こちらが正しいのに!」なんて伝え方では、誰も聞き入れてはくれないだろうから。記事のテーマは資源管理だけど、コロナ禍の行動倫理って文脈に置き換えても「相手を否定しない対話」の大切さは伝わったよね。

- はせたく
- 普遍的な記事作りを意識する一方で、世の中の文脈を捉えながら記事で発信していくのも大事だと思ってる。海洋マイクロプラスチックの問題を主軸に、プラ関連の取材を重ねていったのは、2年目の大きな変化かなあ。
── レジ袋が有料化したとか、世間的な関心は高まっていたと思います。
- 久保
- ここ1年くらいで急速にプラスチック問題への関心の高まりを感じていました。だからこそ、もっとこのテーマを伝えていくために、パートナー企業さんに協力をしてもらったんですよね。環境系の記事に強い『エコトピア』というメディアからいくつも記事を配信してもらって。
── 『エコトピア』さんの記事は反響もすごかったんですよね?
- 久保
- そう。記事の中で「レジ袋は絶対よくないよ」と発信するんじゃなく、プラスチック業者の事情も合わせて聞こうとしていたので、読者から「環境メディアがきちんと両論を伝えようとすることに、好感が持てる」という反響の声が上がりました。
── ある意味、しらす業者さんの記事から学べた「相手の事情を否定しない姿勢」と同じというか。善悪の二項対立にせず、反対側にいる人たちの意見もちゃんと発信することは大切だと考えています。
- 久保
- この間、「みなと新聞」の方とお話したんですが、「Gyoppy!に取り上げられる人はだいたい知っているけど、それでも『この人はこういう人だったんだ、こういう考えがあったんだ』って発見がある」と言っていただいて。
- はせたく
- やっぱりGyoppy!は"人のメディア"でもあるよね。業界では脚光を浴びていた人に、ちょっと違う部分から光を当てて。マニアックだけど海のことをがんばってる人を一般の人に「こんなおもしろい人がいるよ」って伝えていく。

3年目に向けて
── 海にまつわる課題と取り組みを取材することで、社会を持続させるためのヒントを得てきた2年目だったと思います。これから始まる3年目は、どうしていきましょう?
- 久保
- やっぱり、サンマ級の記事をこれからも出していきたい。あれだけ読まれたら、一般の方の海に対する意識を本当に変えていけるんじゃないかな、って実感ができたので。
- はせたく
- 「海から、魚から、ハッピーをつくる」ってメディアの理念に沿って活動してきて、取材相手の方も制作陣も含めて、いろんな人を巻き込んできた。俺たちが学ばせてもらったことを世の中に伝えるためにも、ちゃんと読まれる記事をつくるのは、大切なことだよね。
メディアをやればやるほど、海について考えることが社会のいろんな物事を考えることにつながっていくはずだって、当たり前のことを思い出すんだよね。「海の豊かさを未来に残す」って言っても、そのためには俺たち人間が未来に残らないといけないから、社会全体の話を考えないといけない。

── 立ち上げ期によく話していた、メディアとして伝えるだけではなくて「具体的なアクションを起こしていく」ってこともこれからやっていきたいですね。
- はせたく
- そうだね。イベントを開くとかもひとつの形だけど、もっと多くの人を巻き込んでいきたい。そういう意味では最近、Gyoppy!にナレッジ(知識・知見)のシェアを求められる機会が多くなって。イベントで持続可能な漁業の先進事例を伝える機会が増えてきた。
── それはいい機会ですね。オフラインで発信することには、記事制作とはまた違った意義がありそうです。
- はせたく
- メディアもひとつの手段でしかないし、プロジェクトGyoppy!としてはあらゆる方法で人と海をつなげていきたい。記事を書いてくれたライターさんや、写真を撮ってくれたカメラマンさんだって、一度海に触れて知れば、もう海のことを無視できなくなる。関わってくれた人の海への意識がひっくり返る瞬間をたくさん見てきた分、小さいところから海と人をつなげていきたいですね。

-
文いぬいはやと
Twitter: @inuiiii_
-
編集くいしん
Twitter: @Quishin
Facebook: takuya.ohkawa.9
Web: https://quishin.com/